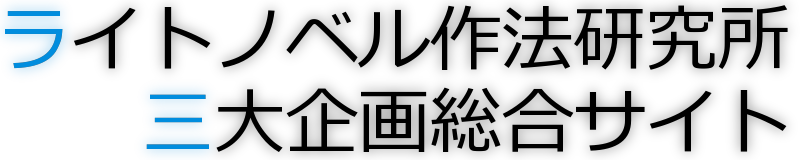2011夏祭り企画優秀作品
『ご主人様に育てられた私がダメすぎる』

【使用したお題】
何の役にも立たないもの、ささやかな悪意
【一行コピー】
ただいま、絶対絶命まっただなか!

下っ端な私でも、戦闘とは冒険者にとっての「華」だという考えには諸手を挙げて賛成したい。
鍛え上げた力と技で薙ぎ倒し、修めた英知で屠り去る。そりゃあ敵を倒して得られる経験値と報酬にも魅力はある。でも、やっぱり己の能力を開放して戦う事そのものが、冒険者にとって生き甲斐であり、醍醐味なんだよ、きっと。
だから、私は常々不満に感じてたんだ。
私だって冒険者なんだから、戦闘に参加させてよーって。
でも、私がそんな不満を口にする度に、ご主人様は決まってこう言うのだった。
「STR(腕力)が3。おまけに魔法も使えない。ただ、LUK(幸運)とAGI(素早さ)が高いだけのお前が、一体何の役に立つんだ?」
それは私が一番知りたかった。
だって、私をそのように成長させたのは、他ならないご主人様だったのだから……
「ギダンとアルティアが一瞬で?! うわぁぁぁ、なんなんだ、あいつっ!? やめろ、来るな! 来るなぁぁ!!」
いつもと同じように始まった戦闘。まぁ、ダンジョン入ってすぐの大広間でボスらしき魔物が出てきたのには面食らったけど、ご主人様が「手間が省けていいや」なんて言っていたのは、ほんの一分前の事だった。
ホント、たった一分前だったんだよ?
それなのに私たちパーティの主力である傭兵ふたりは、ボスの火炎攻撃の前に火だるま、すでに生命活動を停止していた。
「馬鹿な! ギダンはHP999MAXの体力バカ、アルティアは耐火能力A+なんだぞ、それなのにどうして!?」
絶体絶命な状況にも関わらず、ご主人様の説明的なセリフは一見すると余裕があるように思えるかもしれない。でも、
「ごごごご主人様? お願いですから、私の後ろに隠れるの、やめてくださーい!」
「なんだとー! ご主人様の大ピンチなんだぞ、身を挺して俺を守るのがお前の仕事だろうが!?」
私を盾にしてぶるぶる震えるのは止めて欲しかった。
ひええ、ご主人様、男の人が女の子の後ろに隠れるだけでも世間的にはどうかと思われるのに、仮にもレベル69の勇者がレベル30のメイドの後ろに隠れないでくださいよぉ。
「普段は何の役にも立たないのだから、こういう時こそしっかり働け!」
「ひどい! 私が戦闘で役に立たないのって、元を辿れば全部ご主人様のせいじゃないですかー」
私はじたばたと暴れて抵抗する。でも、ご主人様も必死で、がっちりと私の体を捕まえて離さなかった。
てか、どさくさに紛れておっぱいを掴むなー、このエロバカぁ!
非常事態にただただ慌てる私たち。そんな私たちを尻目に、非情にもボスは掲げた右手に炎の球を出現させた。ギダンさんを殺った時は炎輪だった。アルティアさんの命を奪ったのは、地面から現れた火柱だった。そして今回は炎球。なんともバリエーション豊かな炎攻撃を持っているボスだ。
って言うか、絶対これ、私たちを実験台にしてるよなぁ。
そんな事を考えながら泣きそうな表情をしていると、ボスはにやりと微笑って炎球を掴み、私めがけて投げ込んできた。
「うひゃぁ!」
私は慌てて首をひっこめる。後ろで「ちょ、おま……」と声が聞こえたような気がした。
うん、聞こえなかったことにしよう、そうしよう。
圧倒的な熱量を持った魔法の塊が、私の頭上すれすれを通過していく。髪の毛の何本かが焼け縮れ、うなじに日焼けしたような痛みが走る。そして空気を震わせる轟音と、何かを強引に吹き飛ばすかのような激しい振動。だからまさにその瞬間は、本当に声は何も聞こえなかった。
私を通り越した炎球が、壁にぶつかって爆音を発する。爆風で吹き飛ばされそうになるのを堪えながら、私はなんとか後ろを振り返ることが出来た。
そこには私の体をまだ掴んでいる、炎球で頭を吹き飛ばされたご主人様の亡骸があった。
はん年ほど前、私が仕える伯爵様のご子息が「実は俺、勇者だったんだ!」なんて言い出した。
私たち侍女は「んなわけないじゃん」なんて影で話していたけれど、伯爵様はこの発言を大いに喜ばれて「勇者ならば魔物退治の旅に出なければならんの」と、筋肉達磨な武闘派僧侶と妖艶な女魔導士を高額で雇い入れ、旅のお供とした。
きっとニートなご子息の、アホな夢物語ではあるものの、前向きな発言がよっぽど嬉しかったのだろう。まぁ、二人の屈強な傭兵をつけたあたりは過保護すぎるけど。
でも、ご子息のお世話係りである私は、旅立ちを心から喜んだ。なんせこのご子息、性格悪いし、おまけにエロい。すれ違いざまにお尻を触るわ(偶然を主張)、女湯を覗くわ(疑惑調査中)、夜這いをかけるわ(未遂。本人は寝ぼけてたと否認)。伯爵様は立派な方なのに、どうしてこんなエロバカが生まれたのかと、私は日々嘆かずにはいられなかった。
しかし、そんな毎日も明日で終わりという、旅立ち前日の夜。
「ええー! 私も一緒に行くんですかー!?」
伯爵様に呼び出されて出向いた私に、トンデモナイ命令がくだされた。
「いや、でも私、単なるメイドですし。旅のお供なんて、お邪魔になるだけですよぉ」
思わず、あんなご子息と一緒に旅に出るなんて死んでもイヤと本音が出かけたけど、それはぐっと飲み込んだ。
「そ、それにほら、冒険者ってギルドが発行する『ステイタスカード』が必要じゃないですか? あの黒光りする、個人情報満載のヤツ。私、あんなの持ってないですし、これがないと冒険者として認められないんですよね?」
私はさらに「私が同行できない理由」を並べ立てる。
そう、思い出したのだ。自称勇者のエロバカご子息が自慢げに見せびらかしていた、冒険者ギルド発行の不思議なカードを。縦十五センチ、横五センチほどのそれは、カードにしては厚みがあって、大きさの割にずしりと重量感があるのは紙ではなく金属で作られているから。そして、その金属板の表面を撫でると、不思議な事に表面が発光し、持ち主の身体的能力や技能などが映し出される。さらに各項目からの詳細なデータ参照も可能で、まさに個人情報の塊みたいなものだった。
なんでも旧文明の遺産からギルドが作り上げたものだそうで、これを持っていることがすなわち冒険者としての証らしい。冒険者が各国を自由に闊歩出来るのも、ギルドが身分を保証してくれるこのカードあってこそだ。
しかもコレ、成長具合を『レベル』という概念で具体的に数字で表現し、レベルアップで得られる成長ボーナスを自由に各能力に振り分けたり、技能の習得を選んだりすると、なんと実際の体にも変化が起き、技能を身に付けているという優れものだ、
一体どんな理屈かはさっぱり分からないけれど、ロストテクノロジー、まじパネェのだった。
まぁ、それはともかく。
今の私に重要なのは、このカードがないと各国を自由に行き来できないと言う事。カードを持っていないのだから、残念ですけど私はお供できないですよと主張しているのだった。
ところが。
「はっはっは、キィ。それなら心配ないぜ!」
部屋の片隅、ランプの明かりも届かない書架の物陰から、私の名前を呼んでここぞとばかりに満面の笑みを浮かべて登場したのは、言うまでもなく、件のバカご子息だ。
そして、その手には黒光りする冒険者ギルド発行のステイタスカードが……
「こんな事もあろうかと、すでにお前のステイタスカードは作っておいたんだ、ひゃっほーい!」
カードが発光して、私のバカみたいに笑っている顔が浮かび上がる。その横にはしっかり私の名前「キィ・ハレスプール」と表示されていた。
「うわわわ、勝手にそんなの作らないでくださいよー。あ、ちょっと、見ないでぇ!」
カードを操作して情報を堂々と見ようとするバカ。私はもちろんカードを奪い取ろうとする。
でも、悲しいかな。このバカご子息、態度もでかいけど、図体もでかいんだ。必死になって奪い取ろうとする私を軽くいなしながらカードを持つ手を高々と上げて、私の個人情報を次々と読み取っていく。
「しかし、キィ、お前、ほんとに見たまんまの性能だなぁ。なんだSTR(腕力)3って? これでは持てる武器も『はたき』くらいなもんだぞ?」
「私はメイドなんですから『はたき』でいいじゃないですか!?」
てか、冒険者の中では『はたき』も武器扱いなんだ?
「お!? 次は身体データだ」
「うわー、やめてー、見ないでー。そこは見ちゃイヤー!」
一番恐れていた情報を前に、私は更なる抵抗を試みる。そこは乙女の秘密なんだ、そんなに簡単に見られてたまるかっ!
ええい、こうなったら最終手段、発動すんぞ!
私はここぞとばかりに思い切りバカの股間を蹴り上げた。なんとも切なそうな苦悶の表情を浮かべて倒れこむバカの手から、カードが滑り落ちてコツンと床で音を立てる。私はすかさず拾い上げると、取り返されてなるものかと後ろ手に隠した。
「貴様ぁ、いくらなんでもやりすぎだろぉぉ!」
「いやいや、やりすぎなのは、坊ちゃんの方ですよぉ。勝手にこんなの作って、あろう事か個人情報まで見ようとするなんて。やりすぎです」
床で股間を押さえて涙目のバカに、あまりにおいたが過ぎると訴えますよと目で告げる。
でも、そんな私の訴えなんかどこ吹く風とばかりに、私には理解できない痛みから回復してきたバカご子息はふふんと笑うのだった。
あ、イヤな予感がする……
「まったく、お前は本当に浅はかなヤツだ。俺がどうしてお前のステイタスカードを作ったのか、その真の理由を全く分かってないな?」
イヤな予感がどんどん大きくなっていく。
「いいか、よく聞け。冒険というものはな、そりゃー大変なもんなんだ。太陽が照りつける灼熱の砂漠、光も届かないような深い森、時には稲光の荒野を行き、おまけに常にモンスターとの戦闘の危険性に満ちている。そのような時にだな、『いやん、服のサイズが合ってなくて自由に動き回れなーい』なんて事があったら大変だろうが?」
一息でそこまで言うと、激烈バカはクローゼットから一着のメイド服を取り出した。
「そこまで考えて、ほれ、『冒険者メイドクラス専用』のメイド服を新調してやったんだ! カードのデータをもとに身長や体重などはもちろん、今の胸のサイズまで完全に把握した上でのオーダーメイドだ! 泣いて喜べ!!」
「喜べるかー! ってか、マジ泣きだぁぁぁ」
あああ、私の乙女の秘密が、よりによって一番知られちゃいけないヤツに、しかもそんなくだらない理由で。
あ、頭が痛い。私は思わず頭を抱え込んだ。
そしてそんな自ら取った行動を、私はすぐ後悔する事になる。
「ふん、カード再奪取、大成功だ!」
バカご子息が、無防備な私の手から素早くステイタスカードを奪い取っていた。
「これはパーティのリーダーである俺様が管理してやろう。喜べ、勇者様を保護する忠実なメイドとして成長させてやるぞー」
「やめてー。そんなぁ、私の意思はどうなるんですかぁ?」
私は再度カードを奪い取ろうとするが、敵もさるもの、間合いに入れさせてもらえない。
「そうだ、今日から俺の事を『ご主人様』と呼ぶように、あとでキィのカードに設定しておいてやろう」
うわぁ、なんて極悪なチート機能まであるんだ、そのカード。
「さぁ、キィよ、とびきりワクワクな冒険が始まるぞ。スリルいっぱい、危険がいっぱい、でもそこに俺様の栄光の道がある! 勇者である俺の冒険を、その目にしかと刻み付けるがいい!!」
かくしてバカ改めご主人様(自分の意思とは関係なく、そう呼ぶよう設定されているのが口惜しい)の冒険が始まり、そして。
今、終わったのだった。
ご主人様の、意識を司る部分を失った体が、やがて力なく地面に打ち倒れる。
私の後ろに隠れつつ、最後まで私のおっぱいに手を掛けていたのが、あのエロバカご主人様らしかった。
「ご主人様、ここに眠る。辞世の句『ちょ、おま……』は、さすがに情けないから『我が命ここに尽きるとも、この世に光尽きる事なし!』とか適当に伯爵様にはお伝えしておきますね」
私はそんな事をつぶやいてみる。当然だけど、返事は無かった。
いつもだったら「そんなセンスのない辞世の句なぞ、俺は認めんぞー」って怒るのに。
いや、もしかしたら「俺と一緒に冒険したおかげでセンスが上がったな」と褒めてくれるかもしれない。
……まぁ、褒められても嬉しくないんだけどね。
私はご主人様だった体をコツンと蹴ってみる。重厚なプレートアーマーの隙間から黒光りするカードが二つ転げ落ちた。
私と、そしてご主人様のステイタスカード。
拾い上げると、ご主人様のカードの表面に私の手が触れ、見慣れた顔が映し出される。二枚目を気取った三枚目の、精一杯かっこつけた表情。その下に見慣れない「DEAD」の文字が浮かび上がっている。
明らかな死体を見ているのに、私はそこでようやくご主人様がお亡くなりになった事を実感した。
正直、スケベで、わがままで、私に対して好き勝手放題なご主人様だったし、何一つとして良い想い出なんて無いのだけれど、少しだけ涙が出そうになって慌てて上を向いた。
とにかくご主人様の冒険がここで終わったという事は、私の冒険も終わったという事だ。伯爵様にこの結末をお伝えするのは気が重いけど、それは私に課せられた義務というもの。しっかり果たした後、私は、私の人生を生きていこう。
私は顔を上に向けたまま、うーんと背伸びをした。軽やかだった。長年縛り付けられていた鎖が解き放たれた感じだ。
よし、行こう!
私は、新たなる人生の一歩を踏み出した。
「いや、ちょっと待て!」
そんな私を引き止める声が……
「あ、やっぱりダメ?」
回想シーンの流れから上手くこの場を立ち去ろうとした私を、当然だけれどダンジョンのボスは逃してはくれなかった。
くそー、巧妙に「逃げる」戦術を取ったつもりだったのに。
やっぱりボス戦に「逃げる」は無効なのだった。
「主を失いし人間の娘よ、変わった術を使うようだが、余には効かぬぞ」
そいつはくっくっくと嗤った。実にボスらしかった。
そもそもコイツ、外見からして実にボスらしい。長身痩躯な体型。漆黒のマントに映える金色の長髪。焔のように逆立つ眉。切れ長の眼に天突く高鼻。そして両耳の後ろから生えている立派な角。何故かいきなりダンジョン入ってすぐに対面したけれど、一見してボスだと分かる特徴に溢れていた。
そして事実、その能力の凄まじさたるや今さら語る必要もなく、これまた言うまでもなく私に勝ち目なんてこれっぽっちもない。だから回想・別れ・旅立ちという一連の流れを作り上げて逃亡しようとしたのだけれど、これが効かないとなるとお手上げだ。
と言うことで、私は本当に両手を上げた。降参だ。
ところがボスは眉を顰めて、不思議そうな面持ちで両手を上げる私を眺めた。
「なんの真似だ?」
あれ? 意味が通じない? ああ、そうか、この格好って「両手に何も持ってませんよ降参ですよ」というジェスチャー以外にも、世界中から元気を集めていたり、ハラキリアタックを敢行する前動作にも見えるのかもしれない。
と、すると、アレだ。白旗だ、白旗。どっかに白い布はなかったかな?
私は体中をまさぐって、白旗になるような物を探した。
「娘よ、降参という意味は余にも分かる。が、ボス戦で『逃げられない』ように、『降参』なんてコマンドも普通ないであろう?」
「ああ、そうか、しまったっ!」
ボスの言葉に、私はうぐぅと唸るばかりだ。
「その様子では分かったようだな」
私の様子を見て、深く頷くボス。そして
「では、そろそろ死ぬがよい」
唐突に、そう、本当に唐突に、火の玉を飛ばしてきた。
「うわー、あぶなっ!」
間一髪、体を捻って避ける私。危なかった、ホントに今のはギリギリだった。その証拠にメイド服のエプロンのレースにちりちりと炎が燃え移っている。慌てて私はぱんぱんと冒険者メイド専用グローブ、通称なべつかみを使って鎮火にあたる。
「ほぉ、先ほどといい、なかなかの反応だ」
ぱんぱんエプロンを叩いている私を見て、ボスはさも楽しそうにニヤリと口角を上げる。
「ならばこれはどうだ!」
ボスが軽く片手を振るうと、今度は炎の波が空中に現れた。炎が波のようにうねって迫ってくる様子は、さすがは魔法という有り得なさだ。
私はすかさずしゃがみ込んで波が頭上を通過するのを待つ。
「バカめ!」
そんな私を見て、ボスは振るった手の指先を下方に向けた。
あ、ヤバい。私は考える間もなく、そのまま前方にでんぐり返り。直後、私がしゃがみこんだ位置に炎の波が垂直落下するのを、私は翻るスカート越しにはっきり見た。危ない危ない、のん気にしゃがみこんでいたら、今頃炎の波に全身大火傷を食らわされるところだった。
と、安心するのも束の間、今度は急速に足元が熱くなって来るのを敏感に感じ取る。すかさず横っ飛び。案の定、私が居た場所から炎が噴出してきた。
「なかなかやるっ!」
ボスが地面をつま先でタッピングする度に、地面から火柱が吹き荒れる。それを私はもう奇跡的としか言いようのない動きで避け続けた。
「楽しい、楽しいぞ、小娘! お前の悪運が尽きるのが先か、余の魔力が枯れるのが先か、面白い勝負になりそうだ!」
「面白くない! ちっとも面白くないよぉ~」
私は泣きそうになりながら、それでも必死に炎の攻撃を避ける。
かくして炎輪、炎弾、炎波、炎柱、ありとあらゆる攻撃が繰り広げられるボスの発狂モードが、延々三十分近く続いたのだった。
人間というのは自分の事を全て理解しているつもりで、実は全然知らないものらしい。
私はボスの怒涛の攻撃を、どういうわけか、見事に避け続けていた。
正直、冒険に出るまでの私はこんな俊敏ではなかったから、これはやっぱり遊び半分でご主人様が成長させたLUKとAGIの賜物と考えるべきなのだろう。何の役にも立たないと思っていたら、弾幕用能力者並みの当たり判定になっていたとはっ。人生、どこでどう転ぶか分からないものだ。
でも、避け続けているだけでは勝機はないんだよ、困った事に。
だから、私は
「そんな攻撃なんか効かないわ! 私を倒したいのなら、貴方の究極魔法を放ちなさい!」
何十発目かの炎弾をかわして、大見得を切った。
驚きで切れ長の眼を見開くボスに、私は一気に畳み掛ける。
「貴方の究極魔法で私を倒せば貴方の勝ち。倒せなかったら私の勝ちで、私を見逃してやりなさい!」
そして格好良く上から目線で、情けない事を言ってやった。
だってしょうがないんだもん。攻撃を避ける事は出来ても、こちとらSTR(腕力)3だぞ。そんな非力でボスが倒せるかっ。
生き延びるにはボスが「こいつは倒せん」と認め、見逃してくれる以外に考えられなかった。
「余に究極魔法を唱えろ、だと?」
ボスが呟く。そして最初は押し殺したような声量だったのが、やがて「くっくっく」と私にもはっきりと聞こえるほどに笑い始めた。
「魔王である余に、このような愚かな提案をする者がいるとは思いもよらなんだわ」
笑い声は「くっくっく」から「はっはっは」に変わっていた。
というか、この人、今さりげなくとんでもない自分の正体をカミングアウトしなかったか?
「面白い。面白いぞ、人間よ! その願い、叶えてやろう。我が最強の魔法を、見事避けてみせるがよい! あーはっはっは!!」
ボス、いや、魔王の笑い声が洞窟に響き渡る。見事な悪人笑い三段活用だったなと感心しつつ、しかし、私のさきほどまでの勢いはどこへやら、額に冷や汗が流れ落ちた。
魔王? ウソでしょ?
「様々な呪文の複合詠唱ゆえに、この究極魔法は余でも三分近く時間がかかる。おぬしの能力を侮るわけではないが、死にたくなければ、その三分の間に余を攻撃し、詠唱を止めてみせるのが唯一のチャンスと思ってよいだろう。用意はいいか、勇敢な人間の娘よ?」
「お、おっけー」
それまでと全く変わらない魔王の声に比べて、私の声は明らかに震えていた。
だって、魔王だよ、魔王。
その存在は誰もが知っているくせに、誰一人としてその正確な情報を知らない。それが魔王、つまり伝説や御伽噺の中に登場する存在で、そういう意味では神様なんかと変わらない。
なのに、まさかそれが今ここにいて、しかも究極魔法を唱えようとしている。
……死んだな、わたし。
さっきまで私なら絶対避けれると信じてやまなかったのだけど、魔王と知ってしまった今、そんな自信はどこかに吹き飛んでしまった。
「では、詠唱を開始する。健闘を祈っておるぞ。くっくっく」
とても健闘を祈ってもらえているとは思えない邪悪な笑いを最後に魔王は目を瞑ると、高音と低音を同時に発音しているような、まるでひとりで合唱しているような詠唱を始める。それはとても不思議な音調で、思わず聞き入りそうになった私は強く頭を振った。
いけない、いけない、やる事やらなきゃホントに死んじゃうヨ。
そして私は意を決して魔王に背を向け、洞窟の入り口向けて走り出した!
逃げる? ああ、逃げるよ、逃げますとも。逃げちゃ悪い? 魔王なんかとまともに戦えるわけないって、だって私は一介のメイドなんだもん。
真面目に呪文を詠唱している魔王さんには申し訳ないけれど、私だって命が惜しい。せっかく目を瞑って集中してくれているんだ、この隙を逃さない手はない。
「魔王さん、ごめんなさい。お先に失礼ふぎゃー」
全力疾走している私は見えない何かにぶつかって、それにしたたかに顔面を打ちつけた。痛い痛い痛い、ただでさえ低い鼻がまた一段と低くなったに違いない。もんどり返りつつ、何にぶつかったのかを確かめようと目を凝らす私に、絶望的な光景が飛び込んできた。
魔力で造られた透明な壁だ。ぱっと見は分からないけれど、よく見ると魔力が七色の光を発して壁を築いている。
なんてことだ、考えが見破られていた。
振り返って遠くの魔王を睨むと、相変わらず目を瞑って呪文を唱えつつ、ニヤニヤと嗤っているのが見える。
詠唱が始まって既に一分ほど経っていた。
「うわわわ、どうしようどうしよう、死んじゃうよぉ」
いまさらパニックになって私は周りを見渡す。
何かないか? 私が生き残る確率を、少しでも高める何かがないか?
その時、私の近くで不意に空気が小さく弾けた。何かが存在していたわけじゃない。にもかかわらず、突然、小さな爆発が起きた。
びっくりした、と驚く間もなく、洞窟のあちらこちらで同じように小さな爆発が立て続けに起き始める。バチッバチッと弾ける音がやがて幾重にも重なって、広い洞窟に反響する。さすがにそこまでくると、この怪奇現象が魔王の呪文によってもたらされているのは私にも分かった。
そして同時に魔王の究極魔法に目星がついて愕然とする。
それまで魔王が私に放った攻撃は、それぞれ形状は違ったものの、私に向かってくる様子が見て取れるものだった。だから私は避けれたのだ。
では、目に見えない、発動と同時に攻撃が成り立つ「爆発魔法」だったら、どうだろう?
答えは言うまでもない。魔法が影響しないエリアに退避する以外、避ける事は不可能だ。しかし、それは魔力の壁の存在から分かるように、すでに魔王は私を攻撃範囲に閉じ込めたと考えるべきなんだろう。
きっと魔王が呪文を唱え終えた時には、空間そのものが爆ぜるに違いない。そのような中で私が生き残っている可能性は……あるわけなかった。
「うわん、もうやぶれかぶれだ、コンチクショー」
私はほんの数分前とは逆方向に向かって走り出した。目指すは魔王、ただ一人。目的はその魔法の詠唱を中断させる事。思えば詠唱に入る前に魔王がご丁寧にも忠告してくれていたのだけれど、あの時は逃げることで頭がいっぱいで、魔王をなんとかしようなんて考えもしなかった。出来ることなら、あの時の自分に「人の忠告はちゃんと聞きなよ」と言ってあげたい。
いや、それよりもさらに時間を遡って「調子に乗って魔王を挑発するなよぉ、私のアホ」と言ってあげるべきか。
そんなことを考えているうちに魔王との距離はもう目と鼻の先だ。
私は走りながら後ろ手に、腰に差した得物を抜き取る。そして詠唱に集中している魔王に向かって、私は目にも留まらぬ連続攻撃を繰り出した。
パタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタ…………
うん、私の『はたき』のおかげで、魔王様の衣装についた塵芥が奇麗さっぱり取り除かれたヨ。
って、お掃除してどうするよ、私ィ!?
レベル30になっても未だにSTRが3のままで、装備できる武器が初期装備の『はたき』だけという、ご主人様の面白半分な育成プランが今、見事なまでに私を窮地へと追い込んでいた。
あのクソ野朗、地獄で会ったら絶対殺しちゃる!
「ああ、もう、こうなったらアレしかないっ!」
最終手段・股間蹴り。私は魔王の股間に向けて大きく右足を振りかぶる。
それはさりげなく私に伸ばされた魔王の左手が、私を捕まえる直前の事だった。
野猿ばりの動きを誇る今の私なら、魔王の左手が自分を捕らえるよりも早く、ヤツの股間を蹴り上げる自信がある。でも、何故か体が動かなかった。どういうわけか私の本能が、股間を蹴り上げてもここで左手に捕まったら、本当に全てが終わってしまうと警鐘を打ち鳴らしていたのだ。
何故? ここで捕まらなくても、呪文の詠唱が完了したら私は間違いなく殺される。爆発魔法によって、避けることも出来ないまま爆死させられるのだ。
……いや、待て、本当に魔王は私を爆死させるつもりなのか?
ふと、私の脳裏に閃きが走る。
確かに空気があちこちで爆ぜる状況は、魔王による爆発魔法の詠唱を示している。逃げられないために魔法の壁まで造っている。
だけど、いくら炎の攻撃が悉く避けられたからって、ならば広範囲攻撃の爆発魔法で仕留めようなんて、魔王ともある存在がそんなみみっちいことを考えるだろうか?
避けられれば避けられるほど、その攻撃で仕留めないとプライドが許さないのではないだろうか?
そう考えると、詠唱に入る前のあの言葉も納得がいく。
攻撃してみせろとは、つまり近付いて来いということ。
そして近付いてきた私に伸ばされた左手の意図は、分かりきっている!
私を捕まえ、避けられない状態で得意の炎魔法を私に食らわせるためだ!!
「うわわわ、こんなところで死んでたまるかぁ!」
私は右足を強制キャンセルし、思いっきり後ろにジャンプした。
私を捕まえようとした魔王の左手が、あともう少しと言うところで空しく宙を舞う。
瞑っていた目を見開いた魔王と目が合った。距離を取ろうとする私に一瞬驚いたようだったけれど、
「見事! よくぞ余のフェイクを見破った!」
次の瞬間には呪文の詠唱を中断して、腰に手をあてて大笑いした。
どうやら私は助かったらしい。ほっとしたら力が抜け、そして
「うわん」
着地した足元がつるりと滑って、私はバランスを失って後ろ向きに万歳をする格好で空中を舞った。
あ、ヤバイ。この姿勢だと魔王に大事なところ見られちゃう!
慌ててスカートを押さえようとしたところで、後頭部に強烈な衝撃が走り、私は「きゅう~」なんてヘンテコな声をあげて、意識をあっさり手放した。
滅入るほどに頭がずきずきと痛んだ。まるで火酒を無理矢理飲まされた翌朝のようだった。
おまけに頬にも時折鋭い痛みが走った。こちらは鞭で打たれるような、鋭い痛みだった。
一体、何だと言うのだろう? またご主人様に難癖つけられて、お仕置きされているのか?
頭の痛さに耐えながら目を瞑り、必死に今の自分の状況を思い出してみる。
旅の途中でふらりと立ち寄った田舎町。古の支配者が眠るという噂に面白がってダンジョンにやってきたら、いきなりボスらしき魔物と遭遇。あっという間に傭兵ふたりがやられて、ご主人様まで殺されてしまった。私は命からがら逃げまくっていたんだけど……
あれ、そう言えば最後はどうなったんだっけ?
頭を捻るけど、思い出せなかった。
まぁ、でも、夢なんて所詮そんなものだ。
ご主人様の頭が吹っ飛ばされるシーンなんて実に胸がすっとしたなぁなんて思いながら、私はもう一度寝ようとして
「痛っ!」
頬に走る痛みに思わず目を開けた。
「ようやく目覚めたか」
そこには片足を跪いた魔王が平手打ちのポーズをとって、私を覗き込んでいた。
「うわわわわ、なんで? なんで、魔王『様』が? あれは夢じゃなかったの?」
私はすかさず起き上がると、ずざざざっと後ずさる。と、壁に思ったよりも近かったらしく、後頭部を岩壁にしこたまぶつけてしまって、頭上に星がひとつふたつくるくる回った。
「キィよ、お前はもう少し落ち着きを持った方がよい。その調子ではこれからが思いやられるな」
そんな私のパニックぶりを見て、魔王『様』はひとつ溜息をつくものの、その瞳は何故かとても優しく感じられた。私はなんだか拍子抜けして「はぁ」と馬鹿みたいな返事をする。
って、ちょっと待て。
これから? これからって何だ?
いや、それよりも何で私の名前を知ってるの?
それにちょっと自分でも気になってたんだけど、私、さっきから魔王のことをなんで「魔王様」って呼んでいるんだ?
ご主人様の時と同じ、嫌な予感がした。
私はすかさずエプロンのポケットに入れておいたはずのアレを手探りした。
薄っぺらいお財布とか、集めると不思議なアイテムと交換してくれるらしい小さなメダルとか、小瓶に入ったエリクサーという名の清涼飲料水とか。我ながら呆れるほど雑多な物で溢れるポケットの中に、ひんやり冷たいお目当ての物を探りあてて、私はホッと胸を撫で下ろしつつ取り出す。
そこには二枚目気取りのご主人様の顔が浮かび上がっていた。
これじゃない!
私は思わずそれを地面に力いっぱい叩きつけた。
「お前のならばここにあるぞ」
「ああっ、私のステイタスカード!?」
あああ、心配事が見事に的中。カードを指先でくるくる回して得意顔の魔王様を見て、私はがっくりと肩を落とした。
「喜ぶがよい。あれほどの攻撃をかわしたお前に、これから余の奴隷として傅く名誉を与えよう。早速、余の事は『魔王様』と親しみを込めて呼ぶように設定しておいてやったわ」
カードに映し出される私がバカみたいに笑っている。その下、本来ならば健康状態を表示する部分に「SLAVE(奴隷)」の文字が光っていた。
「では、早速仕事がある。ついてまいれ」
魔王様はマントを翻す。それを合図に私は無意識に立ち上がっていた。うあん、これもカードの強制力かぁ。私はまだズキズキ痛い頭を抱えながら、魔王様の後ろを追いかけるのだった。
「いらぬお世話かもしれぬが、お前は一体どんな育てられ方をしたんだ?」
魔王様は仄暗いダンジョンをずんずん歩きながら、私の方を振り向きもせず話しかけた。
やたらと足が速い。私はなんとか付いていくのに必死だ。
「お前のカードを見たが、能力値のバランスが異常だ」
ううう、だってご主人様が面白半分に成長ポイントを振り分けたんだもん。私のせいじゃないよーと心の中で抗議の声をあげた。
「おまけにスキルもパーティスキルのみで、戦闘に使えるスキルがほとんどない」
だーかーらー、それもご主人様のせいなんだってばーと目で訴える私。
「まったく、人間の考えは余には想像もつかんな」
相変わらず私のほうを見ないで、一人溜息をつく魔王様。
いやいやいや、むしろ溜息つきたいのは私だしと、今度は鼻息でアピールする。
「そのあたりを余にも分かるように説明を……おい、キィ、何故先ほどから何も言わぬ?」
「ふげをふけてふからふぁぁぁぁ!」
やっと私の方を振り返る魔王様に、私はふがふがと必死になって抗議の声をあげる。
魔王様は立ち止まり、不思議そうな顔をして私を見下ろすと、これまた理解できないという表情でなにやら呪文を唱えた。
口に咥えさせられていたボールギャグがたちどころに消え去った。
「あんなの付けられて話せるわけないでしょー!」
「なんだと? しかし、人間は奴隷にあのようなものを咥えさせるのであろう?」
「あんた、一体どんなエロスな奴隷を想像してるんだー!?」
怒りながら私もつい想像してしまった。実におぞましい。これだから男は。まったくもって男は。
「ふむ、キィが何に怒っているのか理解出来ぬが、余の知識に誤りがあったようだ。非礼を詫びよう。許すが良い」
許すが良いと言っておきながら、まったく悪びれた様子がないのが実に魔王らしい。私はこれからこんな人に仕えなくてはいけないのかと思うと、我が身の不幸を嘆かずにはいられなかった。
「では、改めて命じよう。キィ、お前の能力値の異常性から『わたし、あんなところにホクロがあるんです』的な他人には絶対知られたくない恥かしい秘密まで、全てを余にさらけ出すがよい」
「わざとか! 知っててわざとやってるでしょ、あんたー!?」
エロバカご主人様の束縛から逃れられたと思ったら、今度はエロ魔王の奴隷とは。
とほほ。私、LUKは高いはずなんだけど、絶対ツいてない。
そんな事を考えながら、私は少しずつ身の上話を始めたのだった。
例えば、冒険を始めた当初の頃。何故か私のほうがご主人様よりも先にレベルアップしてしまい、それに臍を曲げたご主人様が私の能力値を面白半分に設定し始めてしまった。
「やはりキャラ育成というのは、一点豪華主義で行くべきだな。よし、キィはひたすらLUK(幸運)を高めてやるぞ」
「うわわわ、それ、一番あやふやな能力じゃないですか? やめてくださいよー。せめてSTR(腕力)を2つ上げて、メイド武器『竹箒』を装備させてください」
「うるさい、黙れ。お前が竹箒なぞ百年早いわ」
かくして私のSTRはいまだ3のまま。
おかげで戦闘では全く使えず、ひたすら見ているだけのお荷物になってしまった。
「ですが、ご主人様? 私、お供する必要ありますかね? 不必要でしたら、お屋敷に戻って、また屋敷付きメイドとして働きたいんですけど」
ご主人様のレベルが40を超えたあたりだっただろうか、私はそんな提案をしてみた。
「何を言う。お前は立派に役に立っているぞ」
珍しくご主人様が似合わない優しい言葉をかけてくれる。
なんだろう、普段が鬼畜なだけに、こんな言葉でも妙にジーンときた。
「お前のスキル、『パーティの獲得経験値上昇』と『獲得金額上昇』は、誰かが持っていないといけない必須モノだからな。あと『記憶術』のおかげで、マッピングとかヒントをいちいちメモに写し取る事もしなくていいし、便利なんだよ」
……便利とか言っちゃったよ、この人?
「それにお前がいなかったら、誰が危険な宝箱を開けたり、陰湿なトラップを除去するんだ? これこそLUKをとことん極めたお前の仕事だろ?」
「えー、それだったらDEX(器用さ)を上げてくださいよぉ」
「DEXぅ?」
さも馬鹿にしたようにご主人様が鼻で笑った。
「あんなの、罠解除以外では何の役にも立たん。それよりも経験値やお金が多く手に入るかもしれないLUKの方が大切だろ? LUKが高ければ罠が発動しても、被害は最小に抑えることが出来るしな」
……うん、わかった。この人、ヤ○ ザだ。きっとそうだ、間違いない。さっきの時折見せる優しい態度だって、それってヤ○ ザが囲っている愛人への常套手段だもん。
「それに最近では回避も出来るように、AGI(素早さ)も上げてやってるんだぞ。うむ、これからもバンバン罠を発動させて、必死に避けたり、死なない程度に苦しんでいる姿を見せて、戦闘で疲れている俺達を和ませてくれよ、キィ」
……お願いします、神様。一日も早くコイツをぶっ殺してください。
入りたかった。戦闘の場に――
戦闘の矢面に立たなくても、同じパーティという事で私にもわずかながらの経験値が入ってきていた。でも、いくら私が経験値や金額の上昇スキルを持っていたり、罠解除(?)が仕事であったとしても、やっぱり冒険のメインである戦闘で一人ぼーと突っ立っているというのは、なんとも申し訳ない気持ちになるのだった。
だから、ちょっとでもいい、私も戦闘で何かの役に立ちたい。
そんないたいけな気持ちが私のわずかな自尊心を打ち破り、あるレベルアップの時、私はご主人様に土下座までして、何か私にも戦闘で役立つようなスキルを付けてくれるように頼み込んだ。
「うーん、ぶっちゃけ何にもないぞ? 取得するにはある一定の能力値が必要だし、かと言って俺はお前のLUKとAGIしか上げるつもりないしな」
さりげなく酷い事を言う。私はいつものように怒りたくなるのを我慢して、さらに深く土下座して「そこをなんとか」と懇願した。
「そうだなぁ、それじゃあ、この『応急処置』あたりでも取得しとくか?」
「ホントですか? やったー」
私は土下座体制から素早く立ち上がって、ご主人様の持っているカードを覗き見る。そこには『応急処置』スキルの、簡単な説明が表示されていた。その内容は微妙だけど、一応回復スキルだ。
ああ、これでちょっとは戦闘で役立つ事が出来る。
私は有頂天で、思わずその場で舞い踊った。
「あ、間違えた」
……なんですと?
私は歓喜の舞を強制終了して、慌ててカードを覗き込む。
「いや、すまんすまん。思わず隣の『二刀流』を選択しちまったわ」
ご主人様の言うように、カードには『二刀流』のスキルが映し出されていた。『二刀流』、それはつまり両手に武器を持つことが出来る、攻撃重視の戦闘スタイルスキル。戦闘マニアなら押さえておきたいスキルの一つ、なんだけど……
「『はたき』の二刀流で、アークデーモンに勝てるかーっ! ご主人様のおバカー!!」
かくして私にまたひとつ何の役にも立たないスキルが追加されたのだった。
「てんでしょーもないご主人だったのだな」
「そーなんです、ホントにしょーもないご主人様でした」
魔王様の言葉に、私は深々と頷いた。
驚いた事に魔王様は私の話を親身になって聞いてくれた。絶妙なタイミングで相槌を入れてくれるなど、とても聞き上手だった。おまけに非道なご主人様の行いに対して「殺して正解だったな」と怒りを込めておっしゃってくれた。
そんな魔王様の反応が嬉しくて、私は相手が魔王だと言うことも忘れて、ひたすら話しまくった。もしここが酒場だったら、きっと今宵のお勘定は私が全て払わせてもらっていたに違いない。
それぐらい気持ち良く話を聞いてもらったのだった。
「うむ、よくぞ話してくれた。キィの歪な能力の所以が理解できたぞ。礼を言う」
「いえいえ、こちらこそー。魔王様がこんなに親身になって聞いてくれるとは思ってもいませんでした。いい人ですねー、見直しましたよん」
そんな私の言葉に魔王様はきょとんとされた。
「そうか、余がいい人か。ふむ、決してそんな事はないと思うのだが……」
思案に暮れる魔王様。
あ、そうか、魔王なんだから「いい人」ってのは私たちと違って褒め言葉なんかじゃないのかもしれない。むしろ、悪口の類なのかも。
私はちょっと焦った。
でも、魔王様には悪いけれど、本当にいい人だと思うんだ。
「まぁ、よい。そんな話をしているうちに目的地に着いたようだ」
魔王様が思案を断ち切るように、一つの部屋の前で立ち止まった。
私たちは話をしながら、ダンジョンの地下深くへと降りていた。道中三つの昇降機を使い、そのうちの一つは六階層ほどすっ飛ばして私たちを運んだから、おそらくここは地下十階ぐらいだろう。
魔王様が目的地と言われた部屋には「ダンジョン開発本部」と書かれた張り紙が扉に張られてあり、魔王様はそれを軽く押し開けた。
「おおっ、魔王様!」
魔王様の登場に、部屋の中から歓喜の声が沸く。
私はそーと後ろから部屋の中を覗きこんだ。
そこは小さな街の酒場ぐらいの部屋だった。中心に大きな机があり、大勢の魔物がそれを囲んでいる。豚面で全身汗まみれのオーク。筋肉隆々でヘルメットをかぶったホブゴブリン。ガーゴイルは身に付けた作業用パンツにトンカチやレンチをぶら下げ、スケルトンは工事用シャベルにもたれていて、その他にも多種多様な魔物が揃っていた。冒険者なら、この扉を開けた途端に一目散で逃げ出したくなる数だった。
それら様々な魔物が一同に魔王の名を呼ぶと、次々と床に片足をつけて深々と頭を垂れていく。
全ての魔物が平伏し、物音一つ起こす事さえ躊躇うような静けさに部屋が満たされると、魔王様は毅然とした態度で言い放たれた。
「皆ご苦労である。報告はすでに受け取った。ここからは余に任せるが良い」
ははーという声と同時に、先ほどの魔王様登場以上の歓声が部屋を満たした。
魔王様が出張ってくれた以上、もう大丈夫だ!
魔王様、久しぶりにやっちゃってください!
そんな魔物のはしゃぐ様を、魔王様はなんとも嬉しそうに目を細めて眺める。
やっぱりこの人は優しい人だと改めて思った。
「時に魔王様、その人間の娘っ子は一体なんですかい?」
不意に私と目が合ったワーウルフの質問に、沸きあがった歓声が一気に沈静化し、部屋にいる全ての魔物が私を睨みつける。
「うむ、なかなか面白い能力の持ち主でな。余の奴隷として傍に置く事にした」
魔王様の言葉に、おおーっと魔物たちから驚きの声があがる。
「しかし、魔王様。大丈夫ですかい、人間なんぞを傍に置くなんて? いつ寝首を刈られるか分かったもんじゃないですか?」
「うむ、それはもっともだ。しかし、こやつに関してはその心配もない」
魔王様は懐から私のステイタスカードを取り出すと、皆に見えるよう掲げる。
「久しぶりに人間界に来てみれば、人間め、面白いものを天界から持ち込んだものよ。これはな、もともとは天界の神々が人間を隷属する為に造ったものだ」
ほおーっと感心する魔物たちの声を「えええっー!?」と、私の驚愕の叫びがかき消した。
「ちょ、ちょっと、何ですか、それ? 神様が人間を隷属させるためって? 私、そんなの聞いた事ないですよぅ?」
「それはそうだろう。相手にそうとは悟られずに支配するというのは、神の十八番だからな」
さも当たり前かのように話す魔王様に、魔物たちも皆そろってうんうんと頷く。
「そもそも考えてもみるがよい。カードに自分の能力が数値化され、さらには成長ポイントなる数値を入力すれば、それが身体に影響を及ぼすなんて技術、人間なんぞに作り出せるわけがなかろう? こんなものが作れるのは、お前達人間をモルモットとしか見ておらぬ神以外おらんよ」
私の頭の中で既存概念が、魔王様がおっしゃられるところの真実と掴み合いのバトルを始める。
魔王様の言葉には納得させるだけのものがあった。でも、物心ついてからずっと疑いさえ持たなかった常識を根本から否定するのはさすがに躊躇われた。
「まぁ、信じる信じないはキィ自身に任せるとしよう」
そこで魔王様は目線を私から再び仲間の魔族達に移した。
「しかし、事実としてこのカードには人間を拘束する強力な力が備え付けられておる。これがある以上、こやつが余を裏切り、ましてや寝首を刈るなどという反逆は絶対行えぬから皆安心するがよい」
そして魔王様はマントを高々と翻す。
「それではこれより余とキィはダンジョンの主であるドラゴンとの戦闘に赴く。汝らは余の勝利を信じ、このダンジョンを我ら魔族が快適に住めるようリフォーム作業に専念するように!」
魔物たちのオウという返事が部屋に鳴り響いた。
内に入ってわかったのだけれど、魔物というのは、あれで存外に働き者揃いらしい。
魔王様の掛け声からものの数分も経たぬ間に、あれだけ居た魔物たちがすっかり出払って、部屋には私と魔王様だけが残された。
「さて、余たちもそろそろ行かねばなるまいのだが……」
魔王様は困ったように私を見つめる。
「キィよ、いい加減震えて抱きつくのをやめてくれないだろうか?」
私は魔王様を見上げながらぷるぷると顔を横に振った。
だって、ドラゴンだよ、ドラゴン。
ドラゴン、それはこれまた魔王と同じレベルの神話上の生き物。その翼を羽ばたかせるだけで人は軽く吹き飛び、口から火を放てばあたり一面火の海と化すとまで言われている。
はっきり言って、そんなのと戦うなんて自殺行為以外の何物でもなかった。
すっかり怯える私に、魔王様は軽く溜息をつく。
「分からんな。先ほど余と戦った時はあれほど堂々としておったのに。どうして相手がドラゴンだとこうも震えるのだ?」
「だって、魔王様と戦った時は、途中まで相手が魔王だなんて思ってもいなかったんだもん」
いきなり魔王と相対するなんて知っていたら、いくら私たちでもこのダンジョンには近付かなかっただろう。あのバカご主人様でも、それぐらいの分別は出来るはずだ。
「そもそもどうして魔王様ともあろう方がダンジョン入ってすぐの大広間にいたりしたんですか? 普通、ボスはダンジョンの最奥にいるものでしょう?」
「仕方なかろう。このダンジョンはまだ余のものではない。ちょうど良い感じの洞窟を見かけたから、調査をしつつ魔族に住みやすい環境にするよう部下に命令を下したのだ。すると存外に大きな洞窟であったのでな、気がつけば全員そちらにかかりっきりで、ならばと余が入り口の門番を買ってでたわけだ」
なるほど。ずっと疑問だったけれど、いざ聞いてみれば馬鹿らしいほど単純な理由だった。
「それに余が入り口に張り付いている限り、人間どもは中に入れぬであろう? お前達は仲間を無闇に殺しまくるからな。案外余が門番をするというのは、適材適所ではなかろうかと思っていたところだ」
そして優しく私を見つめて微笑む。
「キィ、我が魔族はなんとしてでもこのダンジョンに居を構えるため、主であるドラゴンを倒さねばならん。まだ会いまみれぬ相手ゆえにその力量は推し量れぬが、お前の助力なく、余の魔力だけでは圧する事叶わぬであろう。お前は余の奴隷であるが、同時に仲間でもある。ドラゴン退治は危険ではあるが、決してお前を殺させはせぬと我が名誉に賭けて誓おう。だからどうか、今一度勇気を持って、余を助けてはくれぬであろうか?」
どうか頼むと魔王様は頭を下げた。
不思議な感じだった。
今までの私は命令されてばかりだった。
あれをやれ。これをやれ。つべこべ言うな早くやれ。それが当たり前だった。
ご主人様と冒険に出た時だって、私はなんとか回避しようともっともらしい理由を並べたけれど、それを聞き入れてもらえるとはこれっぽっちも思ってもいなかった。所詮、私は命令される身分の者。いくら「それは無理です」と正論を並べたとしても、命令されたら逆らえなかった。
そして命令を下す者は、私たちがそういう人種である事を知っているのだ。どんな無理難題でも、命令に背く事はない。だから、お願いなんて受け叶えてくれるかどうか分からない事を試すよりも、命令をした方が早いのだ。
命令しかしない人間と、頭を下げてお願いする魔王。
先ほどの神様陰謀説といい、私が今まで見ていたモノは、どこかの狂った誰かが描いた歪んだ世界だったのかもしれない。
「……が、ないなぁ」
私はポツリとつぶやく。
魔王様は首をかしげて、聴き取れないとゼスチャーした。
「しょうがないなぁ。分かりましたよ、手伝いますよ。でも、本当に私、戦闘では何の役にも立たないんですからね、期待しないでくださいよ」
私は魔王様の胸に頭を押し付けた。そうすれば、震えが止まるような気がしたからだ。
魔王様はそんな私に気を配ってくれたのだろうか、私が離れるまで何もせず、ただ「そうか、礼を言う」と再び頭を下げるのだった。
「でかっ!」
ドラゴンを初めて見た私の第一声は、まさしくその大きさに圧倒されて出たものだった。
狭く、岩肌がごつごつとむき出しの通路をしばらく進むと、唐突にまばゆい光に包まれた大空洞に出た。天井は見えないぐらいに高く、広さも田舎の村そのものがすっぽり入るぐらいの大きさがある。そしてその中央、床一面に埋め尽くされた財宝の山々を守るようにして、赤い鱗も鮮やかな巨大なドラゴンが鎮座していた。
その大きさはもはや建物に近い。私は生まれ故郷にあった教会を思い出していた。
「ご機嫌麗しゅう、古の覇者よ」
すっかり萎縮する私をよそに、魔王様は普通に歩いてドラゴンに近付いていく。あんな怖そうな生き物によくもまぁ、と素直に感心した。魔王の名前はやはり伊達ではない。
私は怯えながらも、とてとてとその後を追う。
「魔界の王とは、これは珍しい。こちらの世界にお前はお呼びではないはずだが」
ぶおんとドラゴンが鼻息をたてる。その強風で魔王様のマントが激しく舞ったものの、その歩みに淀みは無い。
ちなみに私はスカートがめくりあがって、その場で立ち止まり、押さつけるのに必死だった。でも、魔王様は振り返りもせず、ドラゴンも全くの無視だった。
ちょっと悲しかった。
「よばれてないのは重々承知ではあるのだが、此度は少々事情があってな」
魔王様の濁した言葉に、ドラゴンはその牙を剥き出しにした。まるで「先を話せ」と威嚇するかのようだ。
「三度に渡る神々との戦いにより、我が魔界も崩壊寸前なのだ。今のうちに我らの次なる安息の地を探さねばならぬ」
「ほぉ? それで人間界に目を付けたか?」
ドラゴンが笑う。まったくもって可愛くなかった。
「事情は理解した。それで、この老いぼれに一体どのような用件かな?」
魔王様とドラゴンの間にちりちりとした緊迫の空気が流れる。
開戦が近い。私は魔王様の横に立ち、両手に得物を取り出した。
「二度は言わん。黙ってこのダンジョンを魔族に明け渡せ」
魔王様の降伏勧告に、ボフゥと再びドラゴンの鼻息が私たちを襲った。
私はなによりもまず左右の手にある得物が吹き飛ばないように、しっかりと握り締めた。
が、しかし。
「二、二度は言わんぞ」
何故か同じ事を二度言う魔王様。セリフの内容と相俟って、実に決まりが悪い。
いや、それ以上に一体どうしたというのだろう? ここまで計画通り順調だったのに、何かトラブルでもあったのだろうかと心配になって魔王様の様子を伺う。私を見つめるそのお顔は少し赤みかかっていた。
戸惑う私の視線を感じたみたいで、魔王様は慌てて目を逸らすと、再びドラゴンに対峙する。
「面白い話だが、もしイヤだと言ったらどうなる?」
魔王様の変調なんてお構いなしにドラゴンが先を急ぐ。
いよいよだ。
「いちいち言わなくても分かるであろう、古の覇者よ。その時は……」
「その時は?」
「「戦うのみ!!」」
私たちは同時に宣戦布告すると共に素早く行動に移した。
私は両手に得物を高々と掲げる。
魔王様はすかさず横っ飛びして、ドラゴンとの距離をあけた。
一瞬躊躇するドラゴンに、私は果敢に襲い掛かる。
「うりゃー! 必殺の『はたき二刀流』を喰らえー!」
まずは左の『はたき』を振り下ろす。
ぱたぱたぱたと『はたき』がドラゴンの腕を撫でる。言うまでもなくダメージ0。
訝しむドラゴンに、続いて右の『はたき』をお見舞いする。
「いいか、これは『ドラゴン殺しのはたき』と言う。ドラゴン以外にはまったく普通の『はたき』だが、ドラゴン相手には繊維一本一本が鋭利な刃となり、奴らの肉を切り裂く伝説の武器のひとつだ。これを使うがよい」
『はたき』を振り下ろす私の脳裏に、魔王様の言葉がリフレインした。
私に伝えられた作戦は、この『ドラゴン殺しのはたき』と普通の『はたき』を二刀流で扱い、頻繁にこれを左右入れ替えて攻撃する、というものだった。
二刀流で扱うのは、武器のスピードを二倍にするため。本来なら左右のどちらかは普通の『はたき』だから、どちらかを避けていればよいのだけれど、ドラゴン殺しの方を避けられなければ結構なダメージを食らってしまう。その恐れからやがては両方避けようとして、ドラゴンは回避運動に専念せざるをえないだろう。そこを魔王様が得意の魔法で仕留めるのだ。
言うならば私の攻撃全体がフェイク。でも、それまで戦闘を眺めるだけだった私からすれば、それだけでも十分に役立っていると実感出来るものだった。
ましてや相手は伝説の生き物・ドラゴン!
これで燃えなきゃ、冒険者失格でしょ?
「すりゃー!」
ぱたぱたぱたぱたぱたぱたぱたぱたぱたぱた……
私は『伝説のドラゴン殺しのはたき』で、ドラゴンの腕に切りつける。
ドラゴンの、己の肉を刻まれる悲鳴が洞窟に……響かなかった。
ぱたぱたぱたぱたぱたぱたぱたぱたぱたぱたぱたぱたぱた
とゆーか、まったく切れてなかった。
あれ? どーゆーこと?
「小娘、先ほどから何をしている?」
ドラゴンが哀れんだ目で私を見ていた。
「え、いや、あの、これ『ドラゴン殺しのはたき』っていう伝説の武器だって魔王様が……」
「そのような武器、聞いた事がないわ。おそらく魔王に騙されたのであろう」
騙された? うそん? だって、とても優しそうな人だったよ、魔王だけど。
……って、ああっ!! 魔王だったっけ、そう言えば。
私は素早く周囲を見渡す。私とドラゴンを結んだ線上の、ちょうどドラゴンの向こう側に魔王様はいた。ドラゴンの股越しに私と目が合うと、あろう事か、両手を合わせて申し訳なさそうに謝っていた。
魔王様のウソが見事に立証された瞬間だった。
「うわぁ、あの人、サイテーだぁ!」
思わず頭を抱えてうずくまろうとしたその時、突然稲妻のような音が遥か頭上から響き渡った。見上げるとドラゴンが苦しそうに顔を歪めている。今の位置からではドラゴンに近付きすぎて状況がよく分からないので、距離をとって確かめる事にした。
ついでに同じ距離を取るなら、すでに高みの見物と洒落込んでいる魔王様に一発お見舞いしておこうと思い、ドラゴンの傍をすり抜けて、魔王様目指して走り出した。
「さすがはキィ。見事であったぞ」
「見事、じゃなーい! この嘘つき! 『ドラゴン殺しのはたき』なんて存在しないってドラゴンが言ってたぞー!」
全力疾走で駆け寄った私に、魔王様は何のお詫びもなく平然と受け答える。ちくしょー、『はたき』投げつけたろか。
「うむ。しかし、見てみるが良い。おかげでドラゴンの翼を封じる事が出来た」
言われて振り返ると、確かにドラゴンの翼に雷のようなものが渦巻き、ドラゴンが翼を動かそうとする度に激しく爆発を起こして、その動きを封じ込めていた。
「この詠唱が完成する時間、そして完成から効果が出るまで気付かれぬよう、ドラゴンの意識を逸らす必要があったのだ。その為の今回の作戦、キィがいなければ到底成り立つものではなかった。本当に感謝する」
恭しく頭を下げる魔王様。その行為は紳士そのものなんだけど、やり方がえげつない。
「で、でも、『はたき』の件はヒドイ! 私、信じてたのに」
「『敵を欺くには、まず味方から』と申すであろう? キィが余の言ったことを本気で信じてドラゴンに立ち向かったから、ヤツもまたキィの攻撃に何かあると意識を向けたわけだ」
うー、言いたい事は分かる。分かるんだけど、なんだか釈然としなかった。
やっぱり一言お詫びぐらいあってもいいんじゃないだろうか。そう思って魔王様に言い寄ろうとすると、その姿に変化が現れていることに気付いた。
「魔王様? なんか体が透けてきていますけど?」
「うむ、翼を封じたので、次は究極魔法でヤツに印籠を叩きつける。しかし、この呪文の詠唱には四十分ほどかかるのでな。その間、余は隠れておるので、それまであやつの相手をよろしく頼む」
「相手? えっ、ちょっと待って!? 魔王様、それはあんまりすぎるーっ!」
「大丈夫だ。キィの回避能力と幸運補正ならば、万が一にも攻撃を喰らう事はあるまいよ。さすがに翼による無差別攻撃は避けるのは無理であろうが、その為にヤツの翼を封じたのだから問題はなかろう。余の時と同じように、避けて避けて避けまくればよい」
なんともお気楽な事を言いながら、どんどん姿を消していく魔王様。
「キィ、お前の最大の不幸は、主人がお前の稀有なる能力に気がつかなかったことだ。だが、余は違うぞ、お前の能力を存分に生かした戦闘をこれからも展開してやろう。くっくっく」
最後の笑いが実に邪悪だった。
魔王様の姿が完全に消え去るのとほぼ同時に、ドラゴンが恨めしそうに咆哮した。そして口から炎弾を吐き出してくる。
えー、またこのパターンかよぅ?
私はうんざりしながらも一つ気合を入れなおして、ドラゴンに向きあった。
四十分後――
魔王様の詠唱により、突如として現れた巨大な炎の隕石に押しつぶされて、ドラゴンが哀れな姿を晒していた。
かく言う私もボロ雑巾のように疲れ果てて、そのドラゴンの横にぺたんと腰を降ろしていた。
「ご苦労であった、キィ」
気が付けば後ろに涼しい顔をした魔王様が立っている。
私は立ち上がる気力も無く、ただ魔王様を見上げていた。
「ところで一つ訊きたいことがあるのだが」
魔王様が不意に口を開く。
「お前、余を『いい人』と言っていたが、今でもそう思うか?」
私はうーんと頭を捻り、一言だけ言った。
「よく分かりません」
自分でもあまりよい返事ではないなと思った。でも、本当に私には分からなかったのだ。
私の身の上話を親身になって聞いてくれたり、仲間の魔族のことを思いやったり、ここぞという時は命令ではなくて『お願い』で私の心を揺り動かしてくれたり。そんな魔王様は本当に優しくて、魔族なんだけどとても人情のある人なんだと思う。
でも、いくら作戦とはいっても酷いウソを言ったり、無慈悲に修羅場へ叩き落してくれたり。そのあたりはさすがは魔族、さすがは魔王という冷酷さだと思う。
「そうか。ならばこれから余の傍で、余の成す事、成すべき事を見ていくがよい。いつか我らも別れの時が来よう。その時にまた同じ質問をするから、それまでに答えられるようにしておけよ」
魔王様が私に手を差し出す。私はそれを受け取って、立ち上がり、それでもしばらく手は離さなかった。これからもよろしくというお互いの心が、繋がった手から相手に伝わるのを確かめるかのようだった。
「さて、行くか。仲間達が余の帰りを待っているであろう」
手を離して魔王様が歩き出す。私もその後を慌てて追った。
「あ、そう言えば」
私はふと疑問に思ったことを思い出した。
「魔王様、ドラゴンと話している時、『二』のカウントを二回やりましたよね? あれはなんで?」
そう、ドラゴンと会話をしながら、翼を呪縛する雷呪文の詠唱を密かに行っていた魔王様は、私と息を合わせるために、会話の最初にカウント数を入れていた。私はそれを慎重に聞き取りながら、『はたき二刀流』で襲い掛かるタイミングを計っていたのだ。
「ああ、あれはな……」
何故か魔王様は照れくさそうに鼻をぽりぽりとかいた。
「一回目のドラゴンの鼻息でキィの身に何が起きたのかを思い出せば、『二』のカウントで何が起こり、どうして余が集中できなかったのか分かるのではないか?」
ざっと考える事三十秒後、私は顔を真っ赤にして魔王様の立派な角が生えた頭をぽかすか叩くのだった。