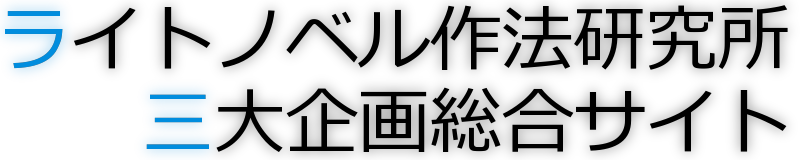2011夏祭り企画優秀作品
『背中で語るダンディズム』

【使用したお題】
「何の役にも立たないもの」→「何の役にも立たないおっさん」として使用。
「君といたあの日」→「父親といたあの日」として使用。
【一行コピー】
言葉は要りません、男は黙って背中で語りなさい。

須藤さんは、何の役にも立たないおっさんである。
これは揺るぎない事実。今決めた、私が決めた。
いやね、須藤さんのもとで働く私が言えた義理じゃないんだけどさ。
それを差し引いてもちょっと酷いんじゃないかと。もっと色々やってくれてもいいんじゃないかと。
ちょうどいいから、ここで須藤さんがどんな人か説明しておこう。
年齢は五十歳。いい年した大人が、会社にも通わないで探偵事務所なんかを経営してる。私立探偵といえば聞こえはいいけれど、早い話が何でも屋だ。いやいや、最近の仕事でいえば行列の場所取りや近所のゴミ拾いしかやってないから、半分無職と言ってもいい。生活能力もゼロに等しくて、その割には独身だから、今までどうやって生きてきたのか不思議で仕方ない。
高校卒業後から須藤さんのもとで働いてるけど、正直このままでいいのか疑問に思い始めてる。私は明日で二十歳になるから、青春まっただ中と言い張るにはそろそろ限界だ。こんなことなら、友達みたいに大学行ってキャンパスライフを謳歌してた方が良かったかもしれない。
――え? じゃあ、何で私が今も仕事続けてるかって?
そりゃあねぇ……私がダメダメなおっさん大好きだからですよ。
私こと柳瀬皐月は喘いでいた。
……こら、そこ。変な想像するんじゃない。えっちな妄想した人は後で体育館裏へ来るように。
それはさておき。事務机の上で広げた出納帳を見て、私が発狂寸前になったのは確かだった。残高欄に書き込まれた数字は、今や三桁を割ろうとしている。幸いマイナスではないけれど、金額が減る一方なのは明らか。出納帳さん、万の位以上を書き込んだ事なくてごめんなさい。あなたはもっといい会社に買って貰うべきだったんです。これも全部、須藤さんが悪いんです。
「ぅっだぁぁああああっ! 今月も無理、家賃滞納一周年ーッ!!」
私は頭を抱えて立ち上がった。その瞬間に太ももを引き出しに打ち付けて、あまりの痛さに一人で床を転げ回る。スーツのスカートからパンツが見えたとしても、今はそんな事を気にしてる場合じゃない。それよりも、私がやるべき事は他にあった。
「ちょっと須藤さん、仕事取ってきて下さいよ!」
半べそかきながら、私は部屋の主に懇願した。
部屋の主こと須藤政隆さんは、椅子に座ったまま鷹揚に頷くだけ。出会った頃から呑気な人だったけど、一年間一緒に仕事してきたおかげで、この人ののんびり具合は筋金入りだと分かった。こっちから焚き付けない限り、須藤さんはずっとああして座ってるに違いない。このまま放っておいたら、即身仏になっちゃうんじゃないかと思うぐらいだ。
「……」
返事がない。寝ているわけじゃないし、私を無視しているわけでもない。その証拠として、須藤さんは自分が着ているジャケットの裏地を私に見せてきた。
〈焦ってはいけません。英国紳士たるもの、いついかなる時もクールでいるべきです〉
内ポケットのあたりに、そう書いてあった。
……そう。須藤さんは一言も喋らず、いつもこうやって私と会話するのだ。何でも、過去のトラウマで声が出なくなったとか。こんなのんびりしたおっさんが、どんな恐怖体験したって言うんだろう。
「や・か・ま・し・いっ!」
怒り心頭の私は、須藤さんの頭に拳骨を当ててグリグリする。須藤さんはどこからともなく〈痛い痛い〉と書いたメモを取り出して、ささやかな抵抗をするのだった。
まったく、何が英国紳士なんだか。確かに見た目だけならそうなんだけど。
須藤さんは一年通してスーツを着こなしているし、ロマンスグレーの髪は今日もばっちりセットしてある。葉巻でも咥えさせたら絵になるんだろうけど、生憎そんな高価なものは事務所に置いてない。早い話、身なりと生活レベルが全然合ってないのだ。
「……もう、今は英国紳士を気取ってる場合じゃないですよ。どんな仕事でもいいですから、今すぐ取ってこないと食事もできなくなりますよ」
実際、事務所の台所にはお米が少しだけ。冷蔵庫の中に至っては、ちくわと脱臭剤しか置いてない。今日の晩ご飯はチャーハンが関の山だろう。
「大体、一日中座ってるだけで仕事が舞い込んでくるわけないじゃないですか。街の中に広告貼るとか、駅の伝言板にXYZって書き込むとか、まずは宣伝しないと!」
うちの事務所が困窮しているのは、宣伝不足が大きな要因。他の事務所は金にものを言わせて、ネット広告やら折り込みチラシやら、とにかく色々やってる。そうするとお金のあるところにはまたお金が入るし、そうでないところは言わずもがな。そんな現状でも依頼人を確保するには、限られた条件の中で宣伝活動をするしかない。
そこで秘書兼助手たる私が考えたのは、手作りチラシの配布と戸別訪問。初めの頃は恥ずかしかったけど、背に腹は変えられない。そういう訳で、今の私の主な仕事は、ほとんど宣伝活動に費やされていた。
「ほら、今日は須藤さんが行ってきて下さいよね」
どさっと、手作りチラシの束を机に置いた。いつも私一人でやってるんだから、今日こそはやって貰わないと気が済まない。
須藤さんが腕時計を見た。高級時計――に見える、露天で売ってるような安っぽい時計。質入れしたって、千円行ったらいいほうだ。須藤さんは、そんな腕時計の竜頭を引っ張って、細い紙きれを取り出した。
〈確かに貴女の言う通りですね。それではちょっと行ってきます〉
そう書いてあった。ようやく外回りしてくれる気になったらしい。
「はいはい、だったら早く行ってきて下さい。ハリー、ハリー!」
意外に均整の取れた身体をぐいぐい押してやると、須藤さんは事務所を出て行った。途中でジャケットのポケットから長いものを取り出して、それを葉巻みたいに咥える。左右を見渡した後、チャコールグレーのスーツが街並みに溶け込んでいった。
「……ったく」
一気に疲れが出た。私は須藤さんの席に腰掛けて、ぼおっと天井を眺める。
一応やる気になってくれたはいいけれど、須藤さんがお客さんを連れてこられるとは思えない。あの人のことだ、きっとぶらぶら散歩した挙げ句に手ブラで帰ってくるに違いない。ちなみに「手ブラ」と言っても、両手で胸をブラジャーみたいに隠す事じゃないのでご注意。
冗談はさておき、須藤さんが帰ってくるのは何時間後になるだろうか。あと三時間もすれば日が暮れるから、それぐらいになるだろうけど。帰ってきたら食事を用意してあげないといけない。須藤さんは一人で何もできない人なんだから。
席を立ち、台所へ。食材をチェックするまでもないけど、賞味期限切れが怖い。食あたりでも出したら、診療代やら薬代やらであっという間に貯金が底を突いてしまう。
「ふんふんふ~ん♪」
鼻歌混じりに冷蔵庫を開ける。料理が絡むと、何故かいつも上機嫌になるのが私。以前、須藤さんに料理の腕を褒められたのが理由だ。なんだかんだ言って、あのおっさんもいいところはあったりする。普段はなかなか見せてくれないけど。
と。
「――!?」
冷蔵庫の中を見て絶句した。脱臭剤しかない。昼に見た時はちくわが一本入ってたはずなのに、いつの間にか忽然と姿を消していた。ううむ、きっとこれは消失トリックを使ったからに違いない。諸君、名探偵の出番だよ!
とか思ってるうちに、速攻で心当たりに行き着いた。犯人は、葉巻に見立ててちくわを持ち出した。そう、滅多に腰を上げない彼が外出したのは、ちくわを持ち出す為だったのだ!
「……って、須藤さん! ちくわ返しなさいよっ!!」
唯一のおかずを求めて、私は事務所を飛び出した。
……あのオヤジ、どこ行った。
街の中を探し回ったところで見付けられるはずがない。ついでに言えば、須藤さんが携帯電話なんぞという贅沢品を持っているはずがなかった。そうして二時間探し回った末に私が得たものは、疲労と須藤さんに対する怒りだけだった。
「あら、皐月ちゃん」
色っぽい声で話し掛けられた。私は悔しさのあまり壁を殴り続けてたのを止めて、声の主に向き直る。
話し掛けてきたのは、胸が大きく開いたスーツ姿の美人さんだった。タイトスカートのスリットが結構きわどいところまで切れ上がってて、そこから覗く太ももだけでもご飯三杯は行けそうだ。こんなナイスバディの知り合いを、私は一人しか知らない。
「美琴さんじゃないですか」
こう見えて美琴さんは刑事だったりする。今まで何度か事務所に仕事を持ってきてくれたし、機嫌がいい時はご飯を奢ってくれたりもする。年齢の事を言ったら怒るけど、普段はとっても優しい人だ。
「また痩せたんじゃない?」
……それ、明らかに栄養が足りてないからです。昨日だってお粥しか食べてないですもん。
食べ物の事を思い出した途端、おなかがきゅうっと鳴った。
「あらあら。どう、寄ってく?」
美琴さんは苦笑を浮かべて、近くのファミレスを指した。
「はいっ、是非!」
そう返事した私が、よだれを垂らしてたのは言うまでもない。
「あなたも大変よね」
「ふぁいっ!」
「……ちゃんと飲み込んでからにしてね」
えっちくない意味でゴックンした後、私はもう一度返事した。
「そうなんですよ。聞いてくれます? 須藤さんったら――」
もう出るわ出るわ、須藤さんに対する不平不満の数々。これで美琴さんも、私が毎日どんな苦労をしてるか分かってくれたと思う。
「それにしてもおかしいわねぇ……。須藤さん、以前はあんな風じゃなかったんだけど」
その話は、前にも聞いた事があった。
何でも、須藤さんはその昔バリバリの刑事さんだったらしい。現場第一主義で、とにかく頑固。当時の部下はみんな口を揃えて「鬼のような人だった」と言ってるらしい。そんな刑事時代の武勇伝を挙げればキリがなくて、やれヤクザの組長と殴り合いの勝負をしただの、やれ逃走する犯人の車にしがみついて百キロ先で捕まえただの……あとは射撃の名手ってのもあったっけか。昔の須藤さんを知る人を訪ねると、毎度のようにそんな話を聞かされる。今の須藤さんしか知らない私にしてみれば、とても信じられないお伽噺だった。
「どうして須藤さんはあんな風になっちゃったんですか?」
「さぁねぇ……。仕事が原因で奥さんを亡くしたからってのは聞いたけど……」
「まさか、恨みを持った犯人に奥さんを?」
だとしたら、須藤さんに同情してしまう。私の想像通りだったら、今後はもうちょっと優しくしてあげたいと思った。
「やぁねぇ。サスペンス劇場の見過ぎよぉ」
美琴さんが手をひらひらと振る。その仕草が微妙におばさんっぽかったけど、口には出さないほうが賢明だ。まだお代払って貰ってないし。
「正直言うと、私もよく分からないの。それより、私が気になるのは」
美琴さんの目付きが変わった。まるで犯人の取り調べをする刑事の目……ってのは言い過ぎか。私から何かを聞き出そうとしているのは当たりなんだろうけど。
「どうして皐月ちゃんが、あの人と一緒に仕事してるのかってこと」
『あの人』のニュアンスに、どこかしら艶めかしいものを感じた。あ、あの美琴さん? 目がやけに怖いんですけど。
「もしかして皐月ちゃん、あの人が好きなのかしら?」
はい来たー! そしてビンゴー!!
みるみる顔を赤らめる私に、美琴さんの更なる追及が来た。
「どうして?」
「……いや、その……」
実は、私にもよく分からない。強いて挙げれば、私が幼い頃にお父さんを亡くしたことぐらいか。
ここで私の身の上話をちょっとだけ。
私は九歳の頃にお父さんを亡くしてる。お母さんの話では、事故で亡くなったんだとか。 お父さんはとっても優しくて家族想いだった。私がせがむと肩車をしてくれて、哀しい時には笑顔で慰めてくれた。中でも私は、お父さんの広い背中が大好きだった。あの背中におんぶされると、いつも安心感で満たされていたから。
お父さんがいなくなった後に思春期を迎えた私は、自分よりも年上の人ばかりを好きになっていた。多分、私は相手の男性に『父親であること』を望んでるんだと思う。私が年を重ねるにつれ、好みの男性のタイプは段々年齢高めに設定されていった。
だから結局、私は須藤さんに自分の父親を重ね合わせているだけなんだと思う。そもそも、私が須藤さんのもとで働き出したのは、須藤さんがお父さんに似た雰囲気を持っているのが理由なわけで。
「なるほど……つまりあなたはファザコンってことね」
「……はい、恥ずかしながら」
こくりと頷く。否定したって、刑事さんから逃げられるわけないんだから。
「そう、安心したわ。これからも仲良くしましょ」
ぱあっと、花の咲くような笑顔を浮かべる美琴さん。ショートカットの黒髪を揺らして少女みたいに微笑む顔は中々に魅力的だ。
――ん? ていうか何で安心するんだろ。ひょっとして美琴さんも……。
「仲良しついでに、仕事あげる。今ちょうど、やりかけの事案があってね。どう?」
私が質問する暇も与えず、美琴さんは話題を切り替えた。仕事をくれるなんて言われたら、聞かずにはいられない。
「心配しないで、危ない仕事じゃないから。ちょっとした小遣い稼ぎだと思って」
そう前置きして、美琴さんは話を始めた。
その夜。私が事務所に帰ると、須藤さんはソファで眠っていた。ご丁寧に、〈おやすみなさい〉と書いたタオルケットをお腹に被せて。
「この人が『鬼刑事』ね……」
安心しきった顔の須藤さんを見ていると、全然信じられない。人違いなんじゃないかとさえ思ってしまう。
気を取り直して、私は事務机に座る。なんだかんだで須藤さんが手作りチラシを全部配りきってくれたので、新しい分を作らないといけなかった。
スタンドの明かりを付けて、残り僅かになったコピー用紙を半分に切る。サインペンで〈気軽にご相談下さい 須藤探偵事務所〉と書いた後、可愛らしいイラストを描き加えておいた。このチラシを見て、一人でも多くのお客さんが来てくれたらいいんだけど。
その時、ふぁさっと音がした。須藤さんが寝返りを打ったせいでタオルケットが落ちたらしい。
……何やってんだか。
私は近づいて、そっとタオルケットを拾い上げる。須藤さんのお腹に掛けてあげようとしたら、思わず笑ってしまった。
〈いつもすみません〉
お腹のところに、そう書いてあった。自分がタオルケットを落とした時の事を見越して、予め書いておいたんだろうか。それとも、普段のお礼?
「……んなわけないか」
勝手な想像でほっこりしながら、タオルケットを掛けてあげる。相変わらず須藤さんは熟睡していた。
この人、五十にもなって子供っぽいところあるんだから。私がしっかりしないと、この事務所はいつか潰れてしまう。そうなったら、もう須藤さんと一緒に居られる理由が無くなるわけで。
そうなったら嫌だなーと呟いて、私は事務机に座り直した。そして今度は、美琴さんから受けた依頼の事を思い返す。
――心配しないで、危ない仕事じゃないから――
美琴さんはそう言ってたから、多分私一人で大丈夫だろう。一人で仕事をこなせば、須藤さんが見直してくれるかもしれないっていう計算もある。だってこの人、私の事を娘扱いするんだから。少しは違った見方をしてくれたっていいのに。
「よし、頑張ろっ」
須藤さんの寝息を聞きながら、一人気合いを入れる私なのだった。
ファッション雑誌の編集者と会う事。それが美琴さんから任された仕事だった。
須藤さんに何も言わず事務所を出るのは抵抗があったけど、当の本人は早朝から外出したらしいので丁度よかった。
美琴さんから借りた服を着て、指定されたカフェで待つこと十数分。からんからんとベルを鳴らして、一人の男性が店内に入ってきた。上等なスーツを着て、手首に数百万はしそうな腕時計を嵌めている。立派な口ひげを蓄えた、そりゃあもう素敵なナイスミドルだった。
優雅な佇まいに私がうっとりしていると、向こうがこっちの存在に気付いた。美琴さんから借りた黄色のスカーフが目に入ったんだろう。
「失礼、貴女ですかな?」
「……はい……」
バリトンの声で話し掛けられて、私は夢見心地で返事する。目の前のオジサマは、須藤さんとはまた違った魅力があった。
「はじめまして。それでは早速、本題に入りましょうか」
と言って、オジサマは名刺を出してきた。〈ニャンニャン編集部 編集長 浦賀雄一〉と書いてある。微妙におっさんのエロ用語っぽい雑誌名だけど、似たような名前の雑誌があるから姉妹誌なのかもしれない。
「まず、御名前をお聞かせ願えますか」
「柳本サチ子と言います」
自分の本名を少しだけ改変して答える。あらかじめ美琴さんから、本当の名前を名乗らないように指示されていたからだった。
「ほぉ、それはまた古風な。古きよき日本女性のようですな」
「はい……私も古きよき日本男性は大好きですの……」
「……何か?」
相手が眉をひそめたのを見て、私は我に返った。いかんいかん、つい本音が出ちゃったよ、てへ。とりあえず「何でもありません」と言って誤魔化しておいた。
「ところで柳本さん、ファッションモデルに興味をお持ちだとか」
「ええ、そうなんです。小さい頃からの夢でして」
「なるほど、それはいい」
浦賀さんが目を細めた。
「私どもは一般の方からモデルを選出することで、読者の方々に身近なお洒落を提供しようと考えていましてね。その点、柳本さんのような方に来ていただけたら、私どもも心強いです」
「それはどういう意味ですか?」
理由を相手に言わせたくて、わざと訊いてみる。
「勿論、貴女がお美しいからですよ。艶やかな髪、神秘的な目、そしてモルディブの砂浜にも負けないほどの白い肌。貴女のような方が一般から応募してきたとは、とても考えられません」
やーん、もーう! それが聞きたかったんですよぅ!!
「……そっ、そんな……」
頬っぺに両手を当てて照れるフリ。心の中ではガッツポーズしまくりだ。だって、これだけ褒められたら悪い気しないじゃない。
「もし宜しければ、ご同行願えますか。今すぐにでもこちらで用意した服に着替えて頂きたい。出来映え次第では、そのまま採用という事も」
「はいっ、是非宜しくお願いしまっす!」
すっかり上機嫌の私は、二つ返事で答えたのだった。
美琴さんが危ない仕事じゃないって言ってたから大丈夫…………んなわけあるかぁぁぁぁぁぁあああああッ!
私が連れてこられたのは、廃ビルの一室だった。この辺りは都市計画破綻の煽りをモロに喰らった地域で、周りを見ても無人のビルばかりが建っている。外壁がボロボロだったり鉄骨が剥き出しだったりと危険な場所なので、普通の人は立ち入りを禁止されてたはずだ。
じゃあ、この場にいる『普通じゃない』人達は何者なんだろうと考えてみたら、そら恐ろしいものがある。親分っぽい人が着てるスーツには某暴力団の金バッジが光ってたから、多分みんな『その道の人々』なんだろう。
「……まあ、これでいいだろ」
私の事を妥協ラインすれすれみたいに言って、脂ぎったおっさんが葉巻を咥えた。ガマガエルみたいな顔をして、無駄な肉がたっぷり付いた身体を紫色のスーツで包んでいる。いまどき吉本新喜劇でも見ないぐらい、わかりやすい親分だった。
「はっ、離しなさいよっ!」
私は威勢よく言った。
……でも、縄でぐるぐる巻きにされた姿じゃ全然格好が付かない。今や私は、悪の巣窟に囚われた簀巻(すま)き姫だった。
「そうも行かねぇんだよなぁ」
黄色い歯を見せてガマガエルが笑う。しゃがんで私に顔を近づけてきた時、凄まじい加齢臭が匂ってきた。息も臭いし、鼻毛出てるし、服の趣味は最悪だし。おっさん大好きな私だけど、この人だけは除外しといてもいいだろう。
「これからお前さんは売られちまうのさ。ドナドナドーナ、ド~ナ~ってなもんだ」
仔牛を乗せてどうするつもり! ……じゃなくて。
「私を売ってどうするつもり!?」
「さぁ、どうなるんだろうなぁ? 娼婦にされちまうか、それとも変態プレイの相手をさせられるか……買った奴に聞いてみな」
変態プレイですって! そ、そんなまさか――
「あんたたち、私の●●●に●●●突っ込んで、●●●●●●する気なんでしょっ! それから次は、●●●●●に●●●と●●を付けて、●●●●●●●って事までしちゃう気なんだわっ!!」
「お、おう……」
私の想像力に、ガマガエルはドン引きしたっぽかった。
「……まあ、その元気が続くのもあと少しだ。取引きは四時間後、せいぜい神様にでも祈っときな」
ガマガエルは浦賀さんを引き連れて廃ビルから出て行った(浦賀さんカムバーック!)。近くにエアコンの効いた車でも待機させてあるんだろう。
「ちょ、待ちなさいよ! 放して、帰らせて、トイレはどうすんのよーっ!?」
私が泣き叫んでも、周りの手下達は下卑た笑い声を上げるだけだった。
私が乙女としての恥じらいを捨てるか否か選択を迫られている間に(要するにトイレの事)、陽がすっかり暮れてしまった。
喚き続ける事に疲れた私は、大人しく転がされたままでいる事にした。砂っぽい地面が嫌だったけど、乱暴されないのがせめてもの救い。手出ししたら『商品価値』が落ちる事を、連中は知ってるんだろう。
……はぁ。何やってんだろ、私。今日、誕生日なのに。
そう考えたら、何だか哀しくなってきた。今日から大人になるんだよって記念すべき日なのに、私を祝ってくれる人はどこにも居ない。それどころか誰かに売られちゃうなんて酷すぎる。
ふと、九歳の誕生日を思い出した。お父さんが祝ってくれた、最後の誕生日。ケーキのロウソクを一息で吹き消して、部屋の明かりが点いたらお父さんとお母さんが「おめでとう」って言ってくれて。確かあの時は、前から欲しかったクマのぬいぐるみを貰ったっけ。一番楽しかった頃の記憶、家族全員が笑顔だった時の思い出。今も鮮明に覚えてる。
――だけど。あの日はもう戻ってこないんだ。だって、お父さんがいなくなっちゃったから。
「……お父さん」
声に出したら、涙が出てきた。
お父さん、どうして私とお母さんを残して居なくなっちゃったの? 私、お父さんのこと大好きだったのに。将来はお父さんのお嫁さんになるって言ったよね、なのにどうして逝っちゃったの。怖いよ、哀しいよ、心細いよ。もし聞こえてるんなら、天国から助けに来てよ……。
「――おい」
無遠慮な声で現実に引き戻された。顔を上げると、嫌らしく笑うガマガエルが見えた。どうやら取り引きの時間が来たらしい。
「お客さんだぜ」
新しく増えた人間が何人かいた。顔付きからして東洋系だけど、話してる言葉が分からないから外国のマフィアか何かだろう。
私の知らないところで、勝手に値段交渉が始まった。ガマガエルの側近が指を五本出すと、相手は首を横に振り、今度は指を三本立てて見せる。その後にゼロが幾つ付くかはあまり考えたくない。
そうしているうちに、お互い納得したらしい。東洋系の一人がアタッシュケースを持ってきた。ガマガエルの手下がそれを受け取り、私に向かってアゴをしゃくる。交渉が成立したみたいだ。
自分が物みたいな扱いを受けてるのを見ると、抵抗する気力も無くなってしまう。私は暴れもしないで、買い手のなすがままにした。
と、その時。
『――警察よ!』
辺り一面が昼間のように明るくなる。廃ビルの周りに設置されたサーチライトが、取り引きに関わった全員を照らし出していた。
『人身売買の現行犯で全員逮捕する!』
拡声器で増幅された声は美琴さんのものだった。全然助けに来ないと思ったら、私が売られる瞬間を待っていたらしい。ここでようやく警察のお出ましとは嬉しい限りだけど、自分が囮に使われたみたいで釈然としない。それでもまあ、助けに来てくれた事には感謝するべきなんだろうけど。
美琴さんの合図で、一斉に警察が動いた。制服・私服入り乱れての連合軍だ。取り押さえようとする側と抵抗する側の怒号が飛び交い、辺りは一時騒然となる。
肝心の首謀者、ガマガエルはというと――
「逃げたぞ!」
誰かが叫んだ。と同時に、銃声が鳴り響く。ガマガエルの側近がぶっ放したからだ。
すると警察側も応射。そうなるとあとは雪崩みたいなもので。
かくして、嵐のような銃撃戦が始まったのだった……。
――って! 冷静に解説してる場合じゃない、私を真ん中に置かないでぇぇぇぇっ!!
頭の上をびゅんびゅん通り過ぎる銃弾。身動き取れない私の近くに何発か着弾した。その度に寿命が削られていく思いだった。
ちょ、死ぬ! マジで死ぬ!! どっちでもいいから、私を避難させてよぉぉぉう!
『皐月ちゃん、頑張って!』
「やかましいっ!」
美琴さん、そもそもあんたが私を騙したからこうなったんでしょーがッ!!
そう叫ぼうと思った時、一人の警官が倒れた。銃弾をまともに喰らったらしい。息はまだあるみたいだけど、命に別状があるかどうかは別の話だ。そうこうしている内に、また一人。もう一人。銃の性能からして、犯人側のほうが有利みたいだった。
「しゃらくせぇ!」
犯人側の一人が、大振りの銃を構えた。あんまし詳しくないから分からないけど、多分あれはマシンガン。目の前にいる人間を手当たり次第撃つにはうってつけの武器だ。あんなものを持ち出すなんて正気の沙汰じゃない。
――これまでか。
私は観念して、両目を閉じた。
――大丈夫ですよ――
そんな声が聞こえた。いや、実際に聞こえたかどうかは知らないけど、そんな気がしたのだ。
目を開く。すると視界に飛び込んできたのは、私に背を向けて仁王立ちしている男性の姿だった。
男性は両手を広げ、身体の正面を犯人側に向けている。まるで私を庇うみたいに。
大きい背中だった。力強く、だけど優しさを内に秘めたような。
これはお父さん…………じゃない!
「須藤さんっ」
名前を呼ぶと、須藤さんは振り向きもせずに頷く。背中には何も書いてなかったけど、〈もう大丈夫です〉という文字が確かに見えた。
思わぬ闖入者に、一瞬、銃撃がぴたりと止まる。須藤さんにとっては、それだけで充分だったらしい。
目にも止まらぬ速さで、ジャケットの内側から拳銃を抜いた。流れるような動作で銃を構え、犯人側に向けて――発砲。
拳銃にしては、やけに間の抜けた銃声だった。
「がっ!?」
犯人側の一人が胸を押さえて倒れる。銃弾を受けたらしい箇所には赤い血がべっとりと……いや、痛がってるだけだからペイント弾かもしれない。
私が推測してる間にもう一発。あとは一定のリズムを刻みながら連射。須藤さんが放った銃弾は寸分違わず命中していた。射撃の名手って武勇伝は本当らしい。
やがて、十数人いた犯人達が残り一人になった。
「くそっ!」
ガマガエルが鳴いた。一番後ろで高見の見物してたんだから、最後に取り残されたのは必然だろう。親分は往生際悪く、弾避けに使われてた車に乗り込んだ。
エンジン始動、タイヤが空回り、いきなりフルスロットルしたからだ。そのまま車は、一直線にこっちへ向かってくる。目の前にいる私達をひき殺すつもりなんだろう。
警察側が一斉射撃。だけど銃弾が跳ね飛ばされる。そうしている間にも、ガマガエルの乗った車は私と須藤さんに向かってきた。
「須藤さん、逃げて!」
私は叫んだ。自分の安全なんかどうでもいい。今は自由に動ける須藤さんに退避して欲しかった。
なのに須藤さんは動いてくれない。銃の弾を交換する余裕さえある。
〈勝負です〉
須藤さんが捨てた空っぽの弾入れ(後で聞いたらマガジンとか言うらしい)には、そう書いてあった。
勝負も何も、ペイント弾なんかで車に勝てるわけないでしょうが!
須藤さんは私の前から動かない。その場で銃を撃ち始めた。
一発。フロントガラスの左斜め上。
二発。今度は対角線上に。
三発。助手席側。
四発。中央。
みるみるうちにフロントガラスが赤く染め上げられていく。この状況で外れが無いのは驚異的だった。
地面の震動が激しくなる。それに比例して心臓の高鳴りも。目を閉じることさえ出来ない。
須藤さんも弾が残り僅かなはず。なのに淡々と撃ち続けてる。そうだ、これはきっとチキンレースなんだ。
けど時間がない。距離もあと少し。私の歩幅であと八歩、いや六歩……!
――もうダメっ!
そう思ったのと同時に、須藤さんが最後の一発を放った。
『おおーっ!』
歓声が上がる。運転席の正面に命中、これでフロントガラスが一面真っ赤になった。
「なぁぁぁぁっ!?」
ガマガエルが驚愕の声を上げた。視界を奪われて怖くなったのか、ハンドルを左に切る。車は須藤さんの横をすり抜けて、瓦礫の山に突っ込んでいった。そして――
激突、大破。暴走車はようやく停止したのだった。
割れんばかりの拍手が響いた。須藤さんの神業に警察一同感銘を受けたんだろう。
……この人、何者だ。今まで役立たずのおっさんだと思ってたのに。
信じられないでいる私に、須藤さんが向き直った。いつものように優雅な笑みを浮かべて、左手をさしのべてくる。いつも嵌めている腕時計が無かったのが不思議だったけど、私は須藤さんのネクタイを見て笑顔になった。
ネイビーブルーのネクタイには、白文字でこう書いてあったのだ。
〈さあ、一緒に帰りましょう〉
あの後、私が須藤さんの手を取って、二人で抱き合いながら熱烈なキスの応酬。二人はめでたく結ばれましたとさ……とかなってたらよかったんだけど。生憎現実はそこまで甘くなかった。だって私、簀巻きのままだったもん。
それはさておき。あのあと私は警察に身柄を保護されて、検査入院させられる羽目になった。結論から言えば、検査結果は何の問題もなし。強いて挙げれば膀胱炎になりかけていたそうだけど(私、頑張ったよ!)、それは日常生活でもよくある事なので支障なしと診断されたらしい。
ところで、お待ちかねのネタばらしは以下の通り。
まずは事件の詳細から。美琴さんの話では、ここ一年で若い女性の失踪事件が相次いでいたらしい。そこで詳しく調べてみたところ、国際的な人身売買組織が捜査線上に浮上してきたんだそうだ。組織の手口は、ファッションモデルのスカウトと称して若い女性をおびき寄せ、誘いに乗ってきたところを拉致するというもの。女性の夢や美意識を逆手に取った卑劣なやり口だ。
捜査を続けてきたものの、いまいち検挙する為の証拠が足りない。だったら囮を使って現行犯逮捕するのはどうだろう。だけど、囮捜査は法律で禁止されてるし。おおっぴらにやるわけにはいかないじゃない。さあ、困った困ったどうしよう……と考えた結果、美琴さんは、一般人が攫われたところへ『偶然』警察が駆けつけた状況を作ろうと計画したのだった。
だったら囮役は誰がいいか。そう考えた時、真っ先に思い浮かんだのが私だったという。というのも、私を巻き込めば須藤さんのおまけが付くからだった。実際、美琴さんは、これまで何度か須藤さんに応援要請していたとの事。刑事時代の手腕を考えれば、それも当然だろう。けれど須藤さんは全然OK出してくれなくて、ずっと断り続けていた。だから私をエサに、須藤さんをおびき寄せたんだそうで。だから、須藤さんがあの場所にいたとしても全然おかしくないってわけだ。
とまあ、昨日の晩に聞かされたのはこんなところ。一通り説明した後で、美琴さんは私に両手合わせて謝った。何でも、須藤さんからこっぴどく怒られたらしい。
須藤さんが美琴さんを叱った。そう聞いて意外に思った。あんだけのんびりした人が怒るなんて、よっぽど腹に据えかねるものがあったんだろう。もしかして須藤さん、私が危険な目に遭わされた事を怒ってくれたんだろうか? そう考えたら何だか嬉しくなってしまう。
それにしても。
あの時の須藤さん、格好良かったなぁ……。
背中をこっちに向けたまま、一歩も動かない須藤さん。あれって、私を守ってくれようとしてたんだろうか。だとしたらこれは『脈アリ』ってやつなんじゃ?
「やーん、もーう!」
布団の中で悶えていると、ドアの開く音が聞こえた。そろそろ最終検査の時間かと思って顔を出したら、そこにいたのはお医者さんじゃなかった。
「須藤さん!?」
そう、須藤さんがお見舞いに来てくれたのだ。さっきの妄想が現実味を帯びてきて、途端に顔が熱くなる。
〈身体の調子はいかがですか?〉
顔にそう書いてあった。いや、これはそう解釈できる笑顔を見せてくれたって意味。
「はっ、はい。お陰様で……」
私はしどろもどろになって変な答え方をする。自分の妄想が顔に出ていないか酷く気になった。
よかったよかったという感じに頷くと、須藤さんはジャケットのポケットから小箱を取り出した。
「私に?」
首を縦に振る須藤さん。受け取って見ると、小箱には〈開けて下さい〉と書いてあった。
箱の中を見て、頬がゆるんだ。中身は、子グマのマスコットが付いた髪留めだったのだ。値段でいえば千円も行かないような安物だけど、このタイミングで渡される事に意味があった。
須藤さん、私の誕生日を覚えててくれたんだ……!
事務所が財政難の今、プレゼントを買う余裕なんかあるわけない。でも、須藤さんが腕時計を付けてない理由を考えたら余計に嬉しかった。
「ありがとうございますっ」
素直にお礼を言うと、須藤さんはいつもと同じ優雅な笑みを浮かべる。そして照れ隠しなのか、私に背を向けた。
〈では、チラシ配りに行ってきます。退院の頃にはまた戻りますので〉
背中にそう書いてあった。付け加えられた一文がまたニクい。
須藤さんが病室を出て行った後も、私のテンションは上がりっぱなしだった。小箱の中にメッセージカードが入っていたので、いそいそと取り出して読んでみる。
〈お誕生日おめでとうございます。そして、いつもありがとう〉
はい、ズキューン来たよこれ。どれどれ、そこから先は何て書いてある?
とか期待していたものの、メッセージはあと一行だけ。そこを読んで私は――絶句した。
〈愛する我が『娘』へ〉
この宛名を見ただけで、須藤さんの考えてる事が全部分かってしまった。やっぱり私は『娘』扱いのままらしい。プレゼントを渡してくれたのだって、純粋な父性愛によるものだろう。
「娘、かぁ……」
気持ちの盛り上がりは一気に最下層へ。失恋したような気がして、私は枕にぼふっと頭を預けた。
「皐月ちゃん、お見舞いに来たわよぉ」
間が悪い事に、美琴さんが病室に入ってくる。
「あら、それ……須藤さんから?」
筆跡に心当たりがあったらしい。
「ええ。私のこと、娘だって」
その一言で、美琴さんは全て察してくれたようだった。すると苦笑を浮かべて、こんな事を言い出した。
「……まあ、ね。須藤さん、愛妻家だったそうだから」
そういえば、須藤さんが声を失ったのは奥さんを亡くしたのが原因だっけ。きっとそれだけ、奥さんの事を深く愛してたんだろう。今も独身を貫いてるのは、永遠の愛を誓ってるからなのかもしれない。
「そう……ですよね」
故人に向けた愛情の深さは、私にも理解できる。だから尚のこと、勝てる気がしない。
私が打ちひしがれていると、美琴さんが「でもね」と付け加えた。その声色は何故か力強くて、私を振り向かせるには充分だった。
「だから燃えるんじゃない」
そう言う美琴さんの顔は晴れやかだった。白馬の王子様を待ってるお姫様じゃなくて、自ら王子様を迎えに行く戦乙女みたいな……そんな魅力に溢れている。
「私、諦めないからね。何だったら、どんな手を使ってでも」
と言って、美琴さんは見事なバストを私に見せつけてくる。両腕で挟んで谷間を強調、中二男子ならそれだけでノックアウトできそうだ。
まさか美琴さん、それを須藤さんの背中に!? あ、くそ。何かカッチーンと来た。
「ちょ、やめてくださいよっ!」
「ふふふ、真似できるもんならやってみなさぁ~い」
おのれ、私がAカップと知っての狼藉か!
「もう! からかいに来たんなら帰って下さい!!」
「はいはい。じゃあ、私は須藤さんを追っかけるわねー」
意地悪な笑みを浮かべて、美琴さんは病室を出て行った。それでも怒りが収まらなかったので、私は枕をドアに向かって投げつける。
「……ま、お互い頑張りましょ」
その言葉を最後に、パンプスの音が遠ざかっていった。
……何それ? もしかして美琴さん、私を元気づけてくれたんだろうか。
まあいいや。今のでちょっと元気出たし。浮いて沈んでまた浮いて、何だか今日は忙しい。
気を取り直して、私は須藤さんに想いを馳せた。
今はまだ娘扱いだけど、きっとそれは私の魅力が足りないからだ。だったら今度は、自分が須藤さんの眼鏡に適う女性になればいい。もう二十歳になったことだし、ひとまず大人の女性でも目指してみますか。
「よしっ!」
気合いを入れてベッドから降りる。そして私は窓を開け、決意新たにこう叫んだのだった。
「須藤さん、愛してるぅぅぅぅっ!」