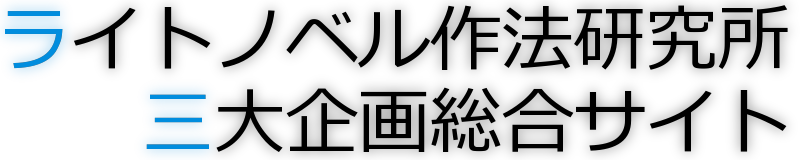2011冬祭り企画優勝作品
『オゾンフィッシュにうってつけの日』

【使用したお題】
終わりと始まり
【一行コピー】
父の人生が終わり、私の旅が始まる。神様はそうなるように世界を作った。

オゾンフィッシュを、既存の生物学において分類することは非常に難しい。
生物学的な観点で見る、古典的な生命の定義は、
一、代謝を行う。
二、遺伝子をもち、繁殖をする。
の二点をクリアしていることである。しかしよく知られている通り、ウイルスの発見がこの定義に対して疑問符を投げかけて久しい。以来、我々は明確な生命の定義を持てずにいるのだから、オゾンフィッシュが生命なのか、単なる自然現象なのか、結論を出せる立場に私はいない。
しかしながら、あくまで感覚的な話をさせて頂くならば、遺伝子を持ちながらも自己では一切の代謝を行えないウイルスの類と比べると、オゾンフィッシュは非常に生命然としている。すなわち、個体的な内部と外部を持つように思われ、代謝と思われるような現象が観察されたのだ。
このことを受け、私はこれらが発生する現象たちを、ひとつの生命体であるように認識し、以下では彼らのことを「オゾンフィッシュ」と仮称して記述をしていきたいと思う。
(あくまで、あるひとつの現象のことを、個人的にそう呼んでいるだけであるということを認識頂き、またご容赦いただきたい)
オゾンフィッシュは、気体のオゾンを体殻としてもち、流線型の形状をした気体の塊である。気体であるが、オゾン分子のもつ電子の不安定さを用い、電子の組み合わせによる電気的な結合によって体を構成していると思われる。
私の想定からすると、彼らは地表から上空約二万メートルから五万メートルのオゾン層のエリアにいると思われる。根拠としては、
一、上空約一万メートルはまだ旅客機の飛行空域であるにも関わらず、オゾンフィッシュであると思われるような現象の確認事例が見られていないこと。
二、私が観測気球によってオゾンフィッシュを確認したのが、上空約三万メートルのオゾン層域であったこと。
三、オゾン層を超えても大気はあるが、オゾン濃度が低下した際に、彼らの代謝に使われるオゾンが手に入らなくなること。また高度一万メートル未満においても同様のことが言える。
の三点によるものだ。
オゾンフィッシュは太陽光や宇宙線による電気的なエネルギーを用いて活動していると思われる。彼らのいる高高度はそれらが豊富にあり、かつ気体の塊である体では、地上の生物と同じように、重いたんぱく質や(液体・固体としての)水を構成要素とするのは難しいためだ。
正確な代謝経路は現時点では調べようがないものの、オゾンフィッシュの発見時に、周囲に比べ、僅かだが明らかに高い電位を観測したことも、この考えの基盤となっている。
***
「……論文としては、失格だな」
榊原風子はそれを聞いて、制服のスカートの上で握った手のひらに、自然と力が入った自分に気づく。
谷口教授は、ぱたりとその本を閉じた。ハードカバーにしては安っぽい、薄い表紙。淡い緑色の無地のカバーに、素っ気ないほどシンプルに題名と作者だけ、こう印字してある。
――オゾン層に生息する空気魚についての報告 榊原清太郎。
谷口教授の研究室は、都内の国立大学の一室にあった。高校生の風子は、これまで大学に来る機会などほとんどなく、ましてや研究室に入ることなどなかった。だから、その空気に少し飲まれていたのだと、後になって思い返す。
陽に焼けて変色した本や資料の束が、所狭しと……本当に足の踏み場もないほど部屋の中に散乱しており、中途半端に年代物の本棚やほこりの被った机が、その奥で見え隠れしている。教授の座っている一角のみ、多少片付けられているものの、とはいえ大差はない。
そんな中に最新式で高性能(だと思われる。風子はパソコンのスペックまで詳しく知らなかった)のパソコンが三台も置いてあり、画面の中で日本上空の雲の衛星画像が、カクカクとパラパラ漫画のようにアニメーションとして流れていた。
教授はそのパソコンの側に本を置いて、傍目に見てきれいとは言えないマグカップでコーヒーをすする。
「まず、論文としてのフォーマットを無視している。普通は表題、概要、目的、調査方法……といった順に並べて、個人の想像は極力省いて記述する。これはどうも、書きたいことをただ単純に並べただけのメモに近い。まあ、ある種のエッセイと言ってもいいが、それにしては文才がないな」
そこまで言ってから、教授は風子に目をやった。
「で、君はこれを僕に見せてどうするつもりだった?」
谷口教授はもう六十歳を超えているらしい。白髪でしわの寄った顔、度の強いめがねの奥で、しかしその奥の目は鋭かった。
風子は緊張で、ごくりと唾を飲み込む。脇で汗がにじんだ。
「……父は、病床でこれを書き終わった直後に死にました」
ぴくり、と谷口教授のまぶたが動いた。視線が風子に突き刺さる。
「父はその前に自分で、この本を自費出版で作るよう、業者に依頼をしていたみたいです。気象研究者として父は世界中を飛び回っていましたから、私はほとんど父との思い出がありません。だから、家に届いたこの本を読んだときも、私はこれをどうすればいいのかわからなかった。ただ、父は何かすごい発見をしていて、それを世に知らしめたいんじゃないかって。
もし本当にこの本に書いてあるように、空に魚がいるのだとしたら、きっと世界でニュースになるんだろうと思いました。だから、父がお世話になっていた谷口教授に、まず読んでもらいたいと思ったんです」
風子の声は、緊張で少し震えていた。谷口教授は、少し眉間にしわを寄せながらため息をつく。
「君は、このオゾンフィッシュなるものについて、清太郎君に何か聞いていたのか?」
「いいえ……もともと父と会うことも稀でしたし、最近は南極越冬隊に参加したりして、病気になるまでは一年以上会っていませんでした。たまに会っても、父は仕事のことは何も言っていません」
教授は立ち上がって、窓際のコンロでカップにコーヒーを注ぎ足した。風子の方は向かずに、丸まった老人の背中だけが風子に向いていた。
「彼は、優秀な学者ではあった。研究者としては少し視野が狭い部分もあったが、まあ、学者なんてそんな人種しかおらんがな」
教授はカップを二つ持っていた。一つはそのまま風子に差し出す。教授のものと同じように汚れたカップだったが、風子は何も言わず会釈だけして受け取った。
「そんな彼が書いたものだ。逆に言うと、彼はこの本を、論文として出す気はなかった。要するに公式に発表するつもりがなかったんだな。まあ普通に考えて、もしこれが本当だとしても、すぐには受け入れられるはずもない。再現性のある検証が行えないものについて、科学的にはそれが真実だとは認めない」
風子は心のどこかでぎくりとした。
風子も薄々気づいてはいた。たとえ世紀の大発見があったとしても、それが世間に認められるのは膨大な時間と検証が必要になるだろうということは。恐竜の化石が、それが過去に実在したと認められるまでの様々な経緯については、詳細はわからないにしても、なんとなく知識として知ってはいる。
だとすると、父は――清太郎は逆に、なぜ公式なデータとしてオゾンフィッシュを示さなかったのか。普通の公立高校の普通科に通う、普通の女子高生には、そこまで想像力は働かない。
ただ、父はなにかをメッセージとして残したかったはずだ。死の間際ではあったが、一冊の本を残すだけの時間を、ただそれだけに費やしたのだ。多分、人生で最も貴重な一瞬を。
「……教授は、なぜ父がこの本を残したと思います?」
風子はうつむいて、つぶやくように言った。教授はコーヒーをすすりながら、風子から目をそらせて宙を仰ぐ。
「真面目な人間だったよ、清太郎君は」
ただそれだけ言って、教授は口をつぐんだ。
***
私がオゾンフィッシュに遭遇したのは、南極越冬隊に参加したときのことだっだ。
約一年もの間、私は極地の、さらに極地で気象観測に従事した。このときは厳しく辛く、しかし楽しい一年間であったことは間違いない。ただ、そのことを語るのが本稿の趣旨ではないので、あえて割愛させていただく。
その日、私はいつものように大気観測用の気球を飛ばしていた。本来の目的はオゾンゾンデを使用したオゾン層の観測だ。南極におけるオゾン層の破壊が唱えられて久しいが、最近はフロンガス排出規制により、徐々に回復傾向にあると言われている。その時も、このオゾン層の濃度の実態を探るための観測が目的だった。
しかし、気球が上空三十キロに到達した際、不具合が生じた。おそらく気球の点検不足だったのだろう、気球の一部が割れてしまい、オゾンゾンデは急速に落下を始めた。
その気球が、離陸した私の地点に数十メートルも離れず着地したことは奇跡としか言いようがない。なにせ高度三万メートルからの落下だ。しかもその間に吹き荒れる様々な気流に揉まれつつも、私の元へ戻ってきた際は、少なからず驚いた。本来なら数百キロ風に流されても不思議ではないのだ。
ただ、その時はまだ私は、珍しいこともあるものだ、としか考えていなかった。運良く機材を無駄にせず、再利用できるかもしれない(オゾンゾンデは一台数十万円は下らない高価な機器である)と思っただけだった。
そして破れた気球に駆け寄ったとき、私はあることに気づいた。
気球の中で、何か動くものがあったのだ。最初は割れた気球が風で揺れているものだと思っていたが、そうではない。破れた袋状の気球の中から、何かがつつくように、中から押されているように動いたのだ。その光景は、昔、縁日で金魚すくいをして、ビニール袋に入れた金魚が中から袋をつつくような動きだった。つん、とわずかに動く程度だが、確かに感触はあった。
私は恐る恐る、破れた気球の中をのぞいてみた。しかし、そこには何も見えなかった。それでも手には、例のつん、つん、という感触は続いている。意を決して、私は気球の中に手を入れた。
確かな感触は、なかった。しかし、手に残るわずかな抵抗感は確かにあった。袋の中で手をかき回してみると、ある部分でだけ、まるで緩やかな風を受けているような、ふわりとした抵抗があるのだ。
気球の中に顔を入れようとして、破れた口に顔を近づけたとき、私の頬を何かがなでて行った。空気の塊ではあったが、それだけではない何かだ。そしてオゾン特有の金属的な匂いを感じた。
その空気の塊は、私の白い、吐く息がかかった。南極でそんなものは一瞬で凍り付いてしまうのだが、その時、確かに私は見たのだった。白い水のコロイドをまとった空気の塊が、まるで魚のように流線型になり、そして少し空中を泳いだように見えた。
もっともそれらは、そのまま霧散するように数秒の後に消えてしまっていたのだが。
***
「ああ、ほら、この辺とかせいちゃんっぽいなあ。最初のほうは真面目に書いてるのに、この辺に来るともうノッてきちゃって小説っぽくなってる。
書き始めたときは新書のブルーバックスみたいにしたかったんだろうけど、書いてくうちにどうでも良くなったのかもね」
と言って佐久間太郎は大きな声で笑った。
ひげ面で色黒の大男。眉毛も手の甲もモジャモジャと黒々とした毛が生えていて、山男っぽい印象もあるにせよ、清潔感は感じられない。なのに、来ている白衣だけは真っ白で染みひとつなく、そのギャップが風子には不審に思えた。
こんな風体にも関わらず、佐久間は医者だった。南極越冬隊にも参加し、風子の父親とも一年間、同じ釜の飯を食った仲でもある。
「そうそう、せいちゃんとはよく麻雀したよ、うふふ、これがせいちゃん面白くてね」
「麻雀、ですか……?」
風子は佐久間に圧倒されていた。病院の一室で、小さな椅子に座らされて縮こまる風子に気も留めないかのように、佐久間は大声で(しかもどこかおネエ言葉で)楽しそうに話し続ける。
「そうなのよ。南極越冬隊って、まあ普段、暇じゃないんだけどルーチンワークばっかりだから、それが終わったらやることないのね。しかも刺激もなけりゃ寒すぎて散歩もできない。だから夜は隊員集めて一週間耐久麻雀ってのを開催してね……」
くくく、と佐久間は笑う。
「せいちゃんって真面目だからさ、最初は役牌で小さく地味に上がってたのに、負けてくるとムキになってくるのよね。で、だんだん大きな役を狙いだしたり、かと思えば地味に『中』のみとかね、緩急織り交ぜてくるのよ。腹立つでしょ。
あーあ、あの役牌のみと見せかけての混一には何度やられたことか」
あーあ、あれでかなりスッたのよね、と佐久間はおかしそうに笑った。
「でもね、あのせいちゃんがガンだったなんてね……僕も医者の端くれならわかっても良かったのに。悔しいわ」
「……発見されたのは南極から帰ってきた次の年でした。越冬隊のときは、腫瘍があったとしてもまだ小さかったでしょうし……佐久間さんは、悪くありません」
風子がそう言うと、佐久間は目を細め、静かに頷いた。
「あんたもやっぱりせいちゃんの娘ねえ。そういう真面目なところや気を遣うとこなんてそっくり」
風子はそれを聞いて、胸の奥のほうでむず痒いものを感じる。ほとんど家にいなかった父親に似ていると言われても、実感はわかないのだが、どこか嬉しいような恥ずかしいような、妙な気分だ。
「それで、せいちゃんがこんな本を書いてたなんてね。僕は素直に面白いと思ったわ。真偽がどうこうを別にすれば、昔の博物誌や冒険小説みたいじゃない。シートン動物記とかね。まあ、でも……」
佐久間は少し切なげに、薄いカバーの冊子をなでる。
「シートンはフィクションじゃないかもしれないけど、せいちゃんがそんなフィクションを書けるような気もしないしね。オゾンフィッシュねえ。そんなものが本当にいるのか、それともせいちゃんの願望なのか……僕には判断つかないわ」
ふう、と佐久間はため息をつく。
「で、娘のあなたはどう思う?」
「私は……オゾンフィッシュは実在するかもしれないと思っています。父とは滅多に顔を合わせませんでしたが、本当に小説をかけるような人間かと言われると、そんなイメージが全然湧きません……」
「そうね、僕もそう思う。じゃあなぜ、せいちゃんはこの本をあなたに託したのかしらね」
「……それを聞きたくて、今日は佐久間さんにお伺いしました。父は、一体なんの意図があったのでしょう。本当にオゾンフィッシュが実在しているのなら、論文ではなく、なんでこんな自費出版で私に遺したのか」
風子はそう言って視線を下げる。
去年、谷口教授に会って以来、風子はこうして父に縁のある人物を訪ねて回っている。最初は見ず知らずの人間に会うこと自体にかなり緊張したものだが、最近は慣れてきたのか、以前よりは自然に話すことができるようになった。
とはいえ、この質問をするときは、いつでも同じだ。心臓をロープで縛られたかのように、胸がぎゅっとなる。この感覚の招待を知りたくて、風子はかれこれ一年間もこうして父の友人を訪ね歩いているのだ。
そんな風子を、佐久間は目を細めて眺めていた。そして手に持った本を風子に差し出すと、小さく息をついた。
「医者をしていると、どうしても人の死に触れてしまう。僕も何人もの患者を看取ったけれど、こんな風に誰かに何かを遺して死ねるのなんてすごく稀なこと。だから、僕はあなたの父親は、せいちゃんは幸せな死に方だったと思うよ」
そういうと、佐久間は椅子に深く座りなおし、ひざに肘をついて顔を風子に向けた。
「……そして、そういう人が遺すものは、誰かへのメッセージが多い気がする」
「メッセージ……ですか」
佐久間は頷いた。
「つまり、せいちゃんは論文として世界にメッセージを送ることよりも、ごく一部の身近な誰か、というか主にあなたにメッセージを送ることを選んだ。それがこの本だった」
佐久間のひげ面が、そこについている二つの目が真っ直ぐに風子を見ている。
風子はその視線を浴びて、息を吸った。そして思う。父親の周りには、良い人が多かったのだと。
「……私に、オゾンフィッシュの存在を知って欲しかった?」
「直接的には、きっとそう。だけど」
佐久間は目を閉じ、少しの間、黙り込んだ。言葉を選んでいるようにも見えた。
「……まあ、せいちゃんはあんな性格で、意外と大事なことをストレートに伝えられない人なのよね。奥さん、ああ、あなたのお母さんと出会ったときも、付き合いだすまで大変だったみたいだし」
佐久間は目を開いて、ふふっと笑った。その微笑が、言葉よりも強い何かを伝えたがっている。それが、風子には感じられた。
「あなたは高校三年生だっけ?」
「はい、そうです」
「そう、じゃあ今年は大学受験? 進路は決めた?」
風子は少し宙を見上げた。少し言いづらそうに、
「……理系の大学を受験しようと思います。父と同じように、大気や気象の方面に興味があるんです」
それを聞いた佐久間は、なぜかがっかりしたように顔を上げ、大きなため息をついた。
「なんだせいちゃん、またツモったの。しかも役満よ、これ」
***
オゾンフィッシュを観測することはとても難しい。しかし、不可能というわけではない。
オゾンフィッシュは、外殻をオゾンで構成していると思われるが、しかし体の全てがオゾンでできているとは考えづらい。組成の何パーセントかは大気と同じ成分――窒素、酸素、二酸化炭素などでできていると考えたほうが自然だ。であるならば、放射線同位体などを用いることで個体にマーキングすることも可能だと思われる。
しかし、最も簡易的な方法は、コロイド状の気体を外殻もしくはその内部に入れてしまうことだろう。いずれは代謝や、そうでなくとも分子運動で拡散していくだろうが、瞬間的には可視状態でオゾンフィッシュを認識できる。南極で私の吐息をオゾンフィッシュが持っていったように、煙などをオゾンフィッシュの体内に紛れ込ませられれば、緩やかに結合している外殻に沿って、煙の塊がオゾンフィッシュの姿を明らかにしてくれる。
非公式だが、この煙によってオゾンフィッシュ(と思われるもの)を視認できた例がある。
二〇× × 年、アメリカのシャトルの打ち上げの際の回想録として、当時宇宙飛行士であったジャック・マクファーソンが残した文章がある。そこには、シャトルが大気圏を脱出した後、自らが昇ってきたロケットの後塵を眺めていると、遠くでロケットの煙がわずかにちぎれ、いくつかの流線型の欠片に分かれたというのだ。
それらはしばらく大気中を泳ぐように、いくつかの塊として空中を漂っていたという。それらは風に流されるのとは思えぬように、右へ左へと、わずかだが自由に動いているように見えた。それはさながら海を魚が泳ぐようだった、そうジャックは記述している。
私もこれを受け、何度か実験を行った。子供が遊ぶ花火の一種の煙球を、ある一定の時間が経つと発火させるような簡易的な装置とともにオゾンゾンデの気球に取り付け、空中に飛ばしたのだ。
何度もこの実験を行ったが、成功したのは一度だけだ。ただ、この一度は私の生涯で最も印象的な瞬間でもあった。
私は気球を飛ばす際、小さなLEDのライトを取り付け、それを目印に地上から望遠鏡で観察するという原始的な方法で煙の行方を追っていた。
その時も、気球が高度三万メートルに差し掛かった折だった。発火し煙を噴き出した煙球が、もう煙が消え去ろうとしているとき、ぼんやりと漂っていた煙の一部が急に、ちぎれて泳ぎだしたかのように見えたのだ。
その塊は大小六つに分かれて、まるで泳ぐようにオゾン層を生物然として移動したのだ。
これは、私の認識の傾向が偏っていることも認めたうえで、それでもなお言わせていただけるならば、魚の群れがそこを悠然と泳いでいるように見えた。
このとき、私は確信できた。
空には我々の知らない何かがいる。そしてそれは、海と同じように広い世界を住処とする、これまで我々の認識の外にあった未知の生物なのだろう、と。
***
ジャック・マクファーソンの家は、カリフォルニア州の田舎町にあった。
アメリカの基準にすると、それほど大きな家ではないのだろう。しかし白く塗られた壁や、きれいに整えられた庭の芝生をみると、それだけで彼の誠実な人柄がわかるような気がした。
「正直なところ、わざわざ日本から、本当に来てくれるとは思わなかったよ」
年老いたジャックは、白髪ではあるが豊かな髪を整え、落ち着いた様子で風子の前のソファーに座った。
「こちらこそ、お目にかかれて光栄です。引退されたとはいえ、宇宙飛行士の方とお会いできる機会なんて、想像もできませんでした」
風子がそう言うと、ジャックは少しはにかんで笑った。
「いやいや、私こそこんなかわいいお嬢さんと話す機会なんて、そうそうあったもんじゃない。失礼だが、我々アングロサクソンを見慣れている人間には、東洋人は若く見えるんだが、ミス・フーコ……君は大学生だといっていたね」
「ええ、今年で四年になります。初めてメールでご連絡したときから五年も経ってしまいました。本当なら、もっと早く来たかったのに」
「いや、そんなことはない。君はこの五年の間にとても興味深い本を送ってくれた。私が日本語を読めないからといって、独学で君の父親の本を翻訳してくれた。あの本は面白かったよ。とても印象深い」
フーコは、はにかんで微笑んだ。
清太郎の本に載っていた宇宙飛行士の文章は、彼が引退後に始めたブログの中にあった。それを探し出した時点で、書かれてから既に数年が経っていたが、運良くログが残っていたこと、そしてそこに表示してあったメールアドレスが変わっていなかったことが風子にとって幸運だった。
たどたどしい英語で始めたやり取りも、父親の本を辞書を片手に必死に英語に直した甲斐もあって、風子は大学三年に上がる頃には、ほぼ完全に英語を身につけていた。
その間に風子は高校を卒業し、国立の理系の大学に進む。着慣れた制服を脱ぎ捨てた後も、風子は気象学や英語の勉強に励み、いつしか一人の研究者としての一歩を踏み出していた。一人暮らしを始め、メイクも上手くなり、ハイヒールを履くようになり、髪も伸びた。父の遺した本をもとに、初めて大学の谷口教授を訪ねたときから、もう五年が経つ。それを思い出し、風子は少しノスタルジックな気持ちを抱く。
「そう、君の父親の本のことだが。彼は、よく私の趣味で残した昔のブログを発見したね。ウェブ社会とは面白いものだよ。私は君が連絡をくれるまで、そんなことを書いていたことをすっかり忘れていたよ」
「でも、私にとっては幸運でした。こうして直接お会いすることも叶いました」
「ああ、本当に。しかし、この本は面白いね。確かにあの時、煙が泳いだように見えたのは確かだ。しかし私は、それが生き物によるものだという仮説など、全く思いつかなかった。まあ、私も初めて宇宙に飛び立つことができて興奮していたんだ。シャトルの煙のくだりも、地球の大気とは美しいものだ、という意図で書いたのだよ」
「では……ミスター・ジャック、あなたはこの本の内容についてどう思われます?」
風子が尋ねると、ジャックは少し困ったようにあごをなでた。
「……わからない、というのが正直な感想だ。ただ、そうあって欲しい、という内容でもある。そうだな、突然だが君は、クリスチャンかい? それともブッディズム?」
思わぬ質問に、風子は困惑する。
「……どうでしょう。日本は文化的には仏教なのでしょうが、私はそれを意識したことがあまりありません」
「そうか。私は神を信じていてね」
そう言いながら、ジャックは立ち上がって、部屋の壁にある本棚に向かう。そこには美しいカバーの何冊かの本と、彼が宇宙飛行士だった頃の写真やNASAのバッジとともに、地球儀が飾ってあった。ジョンはそれを持ち上げてくるくると回す。
「神は七日間でこの世界を作った。海、山、空、木、動物や人間……そして宇宙。ただ、私は思うのだが、神はその時に何を作ったかを、全て我々人間に教えてくれているわけではない。だから私が見たものも、自然現象なのか、未知の生物によるものなのか解らないが、どちらにしても神が作られたものなのだろう。だとすれば、この美しい地球を作った我らが神は、やはり美しいスカイフィッシュを作られても不思議ではない」
ジョンはそのまま地球儀を回しながら、風子の前に座りなおした。そして地球儀をテーブルの上に置き、手を組んで風子に向き合う。
「科学者は神の作った世界を解き明かす職業だ。私は宇宙飛行士だったが、科学者ではなかった。もちろん多少の科学的な知識はあるが、それが本業というわけではなかったからね。だから私は、君の父親が記したようにオゾンフィッシュがいたとしても良いと思っているし、もしいなかったとしても、神がそう世界をつくったまでのこと。君は、オゾンフィッシュを探してみたいと思っているのかい?」
風子は息を呑んだ。
その問いは、何度も自問自答したものだった。オゾンフィッシュが実在していて、それが空を泳いでいるとしたら、それを捕まえてみたいと思うのも確かだ。
しかし、風子は頭のどこかで、それを追い求めて行きたいという欲求が、衝動にならないことを感じていた。
風子の、父の本をめぐる旅は、多分、オゾンフィッシュを追い求める旅ではなかった。
では、何のためにアメリカまで来たのか。
何人もの人々に会いながら、何を求めていたのか。
清太郎がこの本に記し、風子に託したものは何か。
それを知りたくてカリフォルニアにたどり着いたのだ。
風子の中で、それは漠然と形をつくっていた。けれども、直接的にそれを問われたことは無かった。
今までは。
そして今、風子の中でその問いに対し、何かが急に実体を持ちはじめたのだ。たとえるなら、そうれは目に見えない、けれどもそこに存在するオゾンフィッシュのように。
「私は」
風子は息を吸って、吐いた。
雲が晴れるように、頭の中がクリアになっていく。まるでカリフォルニアの晴天の空のように。この空のどこかに、オゾンフィッシュはいるのかもしれない。今の風子には見ることはできないけれど。
「父が遺したこの本に背中を押されてきました。父が論文ではなく、あくまで私書としてこの本を書いたことは、私や父に近しい人へのメッセージだったのでしょう」
「……それは、どんなメッセージだと思う?」
ジャックは優しく微笑んだ。きっと、宇宙から地球を見るときも、こんな笑顔になるのだろう。
「世界は、私が思うよりも広く、私が考えている以上に不思議です。そして、私たちは普段、それを意識して生きていません。私はこの本を読むまで、ただの高校生でした。夢や目標もなくて、ただなんとなく毎日を過ごすだけの。
でも、それだけじゃもったいない。世界には不思議なものも見たことの無いものも、想像のつかないものが、それこそ想像もつかないほど存在している。
それに気づくことができれば、何かが始まるかもしれない。たとえば、父が世界を飛び回ったように。そしてミスター・ジャック、あなたが宇宙に飛び出したように。
父はもしかしたら、それを死ぬ前に伝えたかったのかもしれません」
風子のほおを、何かが伝った。触れてみると、指先が濡れていた。
悲しくはなかった。飛び上がるような喜びを感じたわけでもなかった。
なのに、涙が流れていた。
とても自然に。もともと、そうなるものであったかのように。
きっと神様が、そうなるように風子を作っていたのだろう。
風が吹くように。
太陽が昇るように。
海に波が起こるように。
風子の知らない世界は、風子が知らないだけで、当たり前に、そこにある。
帰り際、玄関のドアを出たところまで、ジャックは見送ってくれた。
太陽は既に隠れていたが、残り香のように、まだ明るさを残した藍色の空が広がっていた。夜の空気の匂いが、ほのかに風子の鼻をくすぐる。風子は空を見上げる。
「きれいな場所ですね」
「ああ。地球はきれいだよ。直接見た私が言うんだから間違いない」
そう言ってジャックは笑う。そして、
「そうだ……君は、サリンジャーは読んだことはあるかい?」
風子は少し考えて、首を振った。
「そうか。サリンジャーはアメリカの作家で、有名な作品に『バナナフィッシュにうってつけの日』という短編がある。内容はある青年の穏やかな日常を描いているのだが、ラストシーンで彼は、なぜか突然、拳銃で自殺してしまうんだ」
ジャックも空を見上げる。星がひとつ、ふたつと輝きだしていた。
「なぜ青年は突然死んでしまうのか。それを考えることがこの作品の面白さでね。いや、オゾンフィッシュという言葉を考えていると、ふと思い出したんだ」
ジャックは風子を見る。父親のように、それとも、先生のように。
「今日はさしずめ、オゾンフィッシュにうってつけの日だったよ」
風子は、五秒間、ジャックの顔を見つめ、静かに頷いた。
父の人生が終わり、残された本によって、風子の中で何かが始まった。それがこの旅になり、それもおそらく、これで終わる。
けれども。
「ミスター・ジャック。私は」
風子は晴れ晴れとした気分だった。
「これから、神様の作った世界の不思議を、探しに行こうと思います」
***
結局のところ、オゾンフィッシュとはなにか、という問いに、私は正確には答えられない。
しかし、空に泳ぐ生物のようなものを、私が見て感じたことは、それが私一人の限定的な観測と体験だったとしても、これだけは間違いない。
オゾンフィッシュは、普段我々は見ることができない。
しかし、私は確信する。空には海と同じように、気流と物質による環境をもとに、我々の知らない何かがあるということを。
そして、私は想像する。オゾンフィッシュが空を泳ぎまわり、空気のクジラやくらげが空に遊ぶことを。そして我々は、水と空の二つの青い海に挟まれて生きているということを。