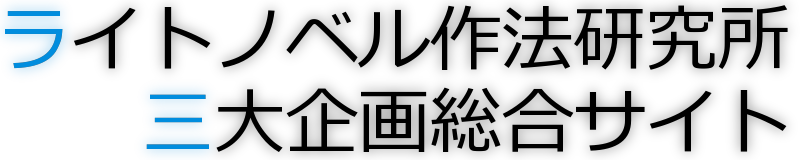2011冬祭り企画優秀作品
『雪舞う聖夜のLVSS』

【使用したお題】
終わり
【一行コピー】
ロリコンサンタ VS シスコン兄貴

「――必ィィッ殺! 《爺射刺・喰捨人(ジイィザス・クライスト)》ォォォオオオッ!!」
雪舞う聖夜。幻想的な風景を破壊するかの如く、砲撃のような声が轟いた。叫んだのは上半身裸の老人。先端にポンポンの付いた帽子と白い豊かなヒゲからして、サンタクロースに見えない事もない。
「っぐふぉぉぉッ!?」
少年漫画のような呻き声と共に、空手着姿の父が宙を舞っていた。百キロはありそうな巨体が高々と打ち上げられ、かと思えば落下を始める。綿のような牡丹雪が降る中、まるで雪の塊が落ちてくるようだった。
地面に激突、父はそれきり動かない。辛うじて息をしているようだが、白目を剥き、身体を小刻みに痙攣させている。これではもう、二度と立ち上がれまい。
「……これで決まりだ。約束通り、娘は貰って行くぞ」
雪を踏み鳴らしながら、〈サンタクロース〉がこちらに向かって歩いてきた。近づくにつれ、ボディビルダーのように鍛え抜かれた身体が鮮明に見えてくる。
「……っ!」
二瓶清正(にへい きよまさ)は、逃げ出したい衝動に駆られた。十六年間という人生の中で、今日ほど恐ろしいと感じた事はない。迫り来る敵が強大であるのに対し、自分はモヤシのように貧弱な身体しか持ち合わせていないのだ。妹を庇う為に勝負を挑んでも、目の前の相手に勝てる気がしない。こうなると分かっていたら、引きこもりになんてならず、空手の一つでも習っておけばよかったと後悔する。
「小僧、そこをどけ」
〈サンタクロース〉の声には、有無を言わせない迫力がある。しかし後ろで震えている妹の事を思えば、ここを動く訳にはいかなかった。
清正は、ありったけの勇気を振り絞って老人を睨み付けた。
「……嫌だ」
「何だと」
相手の顔が険しくなる。
「吾輩と勝負して、勝ったらプレゼントを獲得。逆に負けたら妹を差し出す。これは既に約束した事だろう?」
そんな約束知ったことか。子供を差し置いて、父が勝手に交わした約束ではないか。
「いいか、小僧。望みを叶えるにはそれ相応の対価とリスクが必要なのだ。それでも自分の我が儘を押し通すと言うなら、吾輩を力ずくで納得させるしかないぞ」
そう言って〈サンタクロース〉が構えた。子供が相手でも容赦しないつもりらしい。
どうする? 清正は鼓動が跳ね上がるのを感じた。今、自分が闘ったとしても数秒で負けてしまう。そうなった時、愛する妹を誰が守るというのか。
脆弱な自分が不甲斐ない。今のままでは。そう、今のままでは――
その時、清正の脳裏に一つの考えが閃いた。これは有る意味、賭けでもある。その場しのぎに過ぎないかもしれない。だがそれでも、言わないよりはましに思えた。
「来年だ!」
「ほう?」
老人が嬉しそうな顔をした。こちらの意図を汲み取ったらしい。
「来年……僕が、闘う。僕が勝ったら、その時は」
一言一言が、自分の身体にのし掛かってくる。その重みで、危うい橋が崩れていきそうな気さえした。
すると。
老人が大声で笑い出した。
「なるほど、楽しみは先延ばしというわけか……まあ、よかろう」
意外にもあっさりと、相手は清正の言い分を認めた。
「では、来年この日、この時刻、この場所で逢おうぞ」
背を向ける〈サンタクロース〉。歩く先には、紅いタンクに〈To-NA改〉と書かれたハーレーが駐まっている。彼は大型バイクに跨ると、エンジンをかけた。そして去り際、こう言い残したのだった。
「我が名は蔵臼惨多(クラウス サンタ)。吾輩は逃げも隠れもせん! 小僧、来年のクリスマスを楽しみにしておるぞ!!」
『栗須磨町~、栗須磨町~。お降りの際は――』
清正はバスを降り、久しく忘れていた故郷の空気を吸い込んだ。
季節は真冬とあって、身を切るような冷気が漂っている。バス停の周りには例年通り雪が積もり、見渡す限りの平原が続いていた。夏の頃は田園風景の広がる田舎町だが、今は何もかもが雪で覆われていた。
車の轍(わだち)を辿りながら、実家へ向かう。武者修行の旅に出る為、一年前に飛び出した我が家だ。昨年のクリスマス以降、実家は十一歳になる妹が一人で暮らしている。深手を負った父は地元の病院に入院していたはずだが、僅か一週間後「地上最強の生物に、俺はなる!」とのたまって失踪したらしい。きっと父は、自分を鍛え直す旅に出たのだろう。昨年のクリスマスに味わった敗北は、「強さこそ全て」と信じる父にとって忘れる事のできない屈辱だったろうから。
また、清正にとっても、昨年のクリスマスは忘れられない出来事になっていた。
昨年のクリスマス・イヴ。夜も更けてきた頃、町に突然『奴』――蔵臼惨多が現れた。彼は「勝ったらプレゼントをやる、負けたら幼女を差し出せ」という条件を掲げて、町じゅうの人々に勝負を持ちかけた。当然、これに応じる親は居なかったが、中には例外がいた。その人こそ清正の父、貴光だったのである。
父は、生まれてこのかた働いた事がない。それは全て、地上最強の男になるべく格闘技の修練に心血を注いできたからだった。家に金を入れず、修行の為に家を空ける事もしばしば。妻に愛想を尽かされ別居生活が始まっても、父は自分が信じた道を突き進む男だった。そんな父だったが、一応親としての自覚もあったのだろう。自分の得意分野を生かし、子供達にクリスマスプレゼントを与えたいという願いから、前回の勝負に挑んだのだ。
しかしながら、結局父は負けた。となると今度は、可愛い妹が連れ去られてしまう。そこに待ったを掛けたのが、当時の清正だったのである。
「……親父。『俺』、絶対に勝つよ」
清正は拳を握りしめた。この一年間、死にもの狂いで修行してきたおかげで、今ではあの男と対等にやりあえるだけの実力が備わったと自負している。かつて同級生の誰からも相手にされず、自信を失いかけていた自分を思うと、まるで別人に生まれ変わったような気がした。
実際、清正の風貌は驚くほど様変わりしていた。薄っぺらだった胸板には分厚い筋肉が付き、枯れ木のようだった腕も丸太さながらにボリュームアップしている。修行期間が成長期と重なった事もあって、背も著しく伸び、今や清正は蔵臼に匹敵するほどの体格になっていた。加えて、髪とヒゲは伸び放題、目はぎらぎらと光っているから、その外見は野獣と表現していいかもしれない。
さて、歩いているうちに一軒家が見えてきた。瓦張りの典型的な日本家屋、これが清正の実家である。外観は一年前に比べてほとんど変わっていないが、不思議な事にバリケードが築かれ、有刺鉄線まで張り巡らせてある。自分が家出していた間に何があったのか気になるところだが、まさか実家に入れない事はないだろう。
清正は玄関に向かって歩みを進めた。
爆発した。
(な、何ぃぃぃッ!?)
突如、足元で発生した爆発によって、清正は天高く打ち上げられた。なぜ実家の玄関先に地雷が仕掛けてあったのか解らない。
考えている間に、地面が近づいてきた。清正は顔面から不時着し、一瞬、意識が朦朧となる。
その時、視界の端に小さな影が現れた。
「……こぉの、変態ぃ! まさかこのタイミングで来るとは、思ってもみなかったですぅぅぅぅっ!!」
小さな影が、何かを構えた。ぼんやりと見えるそれは、銃の形をしている。
じゃきん、がしゃん、ずどん。
「ぐはっ!?」
撃たれた。ヘヴィ級ボクサーのストレートに匹敵する威力がある。それを脇腹に叩き込まれたものだから、清正はたまらず呻き声を上げた。
「このっ、このっ、このぉっ!」
相手は容赦なく撃ち続ける。ラバーボール弾なのがせめてもの救いだが、いずれにせよこのままでは死んでしまう。清正は手を挙げて制止を求めた。
「や、やめ――」
「うるさいです! 変態は黙って死になさいッ!!」
この声は、妹のナコだ。あの心優しい妹が、何故こんなことを? 血を分けた実の妹が、その手で兄を葬り去ろうというのか。しかしどうして!?
堂々巡りする思考。やがて薄れ行く意識の中で、清正は一つの結論に行き着いた。
――ああそうか。自分はあの憎き蔵臼に間違われたのだろうな、と。
【完?】
「……あ、あれ? もしかしてアニー?」
『アニー』とは、年末に行われる感動系ミュージカルの事ではない。ナコは、兄である清正をいつもそう呼ぶのだ。
「あ、ああ……」
清正はふらふらと立ち上がり、妹と向き合った。
十一歳になる妹は、実年齢よりも更に幼く見える。背は小さいし、幼児体型だし、大きな目をした童顔がその事に拍車を掛けていた。いつもは花のような笑顔をした可愛らしい娘なのだが、今は戸惑いの表情を隠せないでいる。
「え、えと……ごめんなさい……」
消え入るような声で、ナコが謝った。申し訳なさそうに顔を俯かせ、もじもじしている。後ろに隠した大振りの銃が、やけにアンバランスだった。
「あの、あのっ……間違えたわけじゃなくてですね……」
訊かれもしないのに言い訳を始める妹。間違えた以外の何ものでもないのだが、必死に取り繕おうとしているのが解る。
そんな彼女を見て、清正は「可哀想に」と思った。
きっとナコは、この一年間、蔵臼の影に怯えて生活してきたのだろう。だから自宅に厳重なセキュリティを施し、自己防衛の為の武器まで用意していた。朗らかな性格だった彼女がここまでしているのだから、その恐怖は想像を絶するものに違いない。そう考えると、ナコの蛮行も許せる気がした。
清正はしゃがみ込むと、カチューシャをしたナコの頭に手を載せた。
「ただいま」
満面の笑み。これで少しでも彼女の心が落ち着けばいいのだが。
「う、うん……」
ナコはばつが悪そうに頷いた。自分のした事に負い目を感じているらしく、兄と目を合わせようともしない。まったく、兄は全然気にしていないというのに。こんな妹だから、守ってやりたくなってしまうのだ。
「とにかく……おかえりなさいです」
鈴の鳴るような声で言うと、ナコは清正を家の中に招き入れたのだった。
家の中は模様替えされていた。
レース生地のカーテンや天蓋のあるベッド、カーペットに至ってはピンク色のハート型である。一人暮らしなのをいいことに、ナコがすっかり自分好みの色に染めてしまったらしい。模様替えの費用や生活費はどうやって捻出したのか尋ねると、ナコは「ブログの広告収入があったから」と説明した。頼るべき両親が不在だったにも関わらず、彼女は彼女なりに逞しく生きていたようだ。
「インターネットって、便利なのですよー」
と言いながら、ナコが料理を運んできた。今はネットショッピングで生鮮食品が手に入る時代だから、たかだか十一歳の幼女でも知識を身に付ければ、一人で生きていくのは難しい事ではないらしい。
「……ああ、そうだな」
清正は、暇つぶしに読んでいた本から顔を上げた。ちなみにその本は、〈賢いオンナの処世術〉というタイトルで、内容はキャリアウーマン向けの指南書だった。この歳にしてナコは、一人で生きていこうと決心しているらしい。清正は妹の逞しさに舌を巻きながらも、兄としては一抹の寂しさを感じる。
「さ、さ、食べるですよ」
ナコがテーブルに置いた料理を勧めてくる。料理は肉や魚を中心に、高カロリーのものばかりだった。今夜の決戦に向けて精力を付けてね、という妹なりの気遣いなのだろう。
じゃあ遠慮なく、と清正は両手を合わせる。食べてみると、これがなかなか美味しい。久方ぶりの人間らしい食事だったので、清正はあっという間に平らげてしまった。決戦まではあと四時間もあるから、休憩する時間は充分にある。
「さ、今度は肩をもみもみするですよ。ほら、こっち座って」
ナコがソファをぽんぽん叩く。言われた通り、清正はソファに座る。すると妹は、「うんしょ」と言って踏み台を持ってきた。そのまま清正の背後に置き、彼女が踏み台に乗る。
「……前むいて」
清正が首を捻ってナコの動きを見ていると、彼女は何故か視線を外した。顔を赤らめているから、「これはひょっとしたら照れているのか?」なんて想像をしてしまう。よく考えてみれば、暖房が効いているからかもしれないのだが、それにしたって目をそらす理由が解らない。
……まあいい。何かしら、深淵な理由があるのだろう。
「はいはい」
一人で勝手に納得した清正は、大人しく前を向く。すると間もなく、ナコの細い指が肩に触れた。もみじのような小さい手が、一生懸命に肩の筋肉をほぐそうとしている。後頭部に、妹の吐息を感じた。
暫く、無言の時が続く。清正が気まずさを感じ始めた頃、ナコが口を開いた。
「……アニー、この一年はどうでしたか?」
おそるおそる、といった様子でナコが訊いてきた。たった一年、されど一年。兄妹が離ればなれになっていたのだから、妹も寂しかったのだろう。
「苦しかったよ」
これは本音だった。虚弱体質だった自分が充分な戦闘力を身に付けるには、まず基礎体力を向上させるところから始めなければならなかった。初めの頃は、急激な運動に身体が悲鳴を上げ、丸二日間動けなくなる事もあった。自分が死ぬかもしれないと思った事もあったし、立ち上がるのを止めてしまおうかと考えた事もあった。
清正の本音を聞いて、ナコは黙り込んだ。自分を守る為に兄が厳しい修行をしてきたのだ、その事を申し訳なく思っているのかもしれない。
「……でも、ナコの事を想えばどうってことなかったさ」
などと、爽やか系の台詞でフォローしてみる。妹は、こんな兄でも頼ってくれている。さっきの料理だって、今こうして肩を揉んでくれている事だって、全ては兄の勝利に貢献する為なのだ。妹の心遣いを無駄にしてはいけない。
ナコの手が止まった。肩に意識を集中させると、彼女の震えが伝わってくる。
「どうした?」
「アニー……」
小鳥がさえずるような声。しかしその鳴き声には、楽しさが感じられない。
途端、がばっと抱きしめられた。ナコが清正の背後から、首に両腕を回す形で。
「ナコは怖いのです……」
今にも泣きそうな声だった。いくら生活能力が高いとはいえ、妹はまだ十一歳。怖くて、心細くて仕方なかったのだろう。
と、そこで気付いた。
妹の膨らみかけの胸が、背中に当たっている。正確に言えば僧帽筋。更に細かく説明すると、背骨から両側五センチ圏内に。
いつの間にここまで成長したのか、初めてのブラはどうしたらいいのか、ぽっこりお腹はまだ健在なのか……と、どうでもいいことを考えていた自分に気付き、清正はかぶりを振った。そしてナコの小さな手に、そっと触れた。
「大丈夫だ、俺は絶対に勝つ」
背中越しに勝利宣言。今、妹はどんな顔をしているのだろう。
「本当ですか?」
と言って、ナコは手を引っ込めた。ぺちぺちと、汚れを払っているような音が聞こえたものの、多分それは思い過ごしだろう。
「ああ、本当だ。だからナコ、今のうちに欲しいものを教えてくれるかい」
蔵臼に勝てばプレゼントが手に入る。確か昨年には「何でもくれてやる」と言っていたから、どんな物でもOKなはずだ。
すると妹は清正から離れ、けろっとした声でこう言ったのだった。
「サマンサタバサのバッグ!」
マッサージの後は風呂。湯船に浸かっているだけで、長旅の疲れが取れていくようだった。
「ああは言ったものの……」
風呂場の天井を見上げて、清正はそう呟いた。いや、先程は妹を前に強がってみたわけではない。勝てる見込みは、間違いなくある。
ただ、気がかりが二つばかり。第一に、肉体改造を中心にやってきたせいで戦闘のノウハウがそれほど身についていない事。まあそこはパワーとスピードで補えるとして、第二の問題がより重要だ。というのは、もう少しで踏み込めそうな領域に辿り着けなかったからである。
自分でも説明するのが難しいのだが、きっとあれは『悟り』に近いものだったと思う。肉体をいじめ続けた先に、ふっと何かが解る。あれはそういう類のものだ。その境地に至っていれば、今こうして不安を感じる事も無かっただろう。
とはいえ、体力的には劣っていないはずだ。これから臨む闘いは、言ってしまえばただの喧嘩。自分の体力と勝利に賭ける情熱が相手を凌駕した時、勝利の女神は微笑んでくれるに違いない。
その点、勝利に賭ける情熱は充分だ。何せ、自分はナコを守らなければならない。かつての自分は、妹に頼ってばかりだった。彼女の「アニーはやれば出来る子なんですよ」という言葉に何度も勇気づけられていた。そんな妹を、あの憎き蔵臼に渡すわけにはいかない。
そうだ、自分は妹を――いや、ナコを愛している。家族愛とか兄妹愛とかそういうものではなく、一人の女性として。この闘いに勝利したら、彼女に想いを打ち明けよう。そうしたら健全な交際をしよう。子供を作るなんて、もってのほか。二人の関係はプラトニックでなければならない。さっきのように肌と肌が触れあった瞬間、正直いえば胸が高鳴った。抱きしめてしまいたいと思った。だけど自分はまだ、彼女に想いを伝えていない。告白もしないで行為に及ぶのはマナー違反だ。自分は正々堂々、彼女と向き合いたいのだ。
「よし……!」
士気が上がってきた。今ならきっと〈ゴッドハンド・マス大山〉にも勝てるはずだ。
と、その時。
風呂場の外から、エンジン音が聞こえてきた。これは多分、大型バイクのもの。エンジンが停止したかと思うと、今度は足音がこちらへ近づいてくる。
まさか、奴が来たのか!?
清正はその場で立ち上がり、風呂場の窓を開ける。するとそこには――
ひげ面の老人が居た。
「やはりあんたか……!」
風呂場の外に立っていたのは、蔵臼だった。余裕の笑みを浮かべているのが癪に障る。
「ほぉ、お前があの時の小僧か。見違えるようだ」
これは嬉しい誤算だ、とでも言いたげな蔵臼。それを見て、清正は僅かな誇りを感じた。そこで減らず口を叩いてやる。
「ああ、あんたのせいで俺は地獄を見てきたんだぜ」
「結構、結構。それでなくては倒し甲斐が無いというもの、せいぜい吾輩を楽しませるがよい」
「吠え面かくなよ」
「その言葉、そっくりそのまま返してやろう」
ああ言えばこう言う。二人の間の空気がぐにゃりと歪んでいくようだった。
蔵臼は目を爛々と光らせ、こう言ってきた。
「さあ、早速始めようぞ。吾輩はこの日を待ちわびておった。危うく『慌てん坊のサンタクロース』になってしまうところだったぞ!」
暴れん坊のサンタクロースが何を言う、そう言いかけたが清正は言葉を飲み込んだ。相手も自分も、既に心は決まっている。目の前の敵をぶちのめしたくて仕方ないのだ。喩えるなら、自分達は鎖に繋がれた野犬(ランペイジ)。解き放たれるのを今か今かと待ち構えている。
「いいだろう、身体もちょうど温まってきたところだ」
そう言って、清正は湯船から出る。風呂場の出入口に向かい脱衣所へ出ようとした頃、ふと気付いた事があった。
「……ところであんた、何で風呂場の裏に来た」
窓の外で、蔵臼が不敵な笑みを浮かべた。
「知れたことよ。幼女の入浴を拝もうと思ってな」
決戦の場は、実家の裏手にある広場。昨年と同じように、白い雪が降っていた。
清正はジーンズにダウンジャケットを着て闘いに臨む。急激な成長を遂げた為、修行期間に着ていた服しか着られなくなっていたのだ。
対して蔵臼は、相変わらず上半身裸のままである。着衣はサンタ帽と長ズボンのみ。ブーツすら履いておらず、裸足のまま雪原に立っていた。一見すれば凍死しそうな格好なのだが、当の本人は平然としている。それだけ、血がたぎっているという事なのだろう。
「では、ルール確認だ。時間無制限一本勝負、最後まで立っていた者の勝ちとする。武器の使用は認めない、あくまで己の肉体を使って闘え。ただし、噛み付き・金的は自由、とにかく何でもアリ――これで異存はないな」
蔵臼の説明を聞いて、清正は無言で頷いた。
「それから、この闘いにお前が勝てばプレゼントをくれてやる。逆に、吾輩が勝った時は――」
言いかけて、蔵臼はナコの方を見た。彼女はニット帽を被り、ダッフルコートを着込んでいる。首にはマフラーを巻き、防寒対策は万全だ。その代わり、顔は酷く強張っている。今夜、自分の運命が決まるのだから、彼女は気が気でならないようだった。
「妹を貰うぞ」
その台詞が、ずしんと腹に響く。断るという選択肢もあったのだが、昨年に交わした約束があった手前、逃げるわけにもいかない。少しの間を置いて、清正は頷いた。
「ちょ……」
ナコが口を挟もうとしたが、彼女は頭を横に振って俯いた。何かブツブツ呟いているから、「兄を信じるしかない」という感じの事を自分に言い聞かせているのだろう。そんな妹を見て不憫に思った清正は、こう尋ねた。
「一つ教えてくれ。なぜあんたは妹を――幼女を連れて行きたいんだ」
目の前の老人は、唇の片端を吊り上げる。心底嬉しそうな目をして、彼は答えた。
「決まっているだろう。サンタさんは『子供が好き』だからな!」
『子供が好き』の辺りに、並ならぬ情熱を感じる。なるほど、奴も充分な動機を持っているという訳か。
「幼女はいいぞ。特に、なだらかな胸から腹にかけてのラインが芸術的ではないか! 美幼女であるなら尚よしだ。純粋無垢な子供が恥ずかしそうに顔を赤らめるところなどは、世界遺産にしてもいいと吾輩は考えておる!!」
「『恥ずかしそうに』……だと! あんた、妹に何をさせる気だッ!!」
頭に血が上り、清正は思わず叫んだ。
「ふふふ……それは言えんなァ。『大人の事情』というやつだ」
「『オトナの情事』だと…………貴ィィッ様ァァァァッ!」
怒りに我を忘れた清正は、ゴングを待たずに飛び出した。拳を堅く握りしめ、嫌らしい笑みを浮かべる蔵臼の顔面を――
「ふむ」
しかし、あっさりと躱されてしまう。
「どうした、そんなテレフォンパンチでは『避けて下さい』と言っているようなものだぞ」
「黙れ!」
攻撃に関して自分は素人同然だ。そこは認めるしかないだろう。だからと言って、勝敗が決まるわけでもないのだから、あとは自分の力を信じて闘うしかない。
「はっ!」
反対の手で、もう一度顔面を。その瞬間、蔵臼が僅かに動いた。
衝撃。清正の脇腹に膝蹴りが深々と突き刺さる。
「カウンターにすら気付かんとは。とんだ期待外れよ」
蔵臼は両手を組んだまま、軽やかなステップを踏み始めた。両手を使わずに足技だけで闘うつもりなのだろうか。
だが、清正にとってこれは望むところであった。相手が実力差を意識して調子づいてくれれば、それだけ『秘策』を出しやすくなる。
「ぐふっ……」
腹を押さえて後退。攻撃が効いたように見せかければ、相手は更に隙を見せるはずだ。
「なんだ、その筋肉は見せかけか? ならば、こちらから行くぞ」
地を蹴り、蔵臼が間合いを詰めてきた。体格の割に速い。
(スピード勝負なら!)
清正は横に跳んだ。肉体改造の際に重視したのは次の二つ。一つは耐久力、もう一つは脚力だ。この脚力こそ、自分の秘策を生かす唯一の手段だと思ったからだ。
最短距離で近づいてくる蔵臼、途端、右脚が唸った。これも速い。その威力で、降ってきた雪が舞い散るほどだった。
清正はスウェイバックでこれを避ける。すると第二波が来た。
「甘い!」
返す刀ならぬ『返す脚』。蔵臼は空振りした右脚を引き戻すと、清正のみぞおち目がけて横蹴りを放ってきた。
命中。腰を引いて威力を軽減していなければ、間違いなく貫かれていただろう。蔵臼惨多という男、言動は変態そのものだが、格闘技の実力は折り紙付きだ。素人でもその事が痛いほどによく分かる。
「ほぅ、威力を殺したか。防御はそれなりに出来るようだ」
当たり前だ、と清正は言いそうになった。全ては来るべき一瞬の為、それまでには何としてでも倒れるわけにはいかないのだ。
「ならば、ギアを上げるぞォ!」
言い終わらないうちに、老人が走った。いや、老人と言うには異常なスピード。清正が目で追う間もなく、右の太腿に鋭い一撃が加えられた。
「ぐっ……!?」
これは効いた。膝のやや上、筋肉の隙間と隙間を狙ったピンポイントのローキックだ。清正はバランスを崩し、その場に膝を付く。
「まだまだァ!」
頭が下がったところへ、無情の回し蹴り。こめかみを痛打され、意識を根こそぎ持っていかれそうになる。清正はたまらず、両腕で頭を庇った。
「その程度のガード、切り裂いてくれるわ!」
右から、左から。蔵臼の蹴りが往復する。一発一発が重く、少し気が緩めば腕を下ろしてしまいそうだ。そうなったら最後、頭部に集中砲火を受けてしまう。
(まだか……!)
清正はまばたきするのも忘れて、相手の動きをつぶさに観察した。蔵臼は喜悦に満ちた声を上げ、容赦ない蹴りを放っている。そろそろ『あの技』が来てもいい頃だ。
「がっ!?」
誘いを掛ける為、清正は大袈裟に呻いた。蔵臼が、これを好機と勘違いしてくれればいいのだが。
「ふッ」
蔵臼が息を吐いた。大技を出す前の息継ぎ。一歩下がると、彼は右手を鉤爪の形にした。
(――来る!)
直感した。清正は頭を庇ったまま立ち上がり、腹をがら空きにする。
「必ィィッ殺! 《爺射刺・喰捨人》ォォォオオオッ!!」
蔵臼が吼えた。神の名に似た、彼の必殺技が、今、向かってくる!
神速の踏み込みから、右手を伸ばしてくる蔵臼。狙いは清正の腹部。予想通りだ。
清正は意識を集中させた。インパクトの瞬間を狙う。今こそ、修行の成果を見せる時だ。
蔵臼の右手が、まさに清正の胴体を捕らえようかという時。
清正は身体を半身にしながら、左斜め前へ跳ぶ。そして――
「――返しッ!」
鍛え上げた右腕で、蔵臼の喉に、快心の一撃を叩き込んだ。
「ぐっぼぉぉぉぉッ!?」
クリーンヒット。蔵臼は空中で一回転半すると、背中から大地に叩き付けられた。積もった雪が舞い上がり、月明かりを受けてきらきらと光る。
「やった……!」
清正は拳を握りしめた。
自分の右腕には、確かな手応え。これぞ一年間模索してきた唯一の秘策、《爺射刺・喰捨人返し》だった。
《爺射刺・喰捨人》は、『縮地』とも言える速さで間合いを詰め、鉤爪の形にした手を敵の腹に叩き込んだ後、胃の辺りを掴んでねじ込み、最後に相手を空高く打ち上げる技だ。父が犠牲になったおかげで技の正体が分かり、正体が分かれば対策も立てやすかった。考え抜いた結果、清正が行き着いた答えとは、相手の突進力を逆に利用したラリアートによる反撃だったのだ。
反撃技を成功させる為には、己の脚力と集中力を鍛える必要があった。その為に清正が編み出した修行法は、突進してくるものをひたすらに避けるというもの。イノシシに始まり、次は斜面を転がってくる岩、そして自動車……という具合に、レベルを上げれば上げるほど命の危険は高まる。その中で、驚異的な集中力を養い、万全を期した。
その結果がこれである。清正は、言い知れない歓喜を覚えた。
「やった! やったぞ、ナコ!!」
兄はお前を守ったぞ! そう言ってやりたかった。一年間に亘る恐怖が、今終わったのだと伝えたかった。清正は居ても立ってもいられず、ナコに向かって走り出した。あとは彼女に想いを伝え、二人抱き合ってハッピーエンド。これ以上の締めは考えられない。
――ところが。
「勝ち鬨を上げるのは、まだ早いぞ」
背後から声がした。振り向くと、蔵臼がネックスプリングで起き上がるところだった。首を左右に動かし、感触を確かめている。まるで、肩こりが取れたとでも言いたげだ。
「今のは、なかなか良かった。まさか吾輩の必殺技を破るとはな」
「……な、何度でも破ってやるさ」
動揺を見透かされたくなかったから、清正は努めて強気に発言した。
「それはいい心構えだ。しかしな、吾輩の必殺技が一つだけだと思うか?」
腕組みして言う蔵臼。余裕に満ちた表情からして、単なるハッタリでない事は明らかだった。
「だったらッ!」
清正は走った。先程の一撃によるダメージが抜けきっていないうちに、駄目押しの一発を加えれば済む話だ。
打撃ではなく、今度は組み技で。岩を抱きかかえて山道を走り、それによって培った腕力は伊達ではない。
「……愚かな」
清正が両手を広げて突進するのに対し、蔵臼が取った行動は僅かにしゃがむだけ。その程度で何が出来るというのか。
「うわぁぁああああっ!」
「究極奥義、《滅離威・苦死身増(メリィ・クルシミマス)》……」
呟くと同時に、蔵臼の身体が伸び上がる。握られた拳が清正のアゴを撃ち抜いたかと思うと、暴風雨のようなラッシュが始まった。
清正の身体が伸びきったところへ、機関銃のごとき連打。腹を、胸を、顔面を、全てが正確に急所を狙ってくる。
「……! ……!!」
声が出ない。何発打ち込まれたのか分からない。自分が立っているのかすら分からない。分かるのは、打撃を加えられる度に苦痛が増していく事だけだった。
どれだけの時間、自分は打たれ続けていたのだろう。そう思った矢先、蔵臼が奇声を発した。
「ハイヤァッ!」
後ろ蹴り。これをまともに喰らい、清正は十メートル近く吹き飛ばされた。雪原をもんどりうって転がり、木に激突したことでようやく止まった。
「く……そ……」
悪態を吐くのが精一杯だった。次第に意識が遠のく。清正は暗い闇の縁へ引きずり込まれていくような気がした。
清正は、自分が引きこもりになったきっかけを思い出していた。
高校一年の夏、放課後にこんな出来事があった。
忘れ物を取りに行く為に教室へ戻ったところ、残っていたらしい生徒達が、清正の陰口を叩いていたのだ。
――二瓶って、『普通』だよな。
普通。目立ちたい盛りの少年に、この一言は残酷だった。当時の清正は、クラスの人気者として振る舞っていたつもりだったが、他の生徒はそう感じていなかったらしい。
清正が教室の外にいる事も知らないで、生徒達はこう話していた。
――そうそう。何やっても平凡だしな。
――けどさ、その割にはとっつきにくくねぇ?
――だよなー。「自分は凄い」って勘違いしてるっていうかさ。
――それで、あんなに自信満々なわけ? ああいうのをウザキャラとか言うんかね。
――要するにガキなんだよ。なんか左手に包帯巻いてるし。『普通』の割には、どっか変っつーか。
――もう話すのやめようぜ。あんな奴、相手にするこたねぇよ。放っときゃいいんだって。
(分かってたさ……)
当時の事を思い出しながら、清正は胸の内で呟いた。高校に入って二ヶ月が過ぎた頃、自分が特別な存在でない事には薄々気付き始めていた。勉強にしろ運動にしろ、自分よりも秀でた生徒はごまんといた。それでも自分には能力があると見せかけていなければ、いつかいじめられると思っていた。つまり、自分が格下に見られる事が怖かったのだ。
その日以来、清正は同学年の誰からも相手にされなくなっていた。今までと同じように振る舞っても、集団無視は毎日のように続く。暴力を振るわれた事は無いが、それ以上に無関心でいられる事のほうが辛かった。
孤高ではなく孤立。自分が居ても居なくても他の連中は困らない。そう自覚した時、清正が選択したのは逃げる事だった。自分が凡人だと思い知らされ、それでも些細なプライドを保つ為に自ら閉じこもった。それが自分の心を腐らせていく原因だと知りもしないで。
クラスメイトに馬鹿にされ、父親は「気合いで解決しろ」としか言わなかったから、清正は妹だけを頼りに生きてきた。今回に限って、大切な妹を守る為に立ち上がったものの、結局は凡人らしい結末。こうなるともう、プライドなんて跡形もない。ただ卑屈に、自分を嘲る事しか出来なくなってしまう。
(すまない、ナコ。兄ちゃんはやっぱり、駄目な奴だ……)
清正は暗い世界で、一人むせび泣くのだった。
「――ひぎゃぁぁぁぁぁああああああ!」
悲鳴が聞こえた。
自分が昏睡していた事に気付き、清正は慌てて飛び起きる。
「おーよしよし。そんなに嫌がらんでもよいぞ。それとも『嫌よ嫌よも好きのうち』というやつかのぉ?」
「嫌ぁぁぁああああ! このおじちゃん、洗ってないタオルの臭いがすりゅぅぅぅぅぅッ!!」
見れば、蔵臼がナコに頬ずりしているところだった。清正が倒れたので、勝利したと思っているようだ。
「ま、待て!」
清正は声を振り絞った。妹を助けたい、その一心で。
「む? お前、まだ生きておったのか。見上げた耐久力よ」
「うるさい、勝負はまだ終わっていないぞ……!」
清正の切実な台詞を、蔵臼は鼻で嗤う。
「相手してやっても構わんが、結果は同じであろう?」
痛烈な一言だった。確かに、秘策が役に立たなくなってしまえば、今の自分に勝てる道理は万に一つもない。まして自分は格闘の素人だから、このまま闘ってもジリ貧になるのは目に見えている。
清正は歯を食いしばった。
一年間、必死に修行をしてきたはずだった。だが、結局自分はあの男に勝てない。一体、自分は何の為に己を鍛えてきたのか。考えれば考えるほど悔しさが込み上げてくる。
「ほらほーら、高い高ーい」
「って、ぱんつ見ないで下さいぃぃぃぃっ!」
ナコが両手でスカートの端を押さえながら、悲痛な叫び声を上げている。このままでは、彼女に何をされるか分からない。助けてやりたいと思う。しかし実力が足りない。所詮、自分は凡人。最早何をしても同じに思えてくる。
清正が打ちひしがれていると、突然、胴間声が響いた。
「――立てェイ、清正! 貴様、それでも俺の息子かァッ!!」
聞き覚えのある声だった。一年ぶりに聞くこの声は――父親のものだ。
「親父!?」
顔を上げると、父が仁王立ちしていた。相変わらずの空手着姿だったが、首には赤いマフラーを巻いている。
「帰ってきたのか、だったら……」
あいつを倒してくれ、そう言い繋ごうとすると、父は首を横に振った。
「ならん! いいか、清正。男たるもの、己が闘うと決めたら最後まで闘え。この闘いはお前が望んだものだ。いかに父親といえども、立ち入る事は許されんのだ!!」
父らしい台詞だ。しかし闘ったとしても、負けると分かっている場合はどうすればいいのだろうか。
すると父は、清正の心を読んだように、うっすらと微笑んだ。
「お前に一つ、ヒントをやろう」
と言って、父は語り始めた。ヒントが一つと言う割には長い説教だったが、要約すればこんな感じだ。
――自分を信じろ、自分は特別だと言い聞かせろ。自分を完全に騙した時、嘘は真となる。
「それは……」
中学二年から高校一年にかけて、自分は特別な存在だと信じていた。ただ、幾つもの壁にぶち当たることで、自分は凡人である事を思い知らされた。
けれどもし、自分が凡人である事すら思い込みだったとしたら?
中途半端な幻想は、自信の無さを隠す為のもの。逆に、その「自分は特別」という幻想を貫いたらどうなるか。己を信じ、己を騙し通せば、それは既に幻想ではなく、『現実』となるのでは。
(やってみるか)
清正は決断した。まだ引きこもりになる前の、自信に満ち溢れていた自分を思い出す。
――俺は特別な存在だ。そんじょそこらの連中とは違う。十把一絡げの奴らと一緒にするな。俺は強い。俺は凄い。俺には秘めた力があるんだ。今はまだ目覚めていないが、きっと目覚める。俺は覚醒の時を迎えた、いわば卵だ。孵化しろ、生まれ変われ、凡人とは違うところを見せつけてやれ――
清正は妄想した。想像した。架空の世界で活躍する自分を創造した。
実は、自分は異世界〈エターナル〉から来た最強の戦士なのだ。〈エターナル〉は平和な世界だったが、ある日、邪悪なる王〈ダイモス〉(黒いマントに闇色の甲冑姿。額には捻れた角があり、その角が力の源)が降臨し、善良な人々に暴虐の限りを尽くした。敵の目的は、〈エターナル〉で語り継がれている特殊な力〈グレート・デバイス〉を手中に収める事。この力があれば全てが思い通りになるのだ。〈ダイモス〉は〈ワルプルギス〉と呼ばれる悪の軍勢を率いて王城に攻め込んだ。この世界を治める王族には〈グレート・デバイス〉の『鍵』となるべき素質があったからだ。中でも第一王女(金髪碧眼、この世のものとは思えない美貌を持ち、それでいて気丈な心の持ち主)は、『鍵』としての素質が格別だった。だから〈ダイモス〉は第一王女を攫おうとした。そこへ勇者たる自分が割って入り、悪の軍勢と戦った。一対百万の戦力差だったが、選ばれし者に敵うわけがない。自分は〈ワルプルギス〉を瞬く間に退け、謁見の間で決戦に臨んだ。さすがに敵の親玉は手強く、自分は苦戦を強いられた。〈ダイモス〉には闇を操る力があり、人間の負の感情を糧に、その力を強めているという。だから自分が弱気になると、よりいっそう攻撃の威力が増すのだった。〈ダイモス〉はこう言った。「フハハハ、貴様程度が私に敵うものか!」。疲弊した自分は膝を付いて「もう……駄目かもしれない」と挫けそうになった。するとその時、第一王女が「諦めてはいけません、諦めない心こそ〈グレート・デバイス〉を手に入れる『鍵』なのです」と言った。それで自分は傷ついた身体を奮い立たせ、敵に最後の勝負を挑んだ。戦闘終了間際、ついに自分は〈グレート・デバイス〉に目覚め、〈ダイモス〉を倒す。第一王女は解放され、自分は紳士的に彼女を抱き上げた。「貴方こそ、この世界の王に相応しい。私と結婚して下さい」と言われ、二人で熱い口づけを交わす。これにてハッピーエンド――と思いきや、〈ダイモス〉はまだ生きていた。「この世界だけでなく、全ての世界を無に帰してくれるわ!」。そう言った彼は異世界への扉をこじ開け、別の世界へ逃げ込んだ。その世界こそ、今、自分が居る世界なのだ。自分は〈ダイモス〉を追ってこの世界にやってきた。そして引き続き、魔王を倒す為に日々戦っている。〈グレート・デバイス〉に目覚めたとはいえ、この世界ではその力が通用しない。なぜなら、この世界には別の力が存在するからだ。この世界には〈グレイテスト・フォース〉なる力があり、その力を手中に収めた者は天変地異すらも自由に操れるという。ちなみに第一王女も、こちらの世界に連れてきた。愛する者を一人にしておくわけにはいかないからだ。その第一王女こそ、設定上は妹という事になっているナコである。彼女は今、仮の姿をしている(真の名は、ナコ=ヴォルフィ=ダ=エターナル)。その彼女に、〈ダイモス〉の魔手が伸びている。奪われるわけには行かない。というのも、実は、彼女の秘めたる力こそ〈グレイテスト・フォース〉だったからだ。ナコを救う事は、この世界を救う事に繋がる。すなわち、彼女を守り、この世界の滅亡を防ぐ事こそ、自分に課せられた使命なのだ。それが実現可能なのは、この自分しかいない。だから尚のこと、更に隠された力を目覚めさせる必要があるのだ――
「はぁぁぁぁっ!」
段々気持ち良くなってきた。ドーパミンとか、アドレナリンとか、エンドルフィンとか、デルフィン酸3カンオメデトウとか、何かそういう色んな分泌物がとめどなく溢れてくる。もう、耳から鼻から毛穴から漏れてしまいそうだ。
体内を、熱い血が巡っている。心臓から大動脈、毛細血管に至るまで。熱き血は活力を生み、活力は行動を生み、行動は伝説を創る。
そして、奇跡が起こった。
「覇ァ!」
清正が気合いを入れると、周りの雪が吹き飛んだ。自分を中心に竜巻が起こり、身体には青白い燐光がまとわりついている。ついに……ついに自分は、『覚醒』したのだ!
「……ほお、お前もようやくその境地に至ったか」
蔵臼が言った。声色の割には表情が硬い。
「よかろう、第二ラウンドだ。その代わり、吾輩も本気を出させて貰うぞ」
蔵臼は抱き上げていたナコを解放すると、ズボンを下ろし始めた。
「実はこの服、相当な重量があってな」
投げ捨てられたズボンは、ズシンという音を立てて地面にめり込む。これだけ重いものを身に付けていながら、ああも俊敏に動けていたとは。やはりこの男は強敵だった。
続いて蔵臼は、黒いビキニパンツにも手を掛け、
「これもウェイト代わりだが……」
と脱ぎ始める。しかしその途中で、何かを思いついたようだった。
「……いや、これぐらいのハンデは必要か。簡単に倒しては面白くない」
「へっ、それを脱がなかった事を後悔させてやるぜ」
清正は親指で鼻の頭をこすると、ファイティングポーズを取った。両脚を大きく開いたオープンスタイル。自分の中で目覚めた何かが、この構えを選択したのだ。
「強がりを。ならば吾輩は、最終奥義《甚狂地獄(ジングルヘル)》でもって、貴様を迎え撃とう」
蔵臼が両手を前に差し出した。合気道の構えに似ているが、どんな技を出してくるのか予想もつかない。
(いや……)
清正は首を左右に振った。余計な事は何も考えるな。邪念があれば、躊躇いが生じてしまう。思い切りぶつかる、それだけで充分だ。
「行くぞ!」
「応!」
大地が震える。木々が揺れる。雪は、いつの間にか止んでいた。天が、決着の時を悟ったのだ。
先に動いたのは蔵臼だった。一瞬遅れて、清正が飛び出す。
『ゥォォォオオオオオオッ!』
重なる声。相手の顔が近づく。必殺の間合いまで爪一枚。いや、皮一枚――
閃光。
辺りはまばゆい光に包まれ、隕石衝突にも似た轟音が響き渡ったのだった。
「っぐふぉぉぉぉッ!?」
一人が、宙を舞っていた。綺麗に放物線を描いて地に落ちる。最後まで立っていたのは――
清正だった。
「はぁ……はぁ……」
激しく息をつき、清正は崩れ落ちるように横たわった。今ので上着が全て吹き飛んでしまったが、不思議と寒さは感じない。むしろ、ヒートアップした身体にはちょうどいい涼しさだった。
「げはっ、がはっ!」
咳き込んでいるのは蔵臼だ。清正は身体に喝を入れ、立ち上がる。そのまま、悶え苦しんでいる老人に歩み寄った。
「立てるか」
手を差し出す。何故そんな行為をしたのか自分でも解らなかったが、そうしたほうがいいように思えたのだ。
「……」
逡巡の末、蔵臼は清正の手を取った。清正は手を引き、敗者を起こしてやる。
「お前、どうして」
問われたから、清正はこう答えた。
「闘いは終わったんだ。もう、敵も味方もないだろ。それに」
激闘を思い返す。蔵臼は、この自分と闘う事を心から楽しんでいるようだった。この自分が倒れてもとどめを刺さなかったし、父と話している間に攻撃を仕掛けてくる事もなかった。だから清正は、こう思ったのだ。
蔵臼惨多という男は、フェアプレイ精神を大切にする正統派の格闘家なのだ――と。
思った事をそのまま口にすると、蔵臼は照れ臭そうに微笑む。
「まさかフェアプレイを褒められるとはな。アブノーマルプレイが本業だというのに」
視線を逸らして頬を掻いているところを見ると、案外悪い奴ではないように思えてきた。
蔵臼は「それにしても」と付け加え、邪気の無い顔をしてこう言った。
「これほど血湧き肉躍ったのは初めてだ。お前を見て、吾輩も初心を思い出したよ。いや、実にいい闘いだった」
「そうだな」
清正は握った手に力を込めた。相手を支える為ではない、己の全てを賭けて闘った『漢』に対する友情の証しだった。
すると、蔵臼は目を伏せ、
「……実は、プレゼントが無いのだが」
と言った。目を合わせられないのは、こちらの誠意に応えられない事を恥じているからだろう。
蔵臼は、自分の力を信じていた。負ける事など、微塵も考えていなかったに違いない。今にして思えば、彼がプレゼントを用意していなかったのは当然の事。それも自負心の現れと考えれば納得のいく話だ。
「構わないさ。だって」
清正は白い歯を見せて笑った。
「この瞬間が、何ものにも代え難いプレゼントだから」
【完……?】
「――ふ・ざ・け・る・な、でぇすぅぅぅううううううううううううッ!」
じゃきん、がしゃん、ずどん。
「ぐばっ!?」
清正の頬を、ラバーボール弾が直撃した。何事かと思って弾が飛んできた方向を見ると、ナコが銃を腰だめに構えている。彼女は頬をリンゴのように染め、両目には涙を浮かべていた。
「……ッ!?」
何故だ。兄が蔵臼を倒し、妹を守り抜いたというのに。どうして彼女は怒り狂っているのか。原因が、まったく分からない。
白い息をたなびかせ、ナコがまくしたてる。
「勝手に景品にされた挙げ句プレゼント無しとかどういう事ですか! しかも臭いおっさんに頬ずりされて、ぱんつまで見られて!! ナコが何したって言うんですぅかぁぁッ!」
もう一発。今度は清正の下腹部に命中した。急所を撃たれた清正は、股間を押さえてうずくまる。この部分だけは、どうしても鍛えようが無かったのだ。
「もうこんな生活イヤー!」
乱射、乱射、乱射。
「ぐべぇ、げふっ、うげほぉ!?」
一番の被害者は蔵臼だった。気力を使い果たし、逃げる事が出来なかった為である。彼は白目を剥いて倒れると、それきり何も言わなくなった。
「――逢いたかったぞ、ナコォォォォオオオオ!」
息をつくいとまもあらばこそ。父の貴光がダイブしていた。両手を伸ばし、口はタコのように尖らせて。我が子をこの手で抱きしめ、熱烈なキスをするつもりらしい。父親として愛情表現せずにはいられなかったようだ。
「消えなさぁぁぁい! このろくでなし親父ィィィ!!」
迎撃。父はラバーボール弾と痛烈なキスをした。
「ぶちぅっ!?」
どさっ、ごろごろ……。綺麗にカウンターが決まったらしく、父はぴくりとも動かない。
「もう! やっぱり『本』に書いてあった通りでした。今後、ナコは一人で生きていきますからっ!!」
と言って、ナコは清正に背を向け、歩き出した。彼女の姿が次第に遠ざかる。
「ま、待って……」
清正が呼んでも、妹は立ち止まってくれない。その代わりというか、彼女は一冊の本を落としていった。タイトルは〈賢いオンナの処世術〉、ナコの部屋に置いてあったものだ。
強い風が吹いた。置き去りになった本のページがパラパラとめくれ、途中で止まる。開いたままのページを清正が見ると、そこにはこう書いてあった。
■賢いオンナの三箇条■
1.女の武器は極力使いましょう
2.利用出来るものはとことん利用しましょう
3.男を絶対に信用するな
【完!】