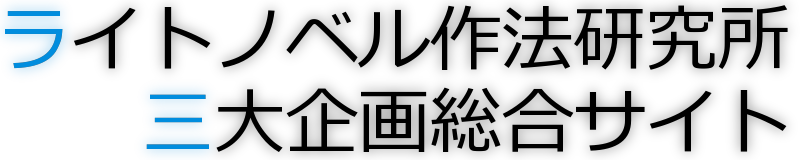2011冬祭り企画優秀作品
『あめゆきの朝』

【使用したお題】 終わりとはじまり
【一行コピー】 あめゆきとってちってった――勇気と笑顔の進軍ラッパ。それは、人生へのエール!

白。
いちめんの白。
塗りこめられてしまうかのような白い、白い朝霧。
その中を、まるで幽鬼がさまようがごとく、おぼつかない足取りで歩く千鳥。
はらはらと降る粉雪。
ひらひらと舞う蝶々。
「……あめゆじゅ」
つぶやく千鳥。
ほろり。
千鳥の目から涙がこぼれる。
きらきらと輝く水滴。
ぴたん。
千鳥の持つ陶器の椀に水滴が落ち、中を満たす水の上に波紋が広がる――。
*
「いかがでしたか?」
暗闇に慣れた目が、急に明るくなった室内に適応する前に話しかけられた。
僕は立ち上がると、目の前で卑屈な笑みを浮かべている映像監督とやらに、なんと云うべきだろうかと考えた。
真っ正直な感想を云ったら彼は怒るだろうか。それとも、完成間際だというこの映画を、僕の――原作者である僕の希望通りに作り変えてくれるのだろうか。
「は、はぁ」
僕は、曖昧に返事をした。
会議室を利用しての簡易試写会場には、五十人ほどの人たちがいて、あちこちで今見た映像について語られている。声高に聞こえるのは褒め言葉だが、ひそひそとしたやり取りの中には、否定的な発言や修正を求める声なども混じっているようだった。
「綺麗な映像に仕上がってますでしょう」
男が自慢げに云う。
僕は、どちらかと云えば不満げな顔をしていたと思うのだが、僕の顔色などどうでもいいらしい。男は、卑屈そうだが、実は尊大だというタイプらしい。
「ええ」
確かに綺麗だったさ。けれど……。
「CG……あ、CGっていうのはコンピューターグラフィックのことでして、それをですね、駆使しましてね、役者はもちろん生で撮るんですが、その生の映像をですね、加工するわけです。製作時間と予算のすべてをつぎ込んで……」
CGとはコンピューターグラフィックのことだということぐらいは知っているさ。けれど、その手法などどうでもいい。ましてやスタッフが徹夜続きだとか薄給だとかいうのは、一体僕に何の関係があるっていうんだ。それよりももっと大切なこと、一番に云うべきことがあるだろうに――。
キンキンとした耳障りな声で、せわしなくべらべらとしゃべり続けているねずみ男のような細くてとがった顔立ちの男の顔を、僕はただ呆然と眺めていた。
それでも、この男があの綺麗な、美しい映像を作り出していたのだ。美しい映像そのものを否定する気はなかった。――けれども。
果てしなく薄っぺらに見えるこの男と同じように、僕もまた薄っぺらなのだ。きっと。
(心象風景のみで綴られる物語は、単に綺麗な言葉の羅列で現実感に欠ける)
僕は、ふと、そんな書評を思い出し、この映画もまた、同じように評されるのだろうと思った。
今見せられた映像の、どこに現実感があったというのか。
人気のある可愛い女の子を連れてきて、CGとやらを駆使して、物語など二の次、三の次。ただ綺麗な映像に美しい音楽がついて、まるでプロモーションビデオのような映像。
――なるほど、原作に忠実で結構なことじゃないか。
いいようの無い思いがひたひたと胸の奥に積もり、お粗末な茶番劇にでも借り出されてしまったような心地になってきていた。
――いや、わかっていたはずじゃないか。
この話の始まりからして茶番劇でしかなかったのだから。
思い返せば、数年前に韓国発の恋愛ドラマが流行ったことがきっかけだろう。その後、ベストセラーの恋愛小説や漫画が次々とテレビドラマや映画化され話題となった。ブームにのって雑誌では恋愛小説、それも悲恋だったり不治の病を扱う小説の特集が組まれた。僕が七年前に書いた『あめゆき』が掘り起こされ、なぜか一躍人気となってしまったのは去年のことだ。
僕はといえば『あめゆき』で新人賞をとったものの、決して高評価ばかりでなく、受賞後に二作目を出すも鳴かず飛ばずで筆も進まず。すでに小説家として暮らすよりも、会計事務所の会計士としての生活のほうが身に染み付いていた。
突然の人気にいちばん驚いていたのは僕自身だったろう。
舞い込むようになった取材や原稿依頼のほかに、はじめに映画化をといってきたのは誰だったろうか。
その時は、とんでもないと、僕は即答した。
そう、やはりとんでもないことだったのだ。
やはり、僕は否やと唱え続ければよかったのだ。
僕は、何を期待していたのだろう。
先程から、曖昧な返事しかしない不熱心な相手に、ためらいも見せずに自分の作り上げた映像がどれだけ素晴らしいかを、延々と力説しているこの目の前の男に、「期待はずれ」だといえる程の何かを期待した事があっただろうか。
――そうだ、僕はこの男に期待していたわけじゃない。
この男から逃れたくて、僕は視線を泳がせた。そして、申し訳なさそうにこちらをみつめている映画のプロデューサーである栗山葉子さんを見つけた。僕はそう、彼女に期待し、彼女に託したのだ。
僕が目線でSOSを出すと、彼女は軽く頭を下げ、他のスタッフと談笑していた少女をひとり連れて、こちらに寄ってきた。
「監督、よろしいかしら。川原先生にまいちゃんを紹介したいのですけれど」
「あ、ああ、そうだね」
男はまだ話したりないといった顔だったが、このはきはきとした女プロデューサーのことが苦手なのかもしれない、抵抗することなく場を譲る。そして、次のターゲットと定めたのか、楽曲提供しているミュージシャンのところに愛想よく寄っていったが、自慢を始めるより早く「音楽とあわない箇所が……」などといわれている。
つい見送ってしまった僕らだったが、やがて、我に返るようにして顔を見合わせ、微笑――いや、苦笑か――した。
「申し訳ありません」
それが栗山さんの第一声だった。
そうして深々と頭を下げる彼女に、僕も驚いたし、連れてこられた少女も驚いていていた。
まいちゃんこと月城麻衣子は、少女ばかりのアイドルグループに所属している。まだ、十五か十六で、高校生にはなっていたはずだ。ほんのわずかの間にも表情をくるくると変え、僕と栗山さんを交互に見ている。連れてこられた時は和やかだと思っていただろう僕と栗山さんの仲が、険悪なのかもしれないと顔を引き締め、そして場を取り繕おうといっそうの笑顔に……そんな変化だろうか。百面相の後の満面の笑みは、先ほどまでの映像で、千鳥と名乗っていた同じ子とは思えない。
普段テレビで観る舞台衣装からすればおとなしいが、リボンとレースに縁どられた鮮やかで愛らしいミニのワンピースに大きめの髪飾りをつけている。華やかな衣装に負けない生気あふれる瞳をきらきらとさせて、好奇心いっぱいといった様子は溌剌としていて、千鳥の持つ儚さなど微塵もない。
目の前で頭を下げている栗山さんに、僕は何を云ったらいいのだろうかと戸惑い、その姿を正視するのにためらいがあって、つい麻衣子の方を見てしまっていたが、そのままにしておくわけにもいかない。
栗山さんが僕に謝りたいこと……僕は、まだ彼女を信じていていいのだろうか。
「綺麗な……綺麗な映像でしたね」
僕は云った。
栗山さんは、静かに頭を上げると「はい」と答えた。
穏やかに笑うその姿は、隣で様子をうかがっていながらも笑顔をみせている麻衣子よりもずっと、千鳥のイメージに似つかわしい。
「僕は今、綺麗な映像にしてくれたことを感謝するべきなのだろうと思っています」
「はい」
「けれども……あなたは謝ってくれるのですね」
「はい。先生」
「僕は好きにしてくださいといいました。覚えていますか?」
「はい。覚えております」
「好きにしていいといった以上、今更、横車を押すようなことはしたくない。だから、僕は何も云いません」
僕は淡々と、できるだけ淡々と冷静に話すよう努めた。彼女もまた、粛々と僕の言葉を聞いていた。
「僕は、自分の原作が傑作だとも絶対だとも思っていません。むしろ穴だらけの欠陥品だと思っています」
そう、評論家に指摘されずとも僕にはわかっていた。僕の『あめゆき』が綺麗な作り事でしかないということは。それでも、あの時、『あめゆき』を書いていた時の僕に必要なのは究極の綺麗事、絵空事の夢物語だった。痛いばかりの現実感などもうたくさんだったのだ。たとえ虚構でしかなくても、僕は千鳥を綺麗なものとして留めておきたかった。
「それでも、こだわりはあります」
「はい」
「あなたにはそれがわかってくれていると思っていました。だからこそ、あなたになら任せていいと思いました」
「はい」
栗山さんは、僕のことをまっすぐに見つめている。それは、初めて僕の元に訪れてきたときと変わらない瞳だった。
『千鳥に紅(べに)をさしてあげたいと思いませんか』
それが、彼女が僕を口説き落とした言葉だ。
映画やテレビドラマにしたいという話がいくつかくる中、僕は断り続けていた。
交渉しに来る人の中には、熱心な読者だという人もいたし、お世辞口で作品を褒め称えてくれる人もいた。提示される金額に気持ちがぐらつくこともあったが、僕は僕の『あめゆき』を人手に任せるなどしたくなかった。
栗山さんにも、一度は同じように断った。
けれども、彼女のその言葉は、僕の中にゆっくりとゆっくりと浸透していった。
ちょうど同じ頃、文庫化をするからと出版社から『あめゆき』の再校正がまわってきた。僕は読み返しながら、自分で作りあげた絵空事、綺麗な硝子細工のようではあるけれどその中身の無さ、薄っぺらさに嫌気がさしていた。
僕は『あめゆき』を書くことによって僕自身の中の何かが浄化されたことを否定するつもりは無い。むしろ僕は僕の『あめゆき』の世界を愛しているといえる。それはできの悪い子ほどかわいいとか、そういう愛ではなく。僕の愛するもので作られた世界、それが『あめゆき』の世界なのだ。
けれども、人形のように白いだけの千鳥は、本当の千鳥……いや、ちとせ……僕の幼くして亡くなった愛しい妹の現実からはひどくかけ離れている。
……千鳥に紅をさすこと。
それは一体どういうことなのだろうか。
硝子細工のようなはかなくて壊れやすいままの僕の『あめゆき』の世界で、白いままに住まう人形のような千鳥。
僕が『あめゆき』の千鳥に与えてやれなかったものは一体なんなのだろうか。
彼女にはそれがわかっているのだろうか。
いや、彼女だけでなく僕にもわかっていた。
紅……それは言葉のとおり化粧を施すことでもあり、そして、「べに」ではなく「あか」。
何よりも千鳥にかけていたのは、「あか」である血だ。
口唇の紅、ほほを染める赤、くるしくて胸をかきむしったみみずばれの痕、ごほごほと吐き出される血の赤。
辛い色だった。
病院のベットに横たわるちとせ。
彼女が毎日見ていた色は、白と赤であって、けっして白だけではなかった。
けれども僕は、血を認めたくなくて、『あめゆき』の世界を白く白く塗りこめた。
ちとせの口唇は赤くてかわいらしかったのに。
ちとせがうれしそうに笑うと、上気するほほはそれは愛らしかったのに。
僕は、そのかわいらしさ、愛らしさもまた、一緒に白の中に塗りこめてしまったのだ。
それは無意識でもあり、意識的でもあった。
僕の『あめゆき』の中でちとせ……千鳥はもう、白いままでしかいられない。
いや、僕の千鳥は白いからこそ千鳥なのだ。
それでも……と、僕は期待した。
『千鳥に紅をさしてあげたいと思いませんか』
僕は、その言葉とまっすぐに見つめてくる彼女の瞳に期待した。
そして僕は、必要以上に期待してしまった自分にあきれつつ、先ほどまで目の前に繰り広げられていた綺麗な、綺麗な映像を眺めていたのだった。
「葉子さん、紹介してくれるんでしょ」
物思いにふけるように黙り込んでしまった僕と、僕の言葉をただ待っている栗山さんの横で、物怖じした様子を見せずに、麻衣子が口を開いた。その明るい声に、止まってしまった時が動き出す。
「え、そ、そうね」
栗山さんがあわてて「千鳥役の月城麻衣子です。よろしくお願いします」「こちらは原作者の川原恭司先生よ」と、互いのことを紹介し、麻衣子に頭を下げさせた。
麻衣子は「よろしくおねがいしまーす」と云ってにっこりと笑った。
「わぁ、まい、小説家の先生とお話したことって無いから、うれしい」
麻衣子が、地元の中学――二年のときに東京の中学に転校したらしい――の現国教師と僕が、顔も声も似ていると云い「なつかしー」などどはしゃいでいるのを尻目に、栗山さんが僕に云う。
「川原先生、もう一度、もう一度チャンスをいただけますか」
「チャンス?」
「はい。もしも言い訳を許していただけるなら……」
言葉を止め、僕の顔をうかがう彼女に、ゆっくりとうなづいた。
「すべてを今日はじめてみたとは云いません。ただ、ラストシーン。少なくともあれだけは私が今日はじめてみたのだと信じてください」
「……わかりました」
僕が云うと、彼女はようやくほっとしたように笑った。
多分、僕は綺麗なだけの映像を見せられたとしても、きっとこんなに憤ることは無かっただろう。だって、僕の『あめゆき』が薄っぺらなことは、もうとうにわかりきっていたのだから。僕は僕の薄っぺらな部分を埋めてもらいたくて映画化を望んだのだから。
それでも、僕には『あめゆき』の中にこだわりがあった。
先ほど見せられたラストシーンは、その唯一ともいえるこだわりが粉砕されていたのだった。
「ねぇ、葉子さん。深刻? まい、邪魔? 小説家の先生とお話してみたいんだけどな」
麻衣子が、居心地が悪そうに栗山さんに問いかけた。
「いえ、大丈夫よ。もうすんだわ。……川原先生、まいちゃんの相手、していただいてよろしいでしょうか」
勘弁してくれ。そう思わないでもなかった。会議室のあちらこちらでは、すでに単なる感想から議論に変わっての会話がなされている。僕の手を離れて、美しい映像に美しい音楽にと、映画という芸術に昇華させようと動いている人たち。この場で僕に出来ることなど、きっと何もなく、すぐにでも立ち去りたい、そんな気分だった。けれども、興味津々といった様子でにこにこと笑っている麻衣子に、アイドルと話す機会なんてこちらのほうが願ったりかなったりかもしれないという気持ちがかすめ、思わずうなづいていた。
「ね、先生、千鳥って、先生の妹さんがモデルってほんと?」
「ああ、そうだよ」
僕と麻衣子のふたりは、ペットボトルのお茶を片手に会議室から出て、廊下にあるソファに並んで座っていた。
「もう亡くなっちゃったの?」
「そう、妹が死んでから、『あめゆき』を書いたんだよ」
少し神妙な顔をした麻衣子に、「もう八年も前のことだから」と云うと、こくりとうなづく。
そして、なんとなく気まずいままに、同じようなタイミングで、お茶を口にする。
ふたりして無言のままに次の言葉のきっかけを手繰っていると、会議室から出てきた男の大きな声が、ふたりの間の沈黙を破った。
「やっぱりさ、これ、月城じゃなくて西野の方が向いてたんじゃね」
「でも、西野はすでに映画デビューしてますから……まぁ、三番手、四番手と、格が落ちても今は彼女たちの天下。月城でも、映画デビューをゲットできたのは大きいですよ」
下世話な会話だった。
男たちが歩いているところからは、ソファに麻衣子が座っているのは見えないだろう。
でも、先程まで一緒の部屋にいて、まだ部屋の中には彼女の関係者だってたくさん残っていることはわかっているだろうに、躊躇なくこんな会話できてしまう。何とも醜い話だけれど、きっと、これが彼女たちの現実の一端なんだろう。
西野というのは麻衣子と同じグループのリーダー格の娘で、彼女たちの中でも一番人気を誇っている。確かに、明るく溌剌とした印象の麻衣子よりも、大人っぽい印象の西野の方が、千鳥には向いているかもしれない。それでも、こんな風に比べられるなんて穏やかであるはずないと、顔をこわばらせる僕に、「平気、よくあることだから」と麻衣子が笑う。ちっとも平気そうに見えないひきつった笑顔だったが、僕はうなづいた。
麻衣子が大きく深呼吸をする。
もう一口、ペットボトルのお茶をのんで、そして、きゅっとペットボトルのふたを締めた麻衣子が、口元をほころばせ、まっすぐに僕を見る。
そして、満面の笑み。
先ほどまでのこわばりなど微塵もない笑顔は、テレビで見るより間近な分、その効力も抜群だった。
アイドルがアイドルらしくとみせる明るいその笑顔は、「こわばった」でなく「つよがった」なのかもしれないけれども、美しく最強の笑顔だ。
僕は多分、さっきの男の発言も、彼女が垣間見せたこわばった笑顔も、見なかったことにするのが正しいのだろう。テレビの裏側など、普段見ることが無いように。
「ええと、ね、先生。私の千鳥、どうだった?」
――仕切り直し。
言葉の裏にもうひとつ、そんな声が聞こえてくるような気がした。
「綺麗だったよ……けれど……」
――君は千鳥ではないね。
僕はその言葉をあわてて飲み込んだ。これは、例え裏でも含めてはいけなかったのに。
「けれど?」
「いや、何でも無いんだ」
「ええぇ、云いかけてやめるなんて、気になるよ。先生も、西野ちゃんの方がよかった?」
「いや、そんなことないよ」
僕の手をつかみ、迫ってくる麻衣子に閉口しながらも、僕は聞いた。
「あのさ、麻衣子ちゃん、原作読んでないでしょ」
その言葉に、麻衣子の動きが止まった。
「あ、あれ? なんでばれちゃったの?」
その言葉と共に、僕の手から離れる。そのはずみか、意識してかはわからないが、わずかに座る位置も遠ざかったようだ。
「……あ、で、でもね。本は買ってあるのよ。寝る前に読もうと思って、ちゃーんと枕元においてはあるの。最初のほうは読んだ……のよ。マネージャーさんに云われたし……って、あれ、あ、や、云われなくても読もうと思って……ああ、ごめんなさいっ」
あわて始めた麻衣子だが、シナリオ段階からして原作と差異があった。読まなくても問題などなかっただろうし、むしろ邪魔になったかもしれないと、僕は思っていた。
「あ、いいよ。いいよ。原作を読んでないことを怒っているわけじゃないんだ。ただね、きっと、何を云っているんだかわからなかったんだろうなぁって思って」
「何が……あ、わかった。あれでしょ。ラストの……」
怒っていないという言葉に安心したのか、ちょっと落ち着いたようで、そうするとまた溌剌とした印象に戻る。覗くたびにくるくると変わる万華鏡の様だ。
「そう、あれだよ」
「ねぇ、あれ、なんなの?」
「あめゆじゅとてちてけんじゃ」
「へ?」
「だからね、本当は、『あめゆじゅとてちてけんじゃ』って云うんだよ」
僕の言葉に、大きな目を、さらに大きくさせている。
「あめゆじゅとてちてた? ……ますます呪文みたいね」
呪文……確かに呪文のようなものかもしれない。
「ははは、呪文か、そうかもね。宮沢賢治って知ってるかい?」
「知ってるわ。ほら、あれでしょ。銀河鉄道の話とか、セロ弾きの……なんですっけ」
「ゴーシュ。セロ弾きのゴーシュだよ」
「ああ、それそれ、カッコウやたぬきが出てくるのよね。ジブリのアニメで見たわ」
アニメかよっ、と、突込みを入れたくなったが、多分、今時はそんなもんなんだろう。
「そう、ジブリのアニメにあるよね。その宮沢賢治という童話作家の詩に、『永訣の朝』というのがあってね、その中に出てくる言葉なんだ」
「どういう意味なの?」
――どういう意味なの?
その質問を受けたのは、初めてではなかった。
僕の小さな妹が、何度も何度も僕に投げかけてきた言葉だ。
僕だってまだ子供で、でも、いろんなことを尋ねてくる妹の質問に答えて「おにいちゃんすごーーい!」と云ってもらうのが好きだった。だから、たくさんの本を読んだし、たくさん勉強もした。
いつも触れ合えるほどの側にいることはかなわなくて、時にガラスの向こう側に行ってしまう妹と、僕が一緒に遊ぶことができるのは、物語の中だけで。だからこそ、僕ら兄妹は、物語の世界で、夢のようにやさしく、お菓子の家のように甘く、常春の世界で幸せに、幸せに、せめて物語の中だけでは元気で幸せにと過ごした。
実のところ、妹の病気のために父親は仕事に、母親は看病にとかかりっきりだった。さみしくないと、恨まなかったと云ったら嘘になる。ただ、「ちとせはお兄ちゃん子だからね」という言葉が、そしてその笑顔が僕の支えだった。妹が僕を頼りにしていたのだと、依存していたのだと両親も医師も云うけれど、きっと、僕の方が妹に依存していたのだと思う。
「あめゆじゅはね、あめゆきって意味なんだ」
そして僕は、いつか妹にしたのと同じ答えをする。
目の前にいる少女は、人差し指を立てて、何かを考えるようにして頬にあてる。
「……あめゆき……あ、映画のタイトルだ」
「そう、あめゆき」
本のタイトルじゃないんだなと思ったが、そこはもう、どうでもいい。ちとせは「なんだかおいしそう!」と笑ったのだけれど、麻衣子はまだすこし、難しい顔をしている。
「あめゆきとてちてた?」
「ああ、いや、とてちてけんじゃ……とってきてくださいって事だよ。賢治には結核の妹がいてね、その妹が死んでゆく朝、ちょうどみぞれが降っていてね。彼女が賢治に、あめゆきをとってきてくださいといった言葉なんだよ」
「そうなの」
麻衣子はまだ何かを考えているようだった。
「原作だとちょうど二章あたりに、千鳥がその宮沢賢治の詩を読んでもらうくだりがあるんだ。この映画ではカットされているようだからね。原作を読んでないとわからないよね」
「ああ、それでばれちゃったんだ」
「そう、麻衣子ちゃんの発音の仕方がね、あ、これはこの言葉を知らなくって云っているんだなって、それがよくわかった」
――僕がずっと憤っていたこと、栗山さんが頭を下げた理由、それは、この宮澤賢治の詩を一緒に読んだことをカットした事に加え、ラストシーンに千鳥がいう「あめゆじゅ」の発音が違っていたことだった。
「わぁ、ごめんなさい」
「いや……」
目の前で大げさなリアクションをしながら謝る少女は、きっとかなり動揺している。僕もまた、動揺していた。こうして謝ってくれる彼女たち――そう、麻衣子だけでなく栗山さんも――のせいなどではなくて。彼女たちを責める言葉など、僕は持ち合わせていなかった。
ただ、悲しい。それだけだ。
それももう、何が悲しいのかさえわからない。そんなに一緒に読むシーンが大事だったのかと云われると、答えに迷う。
原作小説の中には他にもたくさんのエピソードがあり、確かに、その場面にはインパクトもないし転換部でもなくて、ごくごく日常の一コマだった。さして重要ではないかもしれない、いや、むしろ冗長であり、余談であり、カットしたのは至極正しい判断だったのかもしれない。
でも。やはりラストの「あめゆじゅ」は、賢治の妹の言葉と同じでないと駄目だと思うのだ。
一方では、どうでもいいとも思っている。
こだわる事なんてなくて、より美しければ、より優れていればいいのではないかと。いっそ不思議な少女の不思議な呪文のままでもいいじゃないかと。
そう、とても美しい映像に、美しい音楽が流れ、美しくも不思議な少女がすまう、もうひとつの『あめゆき』。
それはそれで、いいのではないだろうか。むしろ、僕はそれを望んだからこそ、映画化に承諾したのではなかったか。
さまざまな思いが渦巻いて、とりとめがなくて、言葉にならない。
せつせつと積もる雪のように、真っ白で重い感情。
僕の中で持て余し気味のこの感情を、ぶつけるべき相手はこの少女ではない。いや、この感情は誰にぶつけるというものでもなく、ただただ僕の中にとどめておくべきものなのだろう。
「でもね。発音が違うなんて、監督も何も云わなかったし……あ、葉子さんがいたら教えてくれたのかなぁ」
「そうだね。栗山さんなら……」
彼女なら、栗山さんならば、僕のこの思いを共有してくれるだろうか。袋小路のようなこの思いの出口を、見つけてくれるだろうか。
「あ、もしかして、葉子さんが云ってたチャンスって、とりなおしってことかな」
麻衣子が笑う。
「ああ、そうかもね」
僕は、思わず微笑んでいた。
「じゃ、まい……がんばるね。まかせてっ」
麻衣子のその笑顔で、僕の中の何かがはじけた気がする。
そして、アイドルとは偶像に由来するのだと、新たにする。
小説の中にすまう千鳥が、僕のために僕が作り上げた偶像であるように。
映画の中にすまう千鳥はきっと、他の誰かが作る他の誰かのための偶像なのだ。
アイドルと呼ばれる少女は、微笑むことで、がんばるねということで、僕の思いも受け止めようとしているのかもしれない。
「ああ、任せる。期待しているよ」
「うん。まい、ちゃんと先生の本、読むよ。字がいっぱいの本だと、眠くなっちゃうんだけど、しっかり読むね」
「そんなに、難しくは無いと思うよ」
「そ、そうかなぁ。まいでも読めそう?」
「多分ね」
目の前でガッツポーズをする少女が、遠い日にベッドの中で「手術、がんばるね!」と云って笑う妹の姿に重なる。
映像の中で無表情で漂っていたこの少女は、僕の描いた幻の少女――千鳥――ではなかったけれど、――ちとせ――現実の妹の姿によく似ている。
「千鳥が……」
――君でよかったよ。
そう云いかけたところに、「せっかくの映画だし、月城にはさ、もっと明るい笑顔を見せてほしかったんだよね」という声が近づいてきた。
僕と麻衣子は顔を見合わせる。先ほど遠ざかって行ったのと同じ声だ。麻衣子は身をすくめて少し怯えた風にみえる。彼女には、声の相手が誰なのかは当然わかっているのだろう。
「オレさぁ、彼女の笑顔が好きなんだよ。なのに、この作品じゃ、笑顔封じ手っしょ、もったいないって」
そう云いながらまた、会議室に入ってゆく。
……もしかして?
麻衣子の目が大きく見開いて、何とも云えない輝きをみせながら、きらきらとした涙がこぼれはじめる。
どうやら、麻衣子よりも西野をかっているわけではなく、麻衣子をかっているからこその不満だったらしい。
例えばアイドル、例えば小説、例えば映画――音楽や絵画や彫刻や、人々が愛でるさまざまなものたち。
偶像へと向けられる期待や言葉は、勝手なものであり、害であり益であり、糧にもなるものであり。同じ言葉でも、さまざまな思いの発露であり、帰結であり。必ずしも含む思いが同じとは限らない。同じ言葉に励まされたり、傷つけられたり、表と裏と、己と他と、決して同調するものだけでなく、違うだけのものでもなく。……人の言葉は、そして望みは、なんとも、ややこしい。
「あ、あれ? やだ。……先生、ごめんなさい」
泣き笑い、というのはこういうことを云うんだろう。
麻衣子は、胸に手を当てて落ち着こうとしていたが、涙はあふれて、頬はゆるみ、ゆらゆらと揺れている――瞳が、体が、心が。
泣きながら、そして笑いながら、くしゃりとした笑顔は、崩れてぐしゃぐしゃだったけれど、とても美しくて綺麗だった。
「いいよ。……大丈夫」
厳密に云ったら何が大丈夫なんだかわからない。でも、彼女は僕の前で泣くつもりなどなかったに違いないことはわかる。泣いていいんだと云いたかったけれど、口には出せなかった。
だから、大丈夫。そんな言葉になった。そして、つい無意識のままに、妹を励ますときにしていたように、彼女の頭、額のあたりを二回、軽くたたいた。
麻衣子は、「ますます、石ちゃん先生だ……」といって、さらに涙を、そして思いをこぼし始めた。
「あのね、まいね……平気なんかじゃなかった。でも、平気って思うしかなくって。がんばってもがんばっても、いいよって云ってくれない人はどこにでもいて。まいよりも西野ちゃんがいいとか、さっちゃんとかゆきちゃんのほうがずっといいよっていう人とか……まいのことなんて嫌いってはっきり云う人もいて。でも、まいだけががんばってるわけじゃなくて。みんなみんながんばってて……それでもダメだって云われてもね。そんなこと、いちいち構ってられないって思うんだけど、そういう不満の声があることも忘れちゃいけなくて。西野ちゃんのことは大好きだけど、大嫌いでもあって……」
複雑な思いを吐露し続けている少女の声を聞きながら、血を吐いているちとせを思いだしていた。
そして麻衣子は、似ているといっていた地元の中学の現国教師に、僕を重ねているのだろう。
重き病に侵されて。遠く故郷を離れて。それでも――。
頑張っている。頑張っている。
――命がけ。
そんな言葉を思う。
頑張れ。頑張れ。
ただ、そばにいてやることしかできない無力を思い、果たして、己がこれほどまでに何かを頑張っていただろうか顧みる。
頑張ろう。頑張ろう。
少女の涙のきらめきに、何かとても大切なものを見つけた。
そんな気がしていた。
「ここにいたんですね」
しばらくした後、落ち着いて涙を拭いた麻衣子が、屈託のない笑顔に戻ったころ、栗山さんがやってきた。
「あ、すみません。もう時間ですか?」
立ち上がる麻衣子を栗山さんが制す。
「そろそろだけれど、まだ大丈夫よ。ちょっとスケジュール調整の打合せをしているから……一部、撮りなおしが決まりました」
麻衣子に状況を説明して、僕の方に向かって一礼しながら、撮りなおしが決まったことを告げた。
「はい。よろしくお願いします」
僕はそれだけを答えた。それで十分だと思っていた。栗山さんは僕から託された『あめゆき』を、彼女自身が納得のいくようにと努めているのだから。
「やったね! まい、頑張るね」
僕のほうを向いて、麻衣子がみせたガッツポーズに、栗山さんが少し驚いた様子になる。
「永訣の朝の話を、彼女にしたんですよ」
僕が云うと、なんらかの合点がいったのだろう、栗山さんの顔がほころぶ。
「ありがとうございます。……頑張ってね。まいちゃん」
「はい!」
麻衣子の笑顔に向けて、「僕は、君が千鳥でよかったと思うよ」と、声をかける。
再び笑顔は崩れて涙がこぼれ、そしてまた、笑顔――。
そろそろ戻りましょうという栗山さんに促されて立ち上がる。
「あ、先生。聞き損っちゃったんだけど、最後に、もうひとつ聞いていい?」
「いいよ」
「あのね。あめゆきって何?」
「えっ?」
「まい、あめゆきって、天国ゆきって事だと思ってたんだけど……とってきて下さいって……変、だよねぇ」
「あ、ああ……」
僕は、あまりにも意外な質問に、どう答えたらいのか、答えよりも先に笑いがこみ上げてきた。
そんな所から、もうすでに彼女にはわからなかったんだなと云うことが可笑しくて。
そんなことさえわからなくても、平気でいる人たちを相手に憤っていた己が可笑しくて。
「あ、やだ、先生。笑ったりしてひどーいっ。まいの物知らず、はなはだし過ぎでサイテーなのは勘弁して」
「いや、最高だよ、麻衣ちゃん」
そう、最高だ。
実はみぞれでしたというよりも、ずっと素晴らしい答えじゃないか。
「だからね、まい、さっき、あめゆじゅとてちてたって聞いて、なんていうんだっけ、行進するときにラッパ鳴らすの……」
「ラッパ……ああ、進軍ラッパ、かな? ずいぶん古いこと知ってるんだね」
「そう? アニメかなんかで見たよ」
「そうか、天国行きのラッパなんだね」
「うん、あめゆきとってちってったっなの」
そう云って、ラッパを吹くマネをする麻衣子に、僕は胸が熱くなった。
天国ゆきだというのは、きっと、ラストシーンで、天女さながらに昇天する千鳥を観ての発想だろうけれど。とてちてたで、天国ゆきの進軍ラッパだと思うとは……。
――本当に素晴らしい。
例え発音など違っていても、映像の中の千鳥は、天国ゆきというイメージをしっかりとはらみ、美しい場面に仕上げていたのだ。僕は、自分の思いにだけ囚われ、麻衣子が、監督が、栗山さんが、何を考えていたのかに思いをはせようともせずにいた。本当に可笑しくて、そして、己が情け無い。
あめゆきとはみぞれのことだと麻衣子に云い、「そうなんだ、ちょっとおいしそうだね」と云う笑顔をみながら、僕は思う。
妹が、ちとせが亡くなったという現実から逃れたくて、ちとせへの想いを白い結晶にし、硝子細工に閉じ込めるようにして『あめゆき』を書き上げた。
そして、その後、僕は筆をとることにためらいがあった。
見ないようにする事もまた、見ている事に他ならない。
白を意識すればするほど。虚構を夢みればみるほど。赤はせまり、事実は容赦なく突き刺さる。
評論家にいわれるまでも無く、僕自身が小説を書くことにこれ以上踏み入れば、白いまま、絵空事のままではいられないことに気がついていた。臆病風に吹かれ、勇気を無くして、痛い思いをするくらいならと、僕は小説から逃げていたのかもしれない。
目の前の少女は、僕の想像を、こだわりを、ためらいを難なく飛び越え、あめゆきは天国行きの進軍ラッパだと笑う。
ちとせの中にもまた、この少女と同じように、僕の想像をはるかに超える明るさがあったはずだ。
そう、ちとせ自身は最期の朝、穏やかに笑っていた。「お兄ちゃん大好き」それが僕に残した最後の言葉だった。やはり宮沢賢治の妹のトシが「私はひとりでゆく」といったように、ちとせもまた、それこそ進軍ラッパに見送られるような心地で死出の旅にでたのではないだろうか。
ただ儚いのではなく、ただかわいそうなのではなく、もちろん、綺麗で美しいだけではなく。現実感をもつことがすべて痛々しいことではなくて、もっともっと違う何か。
目の前の少女の笑顔がきらきらと輝いているように。
そして、病気や困難、誹謗中傷のような心無い言葉にめげたとしても、立ち向かっていく強さと勇気と。
美しいことも醜いことも全部ひっくるめた上での笑顔。
少女の中で、たとえ何かが死んだとしても、絶えず生まれ続けているきらきらとした輝き。
僕は、他人に期待するのではなく、僕自身に期待しないといけなかったのだ。
僕自身の手で、千鳥に紅をさしてあげないといけなかったのだ。
とうにわかっていたことかもしれない。でも、ずっと立ち止まって過ごしていた。
進め、進めと、最期の時まで高らかに鳴り響く、進軍ラッパのように。
僕は、僕の中の勇気を奮い起こし続け、進んでいかなくては。
本当の、本当の最期の時に、あめゆきの、天国行きの進軍ラッパを聞く日まで。
きらきらと輝き続けられるように――。
「ありがとう」
唐突にお礼をいった僕に、目をまん丸とした麻衣子と、優しく微笑んでいる栗山さんをみながら、帰ったら久しぶりに小説のアイデアを書きためていたノートを開いてみようと思っていた。
了