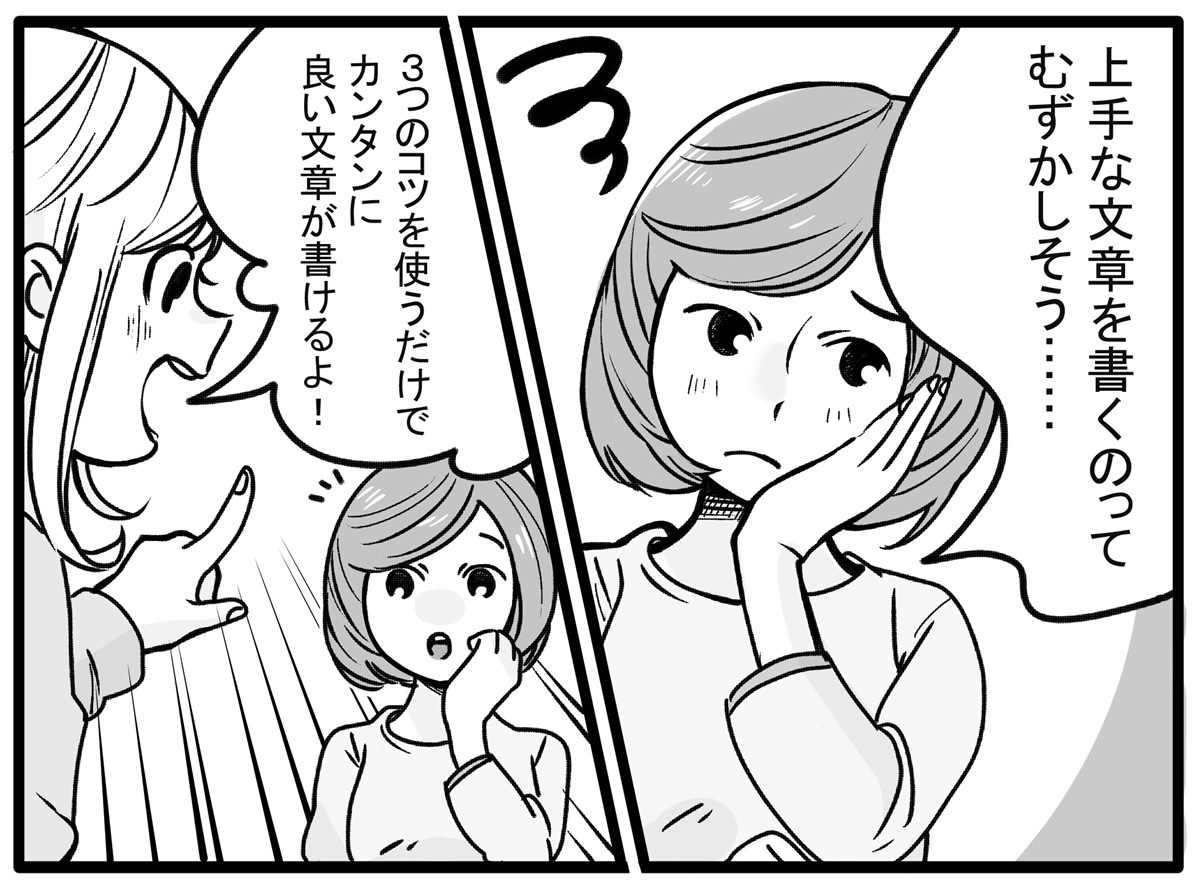
誰でも簡単に良い文章が書ける3つのコツ
- 一文を短くする(約40文字が目安)
- 改行を多めにする(ページに3割くらいの空白を)
- 難しい言葉や漢字を使わない(漢字使用率は20%以下に)
良い文章とは、わかりやすい文章です。
わかりやすい文章とは、かんたんな言葉で書かれた一文が短い文章です。
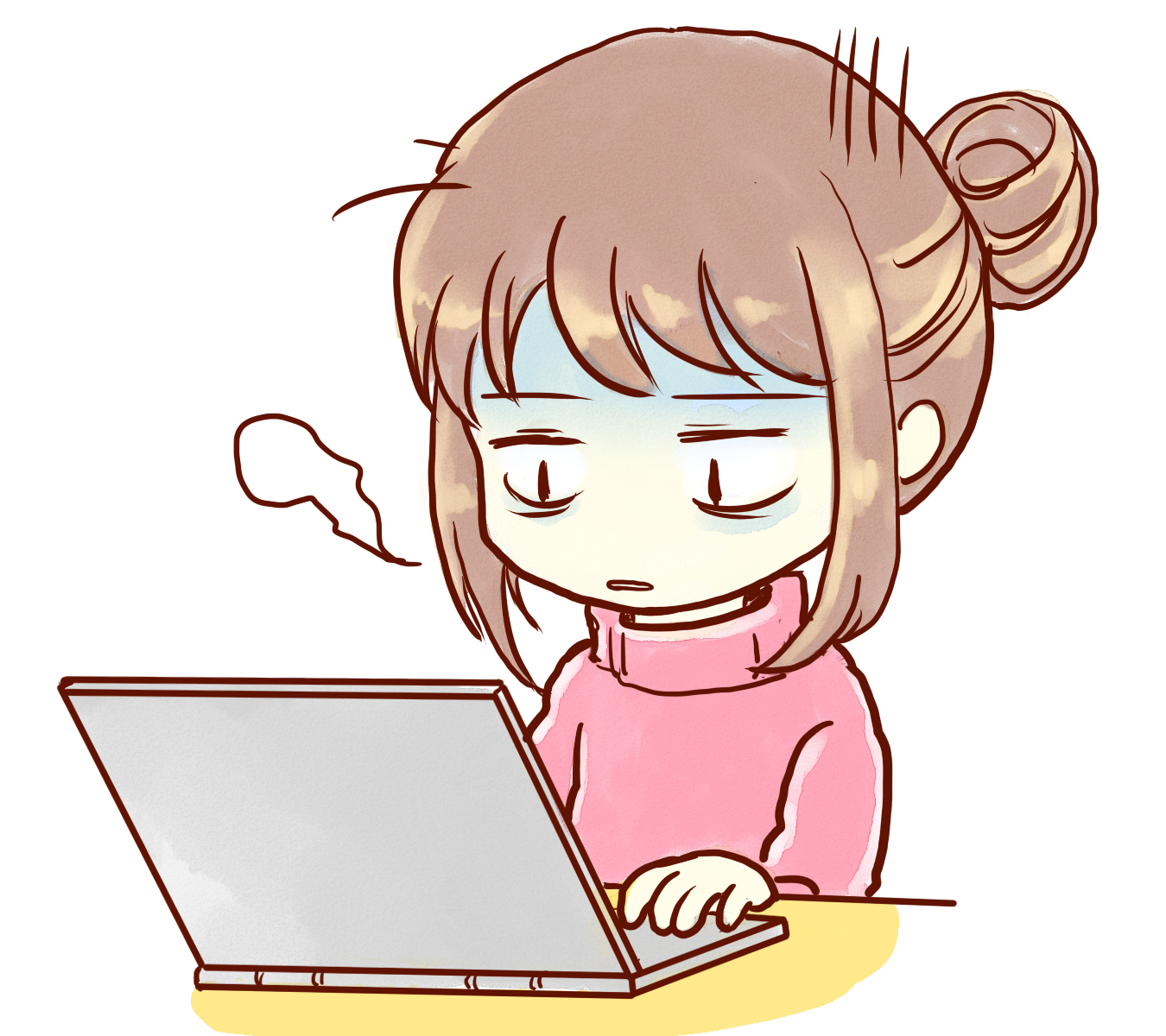
逆に悪い文章とは、一文が3行以上も続く。
改行が少なく、文章がぎっしり詰まっている。
難しい漢字や専門用語が多い文章です。
こういう文章は読んでもらえません。
一文を短くする(約40文字を目安に)
一文の長さは、文章術の本を読むと約40文字程度を目安にした方が良いと出ています。
プロのラノベ作家の文章は、一文の長さが二行以内に収められています(ほぼ一行)。
三行以上になるような長い文は稀、例外です。
一文が短くなると、主語と述語の関係が明白になり、伝えたいことが誤解なく伝わるようになります。
コツとして、ほとんどの文章は「が」で2つに分けられます。
「遊ぶことは大切ですが、勉強もおろそかにはできません」
↓
「遊ぶことは大切です。
しかし、勉強もおろそかにはできません」
一文が長くなったら、「が」で2つに分けることができないか考えてみましょう。
改行を多めにする(ページに3割くらいの余白を)
人は文章がぎっしり詰まっているのを見ると、読む気が失せます。
改行を多めにして画面に空白を作りましょう。
ページを開いた時、3割くらいの空白があった方が、読者は抵抗なく読めます。
昔からラノベは、改行が多くて、本の下半分はメモ帳として使える、などと言われてきました。
これは読んでもらうための正しい工夫です。
例文として、ヒット作『陰の実力者になりたくて!』3話(2018/01/なろうに投稿)の文章を引用します。
「ブシン流って最近王都で流行ってるらしいね。見せてほしいな」
「くそが、見せてやるよおらぁ!」
ボスAの攻撃。
いや、うん、余裕。一生懸命剣を振ってるけど、僕は剣を構える必要すらない。ボディワークとかステップワークで余裕余裕。
このようにセリフや段落ごとに空白の行を加えて、読みやすくしています。
また一文が非常に短いのが特徴です。人気作は、読みやすさにとても気を使っているのがわかります。

難しい言葉や漢字は使わない(漢字使用率は20%以下に)
2000年代まで、ラノベは主に中高生がターゲットだったので、中学1年生でも楽に読める文章が理想とされてきました。
現在(2018年ごろから)では、なろう系ラノベは構造がシンプルであるため、小学生の間でも人気になっていると言われており、小学5,6年生でも読めるくらいの簡単な文章がオススメです。
また、ベストセラーの漢字使用率は20%以下というデータがあります。
2014年の調査ではFacebookでもっとも「いいね!」される記事の漢字割合は「10%~30%」と出ています。
漢字率10~20%に押さえるくらいが、読んでもらいやすい文章です。
これはラノベに限った話ではなく、『黒い家』『悪の教典』で有名なミステリー作家、貴志祐介さんも、あまり重要でない言葉については、なるべくひらがなを使うように配慮しているそうです。
漢字を使いすぎると、読む人にストレスを与えるからです。
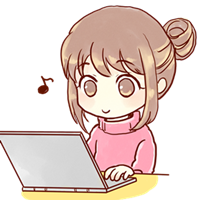
良い文章とは、かんたんな言葉で書かれた一文が短い文章です。
説明や描写は最低限に。文章力より「読みやすさ」
説明や描写が多いと、読みにくくなって読者に嫌われます。
読者が興味があるのは、キャラクターのセリフや行動です。
説明や描写は最低限にしましょう。たくさんの説明をしても、読者は覚えていません。
特にWeb小説は、電車での通勤時間や、昼休みのちょっとした隙間時間にスマホから読まれているので、読者はじっくり読んでおらず、3日前に読んだ説明など忘れています。
必要に応じて、主人公の行動や巻き込まれる事件などのイベントを通して、説明する形が望ましいです。
また、設定はなるべく複雑にせず、シンプルにしておくと、読者に理解してもらいやすいです。
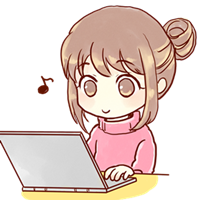
重要なのは文章力より「読みやすさ」です。名文を書く必要はありません。描写もあまり必要ないです。
文章が下手な人は「そして」「……」「――」を多用する!
ベテラン作家さんに教えてもらった「誰でも簡単に上手な文章を書くコツ」。
以下の3つを多用しないようにする。
- 三点リーダー「……」
- ダッシュ「――」
- 接続詞の「そして」
特に文章が下手な人は「そして」を多用する。
「そして」は、文章の前後の脈絡が繋がっていなくても、文章が繋げられてしまう魔法の言葉で、多用すると意味不明な文章になりやすいのです。
「そして」をなるべく使わずに文章を書くようにすると、意味がわかりやすい文章が書けるようになります。
「……」や「――」などの記号を使い過ぎてたらマイナスとかはありますか?
●ラノベ新人賞の下読みジジさんの回答
文章力のチェック欄にマイナスがつきます。
普通に読みにくいですし、できれば文章表現力を見せていただきたいこともありますので、記号による便利な余韻に頼りすぎることなく、言葉で表現できる部分はぜひ言葉で表現してください。

一人称と三人称一視点。小説の語り方
小説の文章は、一人称か三人称一視点で書くのが一般的です。
「みろよ」
俺の目の前に差し出されたのは一丁の拳銃だった。
どうしてこんなものをコイツが……?
「みろよ」
太郎の目の前に差し出されたのは一丁の拳銃だった。
どうしてこんなものをコイツが……と太郎はいぶかしんだ。
一人称小説の書き方
- 主人公視点で物語が進んでいく。主人公(視点人物)が物語を語る。主人公が見たこと、思ったことで地の文が構成される。セリフは主人公の話したことか聞いたこと。
- メリットは、主人公により感情移入してもらいやすくなること。
- デメリットは、視点となる人物以外の心情や視点となる人物が知りえないことは書けないこと。これを解消するため、章が変わったら主人公以外の人物に視点が移ることもあります。1話は主人公視点、2話はヒロイン視点になるなどです。
例文として、ヒット作『乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった…』一話(2014/07 なろうに投稿)の文章を引用します。
「こんにちわ、お加減はいかがですか?クラエス嬢」
第三王子ことジオルド王子様がその天使のように美しい顔を曇らせ私に声をかけてくれた。
あぁ、なんて可愛らしいお顔なのでしょう.
このように物語の視点となる主人公の「見たこと」「思ったこと」で書かれている、主人公の体験記が一人称小説です。
文章に主人公の性格がモロに反映されるため、主人公の個性が際立ち、読者はより主人公に感情移入しやすくなります。
「俺は○○に行った」「私は返事をしなかった」と主人公の一人称で書かれているため一人称小説と呼ばれます。
ネットで読める一人称の人気作
なろう系ラノベには一人称小説が多いです。
一人称は初心者でも簡単に書くことができますが、奥が深く、極めるのが難しい書き方です。
小説の初心者、及び超上級者にオススメ。
三人称一視点小説の書き方
- 物語の語り手が、主人公に密着して、主人公の見た光景を中心に物語を語るという形式。映画に例えると、カメラ(視点)が主人公のちょっと後ろくらいにある感じ。
- メリットは、主人公が直接目にしていない物や主人公が知らない情報も書けること。
- 注意点として、主人公(視点をさだめたキャラ)以外の人物の思ったことは書いてはいけない。これをやると読みにくくなる。「視点がブレる」という状態になる。
章が変わったら主人公以外の人物にカメラ(視点)が移ることもある。
1話は主人公視点、2話はヒロイン視点になるなど。
例文として、人気作『リビルドワールド』一話(2017/02 なろうに投稿)の文章を引用します。
少年もここが自分を殺すに足る非常に危険な場所だと知っている。表情の険しさがそれを示している。それでも自分の意思で、死の危険を覚悟して足を踏み入れたのは、その危険に見合うものがここにあるからだ。少なくとも、スラム街の子供という自身の安値の命よりは遥かに高額なものが。少年はそれを求めてここに来た。
少年の名は、アキラといった。
アキラが溜め息を吐いて呟く。
「……碌な物がねえな。命懸けでここまで来たっていうのに。……もっと奥まで行かないと駄目か?」
このように物語の視点となる語り部が主人公に密着して、その様子を語るのが三人称一視点小説です。
語り部は視点を定めた人物(主人公)の内面も語りますが、視点を定めた人物以外の内面は語りません。主人公以外の人物の内面を語る場合は、場面転換などして、別の人物に視点(カメラ)を定めます。
一人称とは異なり、主人公が直接目にしていない物も書ける自由度の高さがあります。
ネットで読める三人称一視点の人気作
三人称一視点はやや難易度が高い、中級者、及び上級者向けの書き方です。最初は、一人称を書くこととをオススメします。
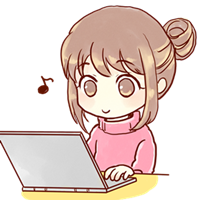
一人称と三人称一視点が同じ作品内で混在している小説もあります。基本的に、どちらか一方の書き方で統一するのが良いです。
また、両方とも書けるようになると執筆できる作品の幅が広がります。
小説の世界観に合った言葉を使おう!
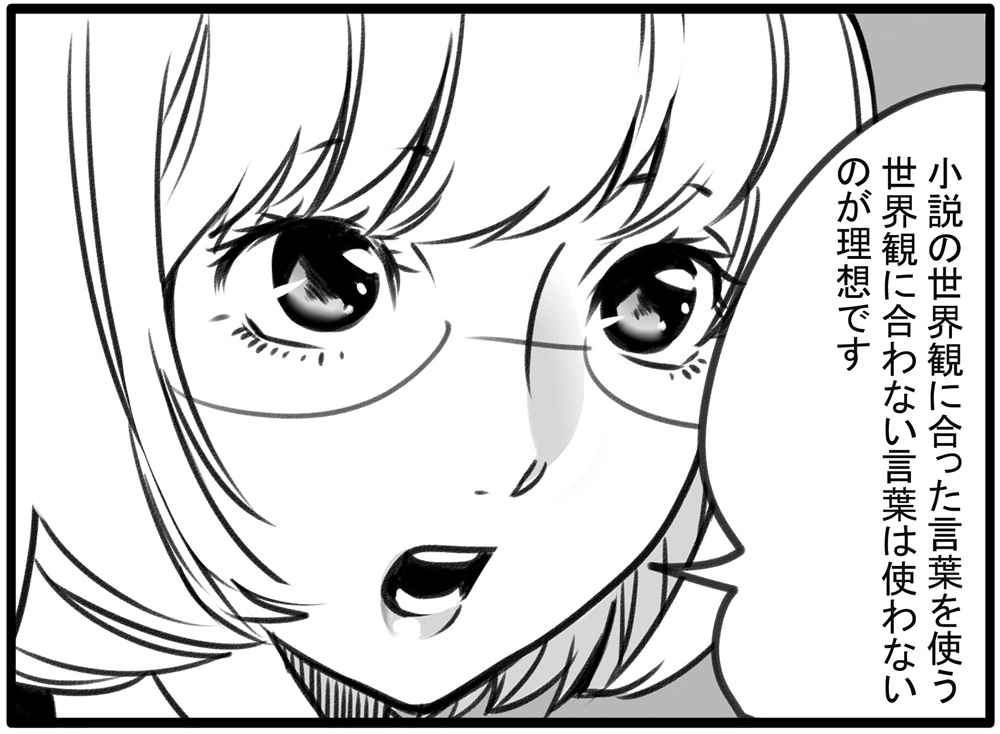
良い文章を書くためのコツとして「難しい言葉や漢字を使わない」ことをご紹介しました。
これには例外があります。
古代中国の宮廷物など、時代がかった難しい言葉が合う世界観の場合は、作品世界を表現するために「下賜」「傾国」「卑賤」といった、その世界に合った言葉を使った方が良いです。
シリーズ累計発行部数130万部以上の人気作『薬屋のひとりごと』(2014/8 刊行)は、古代中国風の帝国の後宮を舞台にした小説です。
後宮のただれた美しさを文体で表現するために、「下賜」「傾国」「卑賤」など、わたしたちの日常生活ではまず使わない、時代がかった難しい言葉を使っています。
また可可树にカカオ、巧克力にチョコレートとルビを振るなど、古代中国の文化を表現するために言葉を選んでいます。
これによって、物語の架空世界にすっと入っていくことができるようになっています。
以下は、クリエーター専門学校AMGの小説・シナリオ学科で文章の講師をされている作家、餅月望さんへの質問と回答です。
サボらないこと、手を抜かないことではないかと思います。私の中で最も評価が低い文章というのは、定型文のような描写をしていながら、その描写が適切でないときです。
例えば「雪のように白い肌」というのは、結構使い古された表現だと思います。美しい表現だからこそ頻発するし、私もよく使いますが、雪がない世界観のファンタジー世界でこれを使うのはいかがでしょうか?
使い古された定型文を思考停止気味に当てはめてしまい、自分なりの表現をする努力を怠ってしまうと、そこには成長がないのではないかと思います。

小説の文章というのは、物語世界に合った物を選ばなくてはならないのです。
例えば、ハイファンタジーで「核兵器のような威力の魔法」などと書いたら、核兵器などその世界には存在しないので、ハイファンタジーの世界を壊しかねません。
逆に異世界転生物なら、主人公が核兵器の知識を持っているので「核兵器のような威力の魔法」と書いてもOKです。
文体の言葉選びは、物語の雰囲気、シリアスなのかコメディなのかによっても変わってきますし、世界観を伝えることよりも、わかりやすさを重視した方が良い場合もあります。
『薬屋のひとりごと』では、主人公の猫猫を次のように紹介している文章があります。
時代と場所が違えばきっとこう呼ばれていることだろう、『狂科学者(マッドサイエンティスト)』と。

マッドサイエンティストとは、古代中国風の世界観に合わない言葉ですが、ライトノベルですので、わかりやすさを重視するためにあえて使っているのだと考えられます。
また、狂科学者という漢字にルビを振ることで、中華っぽさを演出し、違和感を最小化しています。
実力がある作家さんは、言葉選びに気を使っているのですね。
文章の推敲(見直し)の6つのコツ。環境を変えて読む
推敲とは書いた文章を見直して、荒を探してよりよいものに書き直すことです。
プロのラノベ作家は、平均5回は作品を見直して改稿するそうです。最初から完璧なものを作る必要はなく、推敲を繰り替えして質をあげていけば良いのですね。
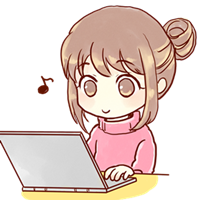
小説をどこかに投稿する場合は、最低でも1回は、推敲しましょう!確実に文章の質が上がります。
推敲のコツは「環境を変えて読む」ことです。新しい視点から読めて、荒に気づきやすくなります。以下、推敲の6つのコツです。
- 最重要。一日以上、時間を開けてから読み直す。一日経つと、より客観的に読者に近い立場から自分の小説を読むことができます。
- PCで書いた小説をスマホで読む。(小説はスマホで読むのが一般的なので、ぜひ!)
- 横書きの文章を縦書きで読む。(日本語は横書きにすると、なぜか安っぽく見える性質があります。縦書きにすると、まったく違った印象になります)
- アナログで読む。PCで書いた小説をA4用紙に印刷して読む。
- 場所を変える。家で書いた小説をファミレスで読む。
- 時間を変える。夜に書いた文章を朝に見直す。

最強の校正法。簡単に誤字脱字が0になる!無料の文章読み上げソフトを使う
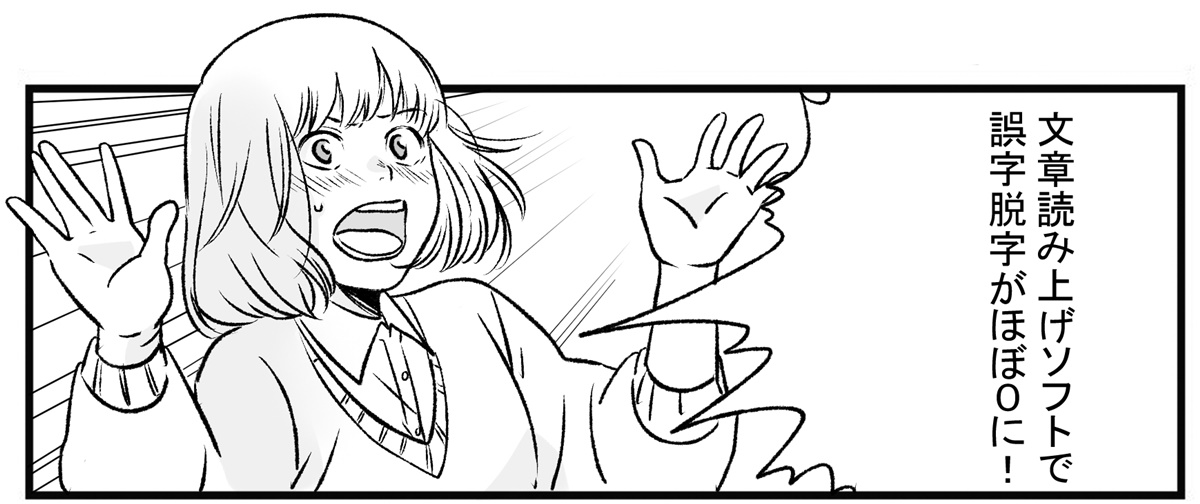
文章読み上げソフトを使って、文章を読み上げさせると100%誤字脱字やおかしな表現に気づくことができます。
私もブログの内容をYouTubeの動画にするために、ボイスロイドで読み上げさせていますが、音読させると100%誤字脱字に気づけます。
プロ作家も使っている方法なので、おすすめです。
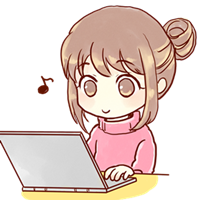
誤字脱字だけは、何度、推敲をしても出てきてしまうものなので、オススメです。
無料でダウンロードできる棒読みソフトを使えば十分です。

以下は、無料で使えるPC用文章読み上げソフトです。テキストファイルだけでなく、Word文書も読み上げてくれるので、書いた小説を音読で聞きたい場合にオススメです。
ワンランク上の文章の書き方
『の』の3連続をさけよう。不必要な言葉を削る
私の父の好きな小説のタイトルは『人間失格』だ。
上の文章では『の』が3連続で続いてしまっています。
『の』が3つ以上続く文章は、稚拙でゴチャゴチャした印象を読む人に与えます。
一文に『の』を3つ以上入れないようにしましょう。
父の好きな小説は『人間失格』だ。
『私』『タイトル』といった、いらない修飾語を消して『の』を減らしました。
書かなくてもわかる不必要な言葉は削ってしまった方が良いです。
すっきりとした、わかりやすい文章になります。
『の』の連続は、夢中で文章を書いていると、ついうっかり起こしてしまいやすいミスなので気をつけましょう。
同じ音を重ねない
読むとなんだか引っかかるという文章があります。
その原因の1つが、同じ音を重ねているコトです。
「学校に行ってから、言うよ」
この文章に違和感を感じませんか?
「行って」「言う」という同じ音を重ねていると引っかかりを覚えます。
もし、同じ音が重なりそうになったら、別の言葉に書き換えてみましょう。
「学校に行ってから、話すよ」
「学校に着いてから、言うよ」
「学校に到着してから、話すよ」
同じ音の重なりを見つけるためには音読が一番です。
音読がめんどくさい場合は、無料の文章読み上げソフトを使うと良いです。
耳で聞いてみて、違和感を感じる部分を探してみましょう。
× まだ試用期間中の新薬を使用する。
○ まだ試用期間中の新薬を服用する。
× 高山さんの私用のパソコンを使用したい。
○ 高山さんのパソコンを使用したい。
例2では、「私用の」という無くても意味が通じる言葉を省くことで、音の重なりを回避しています。
不必要な言葉を省くと、文章が短くなり、読みやすくなるというメリットもあります。

二重表現に注意
二重表現とはセンテンスに新しい意味を追加せず、元の意味を繰り返している言葉です。
「上に上がる」「下に下がる」「普段の平熱」「馬から落馬」「国の建国」などといった文章が二重表現に当たります。
「上がる」というのは、上に行くことに決まっているので、「上に上がる」という言い方はしません。
落馬とは馬から落ちるコトを言うので、「馬から落馬」という言い方は変です。
二重表現は不自然かつ意味のない文なので、使わないように気をつけましょう。
二重表現を回避できれば、文章をより短く、わかりやすくできます。
以下、二重表現と、修正例をいくつか上げます。
○ 夏の登山をやります。
○ 協力する。
○ 第1に。
○ 補足説明する。
○ 明言する。
○ 結論。
○ 結末。
一見、どこが重複なの? と思えるモノもありませんでしたか?
文章を書き上げた際は、二重表現になっていないか良く注意して見直しましょう。
誤解の原因。あいまいな文章に気を付ける
日本語は構造的にあいまいな言語です。
この点に注意しないと、あなたの意図したことが読者に正確に伝わらない、誤解を生む原因になります。
サーファーの兄は消防士。
この例文の意味をすんなり理解できるでしょか?
おそらく、作者の意図を誤解してしまう人が大勢出てくると思います。
この文章は、二通りの意味に解釈できるのです。
どちらの意味が正しいか、この文章からでは判断できません。
斎藤くんは、水無月さんのようにうまく文章が書けない。
こちらも以下の二通りの意味に解釈できるあいまいな文章です。
(佐藤と水無月さんの文章のうまさは同レベル)
(水無月さんの方が文章がうまい)
このように否定文は別の意味に取られることがあるので要注意です。
この他にも、例えば「全生徒が不合格だ」を「全生徒が合格していない」と書くと、「合格していない生徒もいる」という部分否定と解釈する人もいます。
日本語はあいまいな言語であることを頭に入れて、意味が正確に伝わる文章を書くようにしてください。
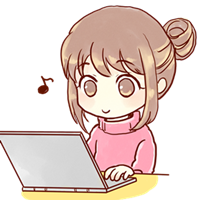
自分では気づくにくい点なので気をつけましょう。









