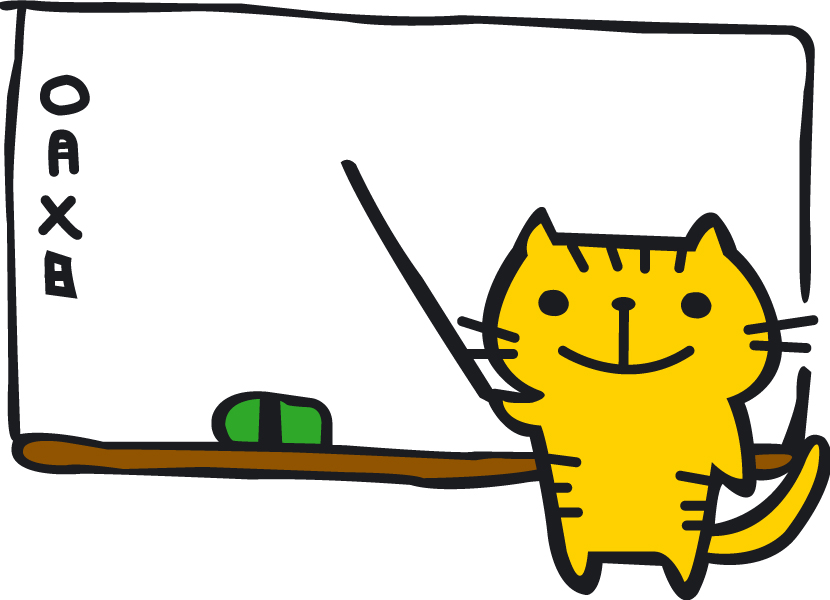サイラスさんの質問2015/01/24
『アニメとラノベの表現特性の違いとは?』の回答ありがとうございました。
視覚表現はユーザーに想像という負担をかけない。
文章媒体はユーザーに想像を強いないと成立しない。
ユーザーに想像を強いるかどうかという観点は意外でした。
個人的には、取り扱える情報量の量かなという感覚がありました。
私は、文庫のラノベ1冊を読み終わるのに、1時間から2時間分掛かるのですが、アニメだと半分、マンガだともっと短く、ラノベ1冊分の話を消化しているという感覚があり、文字情報って、映像にするとかなり圧縮できる。だから、アニメと同じことをすると、どえらい量の文字を使わないと表現できないという感覚があります。
それが、読者(ユーザー)に想像を強いるということなんですよね。
「(理解/補完までの)時間の差」も大きなちがいです。
ぱっと見てわかる映像や絵と、説明を重ねることで、映像以外の部分(心情や背景)もわかる代わりに補完までの時間がかかる文章では、取るべき手段が同じでよいわけがありません。
だから、流行の研究や、他の作品を読むことが重要になるのですよね。
読者が、想像しやすいものを取り入れることで、読者の理解や想像の負荷を落としてあげる。逆に、他の作品を読んで、理解に苦しむ作品とぶち当たることで、何が、理解に苦しむかという感覚を把握することで、初めて読者のことを考えられるのかもしれませんね。
●下読みジジさんの回答
どれだけ文字を尽くしても、読者にその文字の意味や描写を頭の中で映像化してもらえなければ無駄になってしまいます。
だからこそ、読者対象層ががんばって考えることなく、こちらがはしょっている部分までさらっと脳内再生してくれるよう、わかりやすい描写、わかりやすい文章が重要であると思っています。
だから、流行の研究や、他の作品を読むことが重要になるのですよね。
ある意味、今現在の読者はどこまで読み込むことを普通と捕えているのか。それを知るために必要とも言えますね。
読者が、想像しやすいものを取り入れることで、読者の理解や想像の負荷を落としてあげる。逆に、他の作品を読んで、理解に苦しむ作品とぶち当たることで、何が、理解に苦しむかという感覚を把握することで、初めて読者のことを考えられるのかもしれませんね。
インプット作業には、まさにそのあたりの感覚をつかむことも入ってくるものと思います。